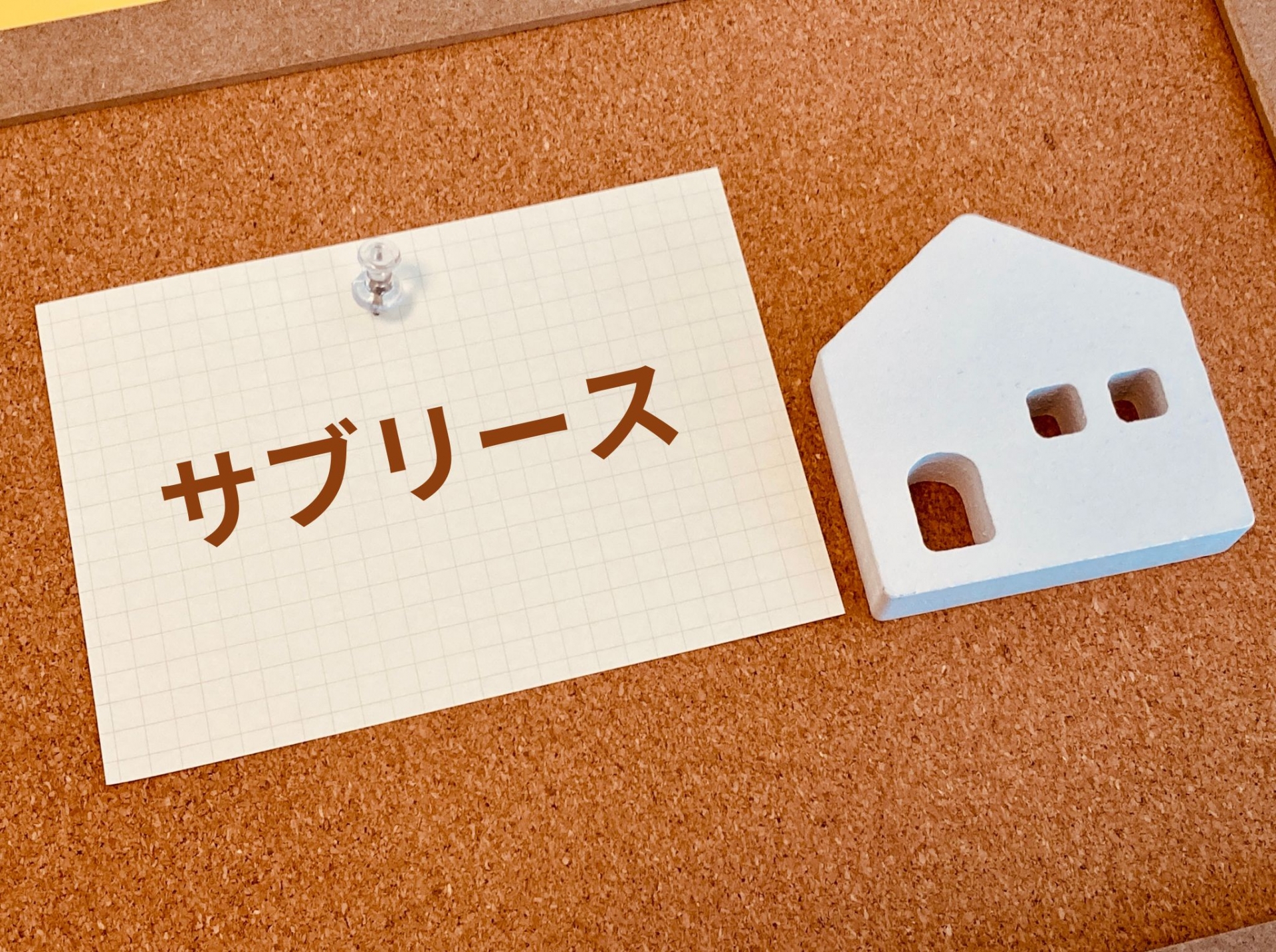
サブリース会社が賃料の支払いをしない場合について、サブリース契約の解除、ユーザー(転借人)との賃貸借契約の締結、賃貸借契約の内容、敷金返還義務の引継ぎ、ユーザーに対する賃料請求などについて述べてみました。
1 はじめに
アパートの所有者であるAからサブリース会社であるBがアパートの1棟借りをし、その後、一般ユーザーであるC1、C2、C3などに、アパートの部屋を転貸したとします。この場合、Bに賃料不払いがあったらどうなるでしょうか。
2 契約解除と明渡し請求

考え方としては、通常の賃料不払いの場合と同じで、Aは、Bに対して、相当の期間を定めて賃料の支払いを催告するとともに、賃料の支払いがない場合は、賃貸借契約を解除する旨を通知します。
そして、それでもBが未払い賃料全額の支払いをしないときは、AとBの賃貸借契約は解除になり、AはBに対して、アパート全体の明渡しを要求することができます。
そして、AとBの賃貸借契約が解除になれば、その賃貸借契約を基礎としていたBとC1、C2、C3などとの賃貸借契約も終了しますから、AはC1、C2、C3などに対しても、各部屋の明渡しを要求することができます。
3 転借人との新たな賃貸借契約締結
① 合意による場合

このように、AはBとの賃貸借契約を解除した上、BとC1、C2、C3などに対して、明渡しを求めることができるのですが、アパートなどの場合は、Aは、Bを排除した上で、C1、C2、C3などと、個々に賃貸借契約を結び直し、直接、C1、C2、C3などに賃貸したいと考えることが多いでしょう。
その場合は、Bと話し合いができる状態であるなら、まず、Aは、Bとの賃貸借契約を合意解約した上で、C1、C2、C3などと個々に賃貸借契約を締結します。
AとBの賃貸借契約と、BとC1、C2、C3などとの賃貸借契約とでは、期間や賃料などの点で、その内容が違っていますが、AとC1、C2、C3などとの間で締結される賃貸借契約の内容をどちらに合わせるかは、AとC1、C2、C3などとの話し合いによって決めることになります。
ただ判例上、Bのような賃借人の立場にある者が、合意解約によって契約当事者から抜け、A(賃貸人)とC1、C2、C3など(転借人)との間で、直接、賃貸借契約が成立する場合には、その契約内容は、BとC1、C2、C3などとの間で成立していた賃貸借契約の内容を引き継ぐということになっています。
つまり、BとC1、C2、C3などとの賃貸借契約の内容を、AとC1、C2、C3などとの賃貸借契約の内容とする、というのが原則ですから、通常は、この原則どおりにした方がよいでしょう。
ただし、後述するように、Aは、BがC1、C2、C3などに対して負っていた敷金返還義務を引き継ぎますから、敷金分のお金をBから受領できないときは、賃料が高い分、高い敷金返還義務を負うことになります。
なお、Bは、Aに対して、未払い賃料があるのですから、この支払いをどうするのか、AはBと話し合いをしなければなりません。
また、Aは、BとC1、C2、C3などとの賃貸借契約を引き継ぎ、Bに代わってC1、C2、C3などに対する賃貸人になるのですから、C1、C2、C3などがBに差入れていた敷金につき、その返還義務を引き継ぐことになります。そこで、この支払いをどうするのかについても、話し合いをしなければなりません。
② 合意ができない場合

①で述べたように、AとBとで賃貸借契約を合意解約できればいいのですが、Bは、なかなか合意解約に応じないのが一般的です。なぜなら、合意解約をすれば、それ以降は、AがC1、C2、C3などの賃貸人になり、C1、C2、C3などからの賃料はAに振り込まれてしまうからです。
そこで、Bが、速やかに合意解約に応じないときは、Aは、Bの賃料不払いを理由に、Bとの賃貸借契約を早急に解除する必要があります。
その上で、C1、C2、C3などと個々に賃貸借契約を締結します。具体的には、まず、Aの名前で、C1、C2、C3などに対し、
・ Bの賃料不払いによって、AとBの賃貸借契約は解除になり、BとC1、C2、C3などとの賃貸借契約も終了したこと、
・ Bは、C1、C2、C3などの賃貸人ではなくなったので、今後の賃料は、Aの口座に振り込むこと、
・ Aは、引き続きC1、C2、C3などにアパートの貸室を賃貸するつもりなので、C1、C2、C3などは、Aと賃貸借契約を結び直して欲しいこと、
という内容の通知を出します。
その後、AあるいはAの管理会社がC1、C2、C3などを個別に回り、状況を説明して、C1、C2、C3などと賃貸借契約を締結し、賃料もAに振り込んでもらうようにします。
AとC1、C2、C3などとの賃貸借契約の内容は、すでに述べたとおり、AとBの賃貸借契約ではなく、BとC1、C2、C3などとの賃貸借契約と同じものにします。
また、この場合は、AはBから、アパートの各貸室の鍵を返還してもらうことができませんから、C1、C2、C3などの了解を得た上で、Aの費用で各貸室の鍵を交換する必要があります。
なお、Aは、Bに対して、これまでの未払い賃料を請求しなければなりませんし、BがC1、C2、C3などに負っていた敷金について、今度は、AがC1、C2、C3などに返還しなければならなくなるのですから、Bに対して、この敷金に相当する金額も請求しなければなりません。
ところで、賃貸借契約が解除になるには、ある程度の期間を要することになります。この期間中、Aがとくに手段を講じなければ、BはAに、賃料を支払わないのにかかわらず、BはC1、C2、C3などから賃料の支払いを受けるということになってしまいます。
このような事態は何としても避けたいところです。ところで、民法613には、賃借人が賃料を支払わないときは、賃貸人は、直接、転借人に対して、賃料の請求をすることができるという規定があります。
そこで、Bが賃料を支払わないときは、AはC1、C2、C3などに対して、Bに支払うべき賃料をAに支払うよう通知を出しておくのも、一つの方法でしょう。
このような通知が行くと、C1、C2、C3などとしては、賃料をBに払ったらいいのか、Aに払ったらいいのか分かりませんから、Bに対する支払いをストップし、その分を留保するなり、供託するなりすることが期待できますから、最終的に、C1、C2、C3などから、Bの未払い賃料を回収できる可能性が高くなります。
4 サブリースの場合の注意点

このように、Aは、BやC1、C2、C3などに対して、明渡しを請求することができるのですが、Bから貸室を借りているC1、C2、C3などの名前が分からなければ、C1、C2、C3などに対して明渡しを請求することはできませんし、明渡し訴訟を起こすこともできません。
また、BとC1、C2、C3などとの契約内容(とくに、賃料、敷金の額、賃貸借期間)が分からないと、Aが、C1、C2、C3などと新しく賃貸借契約をしようとするときに余計な手間がかかります。
したがって、BがC1、C2、C3に対して、貸室を転貸した時は、Aは、その賃貸借契約書のコピーをもらっておき、C1、C2、C3の名前や、BとC1、C2、C3の契約内容を把握しておくべきです。その後に、転借人が変更になった時(たとえば、C1が退去して、その貸室にC4が新たに入居した時)も、BとC4の賃貸借契約のコピーをもらっておかなければなりません。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






