
本コラムでは、製造業や建設業で広く使用される一般動力機械、特に混合機(ミキサー)が原因で発生する重篤な労働災害について、解説します。
労災保険給付だけでは不十分な慰謝料や逸失利益を会社から確実に得るための、損害賠償請求を並行して進める具体的な方法と、弁護士に依頼するメリットについて解説を致します。
混合機とは?:危険性をはらむ産業の必須機器

混合機、すなわちミキサーは、食品製造、化学、製薬、建設、樹脂加工といった日本の基幹産業を支える上で欠かせない汎用動力機械です。
その目的は、異なる複数の物質を均一に混ぜ合わせることにあり、用途に応じて非常に多岐にわたる種類が存在しています。
液体やペースト状の物質を混ぜる撹拌装置、粉体を混ぜるための粉体混合機、高粘度の物質を練るニーダーなどがありますが、どのタイプにも共通しているのは、強力なモーターによって駆動される回転翼や羽根といった稼働部を内蔵しているという構造的特徴です。
この「強力な回転運動」こそが、作業効率の向上という利便性を提供する一方で、ひとたび事故が発生した場合に深刻な結果を招く、本質的な危険性の根源となります。
実際に稼働中の混合機に作業者の身体の一部や衣服が接触し、あるいは巻き込まれてしまえば、切断、挫滅、さらには死亡に至る重篤な傷害につながる可能性が極めて高いのです。
混合機が原因となる労働災害のほとんどは、この回転部や稼働部への接触による「巻き込まれ」や「挟まれ」事故であり、多くの場合、作業手順の逸脱や安全装置の適切な設置・運用が欠如していることによって引き起こされています。
混合機で多発する重大事故の類型

混合機に関連して発生する労働災害は、その危険性の高さから、軽傷で済むケースが非常に少なく、死亡事故や重度の後遺障害を伴うケースが後を絶ちません。弁護士が特に多く相談を受けるのは、以下の四つの典型的な事故類型です。
事故類型(1)巻き込まれ・挟まれ事故(稼働中の接触)
この事故類型は、混合機による労災の中で最も頻繁に発生し、かつ結果が最も重篤化しやすいものです。
事故の典型例としては、稼働中の機械の原料投入口や点検窓から作業者が手を伸ばし、投入材料の様子を確認したり、材料の詰まりを解消しようとした際に、回転翼に手や腕が巻き込まれるという状況が挙げられます。
また、安全カバーやフェンスが外されたまま運転が続行されている場所で、近くを通行した際に衣服や身体が回転部に接触し、巻き込まれてしまうこともあります。
あるいは、混合翼の回転部とタンクやケーシングのわずかな隙間に手や腕が挟まれ、強烈な圧力を受ける場合もあります。これらの事故の結果、指や腕の切断、複雑骨折、組織が激しく破壊される挫滅創、さらには内臓損傷や失血死に至ることがあります。
事故類型(2)清掃・点検中の事故(不意な起動)
機械が停止している状態での作業中に発生する事故も、決して少なくありません。
主に混合機内部の清掃、メンテナンス、あるいは部品交換のために作業者が機械内部に立ち入っている、あるいはカバーを開けて作業している最中に発生します。
この種の事故の最大の原因は、電源が適切にロックアウト(遮断・施錠)されていないことです。別の作業員が誤って運転スイッチを入れてしまったり、連動している他の機械の起動によって混合機が不意に動き出してしまったりすることで、内部にいた作業者が巻き込まれたり、圧潰されたりするのです。
作業指示書や安全手順書に定められた手順が守られていなかったり、そもそも手順書が存在しなかったりといった、安全管理体制の不備が背景にあります。
事故類型(3)落下・転落事故
大規模な混合機やタンク型の混合機では、原料投入口が工場の二階や高所に設けられている構造のものがあります。
このような高所での作業中に、原料の運搬や投入作業を行っている作業員が、足場や作業床の不安定さからバランスを崩したり、安全帯の使用が徹底されていなかったりした結果、投入口から転落してしまうケースです。
また、投入口の周りの手すりや覆いが不十分であったり、老朽化していたりすることも、転落のリスクを高めます。転落による頭部外傷、脊髄損傷、全身打撲といった重傷を負うことになります。
事故類型(4)爆発・火災事故
主に粉体混合機や、可燃性の液体・溶剤を扱う混合機で発生する事故です。
粉体(小麦粉、化学粉末、樹脂など)を混ぜる際に、粉塵が空気中に高濃度で浮遊し、混合翼やモーターの摩擦熱、または静電気火花といった着火源によって粉塵爆発が発生することがあります。
また、可燃性の溶剤を混合中に、静電気対策が不十分であったために引火し、火災につながるケースもあります。これらの事故は、作業者に全身熱傷や爆風による外傷を与え、死亡に至る可能性もあります。
混合機で発生する労働災害の現状と背景

厚生労働省が公表している労働災害の統計を参照すると、「挟まれ・巻き込まれ」は死亡事故の主要な原因の一つであり続けており、混合機はこのタイプの事故が頻繁に発生する典型的な危険源となっています。
混合機による事故が重篤化しやすい背景には、安全対策における「人間のミスは必ず起こる」という考え方が欠如していることが挙げられます。
特に、表題にあるような巻き込まれ、挟まれといった重傷事故が発生する典型的なケースには、いくつかのパターンが見られます。
第一に、生産効率を上げるためや、詰まりを解消するためといった理由で、安全カバーが開くと機械が停止するインターロック装置や、安全スイッチが、作業者自身の判断や上司の指示によって安易に無効化または解除されている状態での作業です。
第二に、清掃・点検・修理といった非定常作業の際に、機械の電源を完全に遮断し、再起動できないように施錠し(ロックアウト)、標識(タグアウト)を付けるというLOTO(ロックアウト・タグアウト)の手順が徹底されていないケースです。
第三に、運転を止めるまでもないと安易に判断し、稼働中の混合翼の近くに手を差し入れたり、工具を入れたりしてしまう危険源への不用意な接近があります。
そして第四に、経験の浅い作業者に対し、混合機の持つ潜在的な危険性や、事故を防ぐための正しい作業手順に関する安全教育が著しく不足していたという背景です。
これらの事態を未然に防ぎ、労働者の生命と身体の安全を守るための厳格な義務は、会社、すなわち使用者に課せられています。
労働安全衛生法・民法715条と会社(使用者)の責任
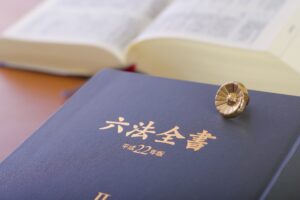
混合機が原因で労働災害が発生した場合、被害を受けた労働者やその遺族は、国が運営する労災保険による迅速な給付を受ける権利を有します。
しかしながら、労災保険の給付とは別に、事故の原因が会社の安全管理の不備に起因する場合、会社に対して直接、損害賠償を請求するという選択肢が法的に認められています。
会社が負うべき法律上の義務

会社は、労働安全衛生法に基づき、混合機を含む機械設備について、危険を防止するための具体的な措置を講じる義務があります。
これには、適切な安全カバーやインターロックの設置といった機械の構造的安全性の確保、作業手順の確立と周知徹底、特定の作業における作業主任者の選任、そして何よりも労働者に対する危険有害性に関する教育の実施などが含まれます。
これらの義務を怠った結果として事故が発生した場合、会社は行政指導や罰則の対象となるだけでなく、民事上の責任を追及される際の大きな根拠となります。
さらに、会社は労働契約に基づき、労働者がその生命および身体の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする安全配慮義務を負っています。
混合機事故において、会社の安全対策の不備、例えばインターロックの未設置や作業手順の不徹底などが認められた場合、この安全配慮義務に違反したとして、民法上の債務不履行に基づく損害賠償責任を追及することが可能になります。
これが、労災事故における会社への損害賠償請求の最も重要な根拠です。
また、事故の原因が、現場の管理者や他の従業員の具体的な不法行為、例えば安全手順を無視した運転操作などによる場合、会社は民法715条に基づき、その行為者(被用者)と一体となって使用者責任を負うことになります。
労災保険給付と会社への損害賠償を並行して請求する方法

混合機による重度の労災事故の被害者が、経済的な補償を十分に得るためには、「労災保険」と「会社への損害賠償請求」という、性質の異なる二つの制度を正しく理解し、それらを並行して進めることが不可欠です。
労災保険で受け取れる給付の種類
労災保険は、会社の過失の有無を問わず、業務上の災害に対して迅速に給付を行う公的な保険制度であり、生活の安定を図るための基礎的な補償を提供します。
具体的には、治療費を全額支給する療養(補償)給付、休業(補償)給付、そして治癒後に後遺症が残った場合にその等級に応じて支給される障害(補償)給付や、死亡した場合の遺族(補償)給付などがあります。
労災保険の申請は、会社の協力が得られない状況であっても、労働者自身で進めることが可能です。
会社への損害賠償請求

労災保険は迅速な補償を目的としているため、その支給額には限界があり、特に精神的な苦痛に対する慰謝料や、将来得られたはずの全額の逸失利益といった項目は労災保険ではカバーされません。
したがって、労災保険の給付では不足する、損害の差額については、前述の安全配慮義務違反や使用者責任を根拠に、会社に損害賠償請求を行う必要があります。
具体的に会社に請求できるのは、労災保険で賄いきれない休業損害、そして最も重要なのが、事故による精神的苦痛を償うための入通院慰謝料や後遺障害慰謝料です。
また、後遺障害が残った場合の逸失利益についても、労災保険の障害給付で賄いきれない差額を請求対象とします。
この請求手続きは、まず会社との示談交渉から着手しますが、交渉が難航した場合には、訴訟へと移行して、会社の責任を法的に確定させる必要が出てきます。
混合機事故の解決を弁護士に依頼するメリット

混合機による労災事故は、重篤な傷害を伴うために請求額が非常に高額になりやすく、会社の法的責任の追及が複雑化する傾向にあります
この複雑な手続きを弁護士に依頼することは、被害者が治療に専念できる環境を整えつつ、最終的に最大限の経済的補償を受けるために不可欠な手段となります。
弁護士に依頼するメリットは多岐にわたりますが、最も重要なのは、適正な後遺障害等級の認定サポートを受けられることです。
巻き込まれや挟まれ事故では、指の切断や複雑な機能障害など、重く複雑な後遺症が残ることがあり、後遺障害の等級が一つ変わるだけで、障害給付や会社から受け取るべき慰謝料額が数百万円単位で変動します。
弁護士が介入することで、診断書の内容を精査し、適正な等級認定のために必要な証拠や手続きを指導することで、被害者にとって最も有利な結果を目指します。
また、会社との交渉や訴訟対応をすべて代行することも大きなメリットです。
会社は自社の安全管理体制を否定することを避けようとするため、示談交渉において責任を認めようとしないか、不当に低い賠償額を提示してくるのが通常です。
弁護士が介入することによって、裁判例に基づき、会社の安全配慮義務違反を厳しく立証し、裁判所基準(弁護士基準)に基づく、適正な慰謝料と逸失利益を請求します。
当事務所のサポート内容

当事務所では、事故直後から、今後の見通しや取るべき法的措置について、専門チームの弁護士がご相談に応じます。
交渉や訴訟の準備においては、事故現場や機械の状況、会社の安全管理体制に関する重要な証拠を確認し、後の責任追及に備えます。
被害者の方の具体的な状況を詳細に分析し、個別の事情を反映した適正な損害賠償額を算定した上で、会社側の主張に対しては法的な根拠をもって反論し、依頼者様の利益を最大化するための粘り強い交渉と徹底した訴訟活動を行います。
まとめ

労働災害は、人生を大きく変えるほどの出来事です。一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。被害者の方の正当な権利を守るために、全力を尽くします。
労働災害に遭われてお悩みの方は、まずはご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






