
工場や倉庫の屋根工事、補修作業中に、スレート屋根を踏み抜いて墜落する事故が後を絶ちません。例えば、2024年にも、名古屋市の工場で62歳の作業員がスレート屋根を踏み抜き、約4メートル下に墜落して死亡する事故が発生しています。
スレート屋根は軽量で安価、耐久性もあることから、多くの工場や倉庫で使用されていますが、経年劣化により強度が著しく低下し、人が乗ると簡単に割れてしまうという危険性があります。しかし、見た目には劣化が分かりにくいため、作業員が気づかずに踏み抜いてしまう事故が頻発しているのです。
もし、あなたやご家族がスレート屋根での作業中に事故に遭われたなら、「労災保険が下りるから大丈夫」と安心するのはまだ早いかもしれません。労災保険は治療費や休業中の生活を支える重要な制度ですが、事故によって受けた精神的苦痛(慰謝料)や、将来にわたる全ての経済的損失を補填するものではないのです。
この記事では、スレート屋根での作業中に事故に遭われた方が、ご自身の正当な補償を得るために知っておくべき知識を、事故事例から法的な手続きまで、弁護士の立場から解説します。
スレート屋根での作業中の労災事故とは

スレート屋根の特性と「ふみ抜き」事故の深刻さ
スレート屋根(波形スレート屋根)は、工場や倉庫の屋根材として広く使用されています。一般的には灰色で波型をしており、軽量で安価、一定の耐久性があることから、多くの事業場で採用されてきました。
しかし、スレート屋根には重大な問題があります。
スレート屋根は非常に薄く、劣化すると簡単に壊れてしまう
スレート屋根は、そもそも人が乗ることを想定して作られていません。雨風をしのぐためには十分ですが、人が乗るほどの耐久力はないのです。人が乗ると、足の裏の面積にだけ体重が集中するため、割れてしまう可能性があります。
特に深刻なのは、経年劣化の問題です。設置して何十年ともなると、紫外線や雨風により劣化し、極めて脆くなります。ある試験では、30年ほど経過した波形スレート屋根を新品のものと比較すると、半分以下の強度しかないことが確認されています。具体的には、1点で耐えることができる荷重は30kg程度しかなく、成人男性が乗れば簡単に割れてしまう状態だそうです。
スレート屋根を踏み抜いた場合、作業員は何の支えもなく真下に墜落します。工場や倉庫の屋根は高さが4メートルから10メートル以上あることも多く、墜落した作業員は全身を強く打ち、重篤な傷害を負うか、最悪の場合は死亡に至ります。
スレート屋根での死亡事故の発生状況について
スレート屋根での事故は、決して珍しいものではありません。
厚生労働省の統計によれば、平成18年から平成27年までの10年間で、スレート屋根からの墜落による死亡災害が145件も発生しています。これは年間平均で約15件、つまり月に1件以上のペースで死亡事故が発生している計算になります。
また、地域別に見ても事故の多発が確認されています。例えば、香川県では5ヶ月で4件の災害が発生し、うち3人が死亡しています。茨城県の水戸管内では、約10ヶ月で5件の死傷災害が発生しているとの報告もあります。
死亡事故だけでこれだけの件数ですから、重傷を負った事故を含めれば、さらに多くの被災者が存在することは間違いありません。
スレート屋根での事故の特徴は、重傷や死亡につながりやすいという点です。墜落事故の性質上、骨折、脊髄損傷、頭部外傷など、生命や労働能力に重大な影響を及ぼす傷害を負うケースが大半を占めています。
スレート屋根のふみ抜き事故と「会社の責任」

スレート屋根での事故の多くは、会社側の安全対策の不備が原因で発生しています。法律上、事業者には労働者の安全を守る義務が課されており、この義務に違反した場合には、会社に対して損害賠償を請求することができます。
安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、労働契約法第5条に定められている、使用者(会社)が労働者の生命・身体の安全を確保するために講じなければならない義務のことです。
事業者は、労働者が安全で健康に働けるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。具体的には、事業者は労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負っています。
この義務は、単に法令を守れば良いというものではありません。当該工事現場の実情に応じた転落防止措置を講ずるなど、具体的な状況に応じた配慮が求められます。
スレート屋根作業における具体的な義務

スレート屋根での作業については、労働安全衛生規則第524条に明確な規定があります。
【労働安全衛生規則第524条(スレート屋根等の屋根上の危険の防止)】
「事業者は、スレート屋根、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」
この規定を踏まえ、事業者は以下のような安全対策を講じる義務があります。
作業床の設置
高所作業については、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設置する必要があります。ただし、スレート屋根の上に足場を組むことは現実的には困難な場合が多いため、他の措置と組み合わせて安全を確保する必要があります。
墜落防止ネットの設置
スレート屋根の下部に墜落防止用のネットを張ることで、万が一踏み抜いた場合でも、作業員がネットで受け止められ、地面まで墜落することを防ぐことができます。これは、スレート屋根作業において極めて有効な安全対策です。
安全帯(墜落制止用器具)の使用指示・設備の提供
作業員に安全帯を使用させ、親綱に確実に掛けさせることで、踏み抜いた場合でも宙吊りになるだけで、墜落を防ぐことができます。ただし、安全帯を使用するためには、親綱を固定するための設備を事前に設置しておく必要があります。
事業者は、単に安全帯を用意するだけでなく、親綱の設置場所を確保し、作業員が確実に安全帯を使用できる環境を整える義務があります。
歩み板の設置
幅30センチメートル以上の歩み板を設置することで、体重が板全体に分散され、スレート屋根の踏み抜きを防ぐことができます。歩み板は、スレート屋根の形状や屋根上に突出したボルトの状態等に合わせた専用のものを備え付けることが望ましいとされています。
ただし、歩み板の設置が困難である場合は、墜落防止用のネットを張る、安全帯を使用させるなど、他の方法で安全を確保する必要があります。
過去の裁判例について

スレート屋根の踏み抜き事故については、会社の安全配慮義務違反を認めた裁判例が複数存在します。代表例をご紹介します。
富山地方裁判所高岡支部昭和61年6月24日判決
この事案では、被災者が工事の管理運営を任された責任者であり、被災者自身にも安全対策を講じなかった手落ちがあったとされた事案です。
しかし、裁判所は次のように判示して、会社の安全配慮義務違反を肯定しました。
「事業主は、安全配慮義務に基づき、従業員に多少の過誤があっても事故が生じないよう万全を尽くすべき義務があるところ、被告は右義務に基づき本件工事現場に前記認定の踏み抜きによる墜落防止措置を講ずべきであったにもかかわらず、右義務に違反し、その措置を講じなかったものであるから、仮に、被災者において本件事故につき右過失があったにしても、被告は、本件事故につきその責を免れるものではない。」
「右事案において、会社がスレートの販売、付帯工事の受注、工事の管理運営を業務とし、工事それ自体を下請に出していた場合、その者が営業所の責任者として工事を管理する地位にあったとしても、雇主である会社の労働契約に基づく安全配慮義務違反が否認される理由とはならない」
この判決は、労働者に多少の過失があったとしても、会社が適切な安全対策を講じていなければ、会社の責任は免れないという重要な原則を示しています。
東京地方裁判所平成28年5月31日判決
この事案では、会社の安全配慮義務違反を肯定した上で、労働者が安全帯を親綱に掛ける等の措置を全く講ずることなく、漫然とスレート屋根に上がったとして、2割の過失相殺をした事案です。
判事事項をまとめると、
1 建物の解体工事に従事していた労働者が屋根から転落して死亡した事故について当該解体工事の施工業者である勤務先の会社に安全配慮義務違反を原因とする損害賠償責任が認められた
2 建物の解体工事に従事していた労働者が屋根から転落して死亡した事故を原因とする勤務先の会社の負う損害賠償責任について,当該労働者側に2割の過失相殺が認められた
3 建物の解体工事に従事していた労働者が屋根から転落して死亡した事故について,当該労働者の内縁関係を認定して,その内縁の妻による当該労働者の勤務先である会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した
とまとめられます。
また、裁判所は、安全配慮義務違反について次のように判示しています。
「スレート葺きの屋根に上がる作業を行う際には,踏み抜きによる落下事故の発生する危険が生ずることが明らかである。したがって,当該落下事故の発生を防止するため,当該作業に従事する者の安全帯を親綱に掛けさせ,さらに,当該屋根に上がる際には,その支柱等の上を移動させる等の配慮が必要となると考えられる。」
そして、会社がこのような配慮を怠っていたことから、安全配慮義務違反を認定しました。
一方で、労働者についても、「本件スレート屋根に上がる場合に踏み抜きによる落下の危険が生ずることは被災者にとっても予見することが可能であったところ、安全帯を親綱に掛ける等の措置を全く講ずることなく、漫然と本件スレート屋根に上がった」として、2割の過失相殺を認めました。
これらの裁判例から分かるように、スレート屋根での作業においては、会社に高度な安全配慮義務が課されており、適切な安全対策を講じていなければ、会社の責任が認められる可能性が高いと言えます。
労災事故で被災者が受け取れる補償について

労災保険から支給される給付(補償)
業務中の事故であれば、労災保険から以下の給付が受けられます。
療養給付
労働者が労働災害により病気やケガをしたときに、病院で治療費などを負担することなく治療を受けられる給付です。治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものは、基本的にすべて含まれます。原則として自己負担はありません。
休業補償給付
療養のため働けない期間の4日目から、休業1日につき給付基礎日額(事故前3ヶ月の平均賃金)の60%が支給されます。これに加えて、社会復帰促進等事業として、給付基礎日額の20%が「特別支給金」として支給されますので、合計で給付基礎日額の80%の収入が補償されることになります。
傷病補償給付
労災により病気やケガをして、療養開始後1年6か月を経過しても病気やケガが治癒しない場合には、傷病等級(第1級から第3級)に応じた傷病補償年金等が支給されます。
障害補償給付
治療を続けても症状が改善しなくなった状態(症状固定)で、後遺障害が残った場合に、その等級(第1級~第14級)に応じて年金または一時金が支給されます。
障害等級が1級から7級のときは年金が支給され、8級から14級のときには一時金が支給されます。
スレート屋根からの墜落事故では、以下のような後遺障害が残る可能性があります。
- 脊髄損傷による下半身麻痺:等級1級から5級程度
- 高次脳機能障害:等級1級から9級程度
- 骨盤骨折による機能障害:等級8級から12級程度
- 下肢の骨折による可動域制限:等級8級から12級程度
- 慢性疼痛・神経症状:等級12級から14級程度
会社に別途請求できる損害賠償

労災保険とは別に、事故の原因が会社側にある場合、民法上の不法行為(709条)または労働契約法上の安全配慮義務違反(5条)を根拠に、会社に対して損害賠償を請求することができます。
請求できる理由(会社の安全配慮義務違反または使用者責任について)
前述のとおり、事業者は労働者が安全で健康に働けるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。スレート屋根での作業において、会社が以下のような安全対策を怠っていた場合、義務違反に問われる可能性が非常に高くなります。
- 歩み板、墜落防止ネット、安全帯の親綱設置などの安全措置を全く講じていなかった
- 作業計画書を作成せず、具体的な作業手順を指示していなかった
- スレート屋根の劣化状況を事前に調査・確認していなかった
- 作業員に対する安全教育が不十分だった
- 危険予知(KY)活動が形骸化し、危険な作業に対する注意喚起がなされていなかった
これらの事実が認められれば、会社に過失や安全配慮義務違反があるといえる可能性があります。
損害賠償の内訳
会社に対しては、主に以下の損害について賠償を求めることができます。
| 損害項目 | 内容 | 労災保険との関係 |
| 傷害慰謝料 | 入通院によって受けた精神的苦痛に対する賠償 | 労災では支払われない |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償 | 労災では支払われない |
| 逸失利益 | 後遺障害により将来得られなくなった収入の補償 | 労災給付で不足する部分を請求 |
| 休業損害 | 休業期間中の収入減(労災の8割給付との差額2割+α) | 労災給付で不足する部分を請求 |
| 将来介護費等 | 重い後遺障害で将来必要となる介護費用や住宅改修費 | 労災給付で不足する部分を請求 |
| 弁護士費用 | 賠償請求のために要した弁護士費用の一部 | 労災では支払われない |
逸失利益
後遺障害によって労働能力が低下し、将来にわたって得られたはずの収入が減少してしまうことに対する補償です。後遺障害の等級、事故前の収入、年齢などによって計算され、賠償項目の中で最も高額になる可能性があります。
【逸失利益の計算例】
- 前提条件:
- 事故時年齢:45歳
- 事故前の年収:500万円
- 後遺障害等級:第9級(労働能力喪失率35%)
- 計算式: 年収500万円 × 労働能力喪失率35% × 労働能力喪失期間(67歳までの22年)に対応するライプニッツ係数14.029
- 逸失利益:約2,455万円
慰謝料
慰謝料には、主に2つの種類があります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
事故日から症状固定日までの間、入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する補償です。入院期間や通院期間が長くなるほど、金額は高くなります。
後遺障害慰謝料
症状固定後も、体に痛みや機能障害などの後遺障害が残ってしまったことによる、将来にわたる精神的苦痛に対する補償です。後遺障害の等級に応じて、金額の相場が決まっています。
弁護士基準(いわゆる「赤本基準」)による後遺障害慰謝料の目安は以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
| 1級 | 2,800万円 |
| 2級 | 2,370万円 |
| 3級 | 1,990万円 |
| 4級 | 1,670万円 |
| 5級 | 1,400万円 |
| 6級 | 1,180万円 |
| 7級 | 1,000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
【具体例】
前述の逸失利益の計算例(9級、年収500万円、45歳)の場合、逸失利益(約2,455万円)と後遺障害慰謝料(690万円)だけでも、合計3,145万円を超える請求が可能になります。
労災保険からは、9級の場合、一時金として給付基礎日額の391日分(年収500万円なら約535万円)しか支給されません。その差は約2,610万円にもなります。
労災保険からの給付と会社からの賠償金を合わせて受け取ることで、初めて事故によって生じた損害の全体が補填されるのです。
死亡事故の場合のご遺族への補償

不幸にも労働者が死亡された場合には、ご遺族に対して以下の補償がなされます。
労災保険からの給付
- 遺族補償給付:労働者の死亡当時に労働者の収入で生計を維持していた遺族に対して、遺族補償年金が支給されます。また、遺族補償年金の対象となる遺族がいないときには、一定の範囲の遺族に遺族補償一時金が支給されます。
- 葬祭料:葬儀を行った方に対して、葬儀費用として一定額が支給されます。
会社に対する損害賠償請求
死亡事故の場合、ご遺族は会社に対して以下の損害賠償を請求することができます。
- 死亡慰謝料:被災者本人の慰謝料とご遺族固有の慰謝料を合わせて、弁護士基準では一家の支柱の場合で2,800万円程度が相場です。
- 逸失利益:被災者が生きていれば将来得られたはずの収入から、生活費を控除した金額が請求できます。
- 葬儀費用:実際に支出した葬儀費用のうち、相当な範囲の金額が請求できます。
死亡事故の場合、賠償額は数千万円から億単位になることも少なくありません。
弁護士に依頼するメリット

労災に遭ってしまった場合、なぜ弁護士が必要なのでしょうか。それは、上でご説明したように、慰謝料は労災からは支給されませんし、後遺障害を負った場合の逸失利益の補償も不十分であるからです。
また、労災が認められたとしても、さらに請求をするためには、自分が所属する会社を相手に損害賠償請求を行う必要があります。
ただ、この損害賠償請求は、会社に過失(安全配慮義務違反)がなければ認められません。
会社に過失が認められるかどうかは、労災発生時の状況や会社の指導体制などの多くの要素を考慮して判断する必要がありますので、一般の方にとっては難しいことが現実です。
弁護士にご相談いただければ、過失の見込みについてもある程度の判断はできますし、ご依頼いただければそれなりの金額の支払いを受けることもできます。
また、一般的に、後遺障害は認定されにくいものですが、弁護士にご依頼いただければ、後遺障害認定に向けたアドバイス(通院の仕方や後遺障害診断書の作り方など)を差し上げることもできます。
さらに、会社側は往々にして「労働者にも過失があった」と主張し、責任を否定してきます。適切な反論をするためには、法的知識と交渉経験が不可欠です。
そのため、労災でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。労働災害については、そもそも労災の申請を漏れなく行うことや、場合によっては会社と裁判をする必要もあります。
労災にあってしまった場合、きちんともれなく対応を行うことで初めて適切な補償を受けることができますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。
当事務所のサポート
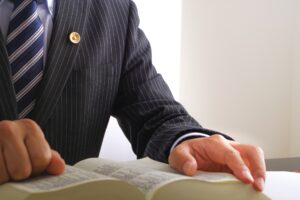
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。労災分野では労災事故と後遺障害に集中特化した弁護士チームが、ご相談から解決まで一貫してサポートいたします。
- 初回相談無料:まずはお気軽にご状況をお聞かせください。
- 後遺障害労災申請のサポート:複雑な手続きもお任せいただけます。
- 全国対応・LINE相談も可能:お住まいの場所を問わずご相談いただけます。
労災事故で心身ともに大きな傷を負い、将来への不安を抱えていらっしゃるなら、決して一人で悩まないでください。お気軽にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






