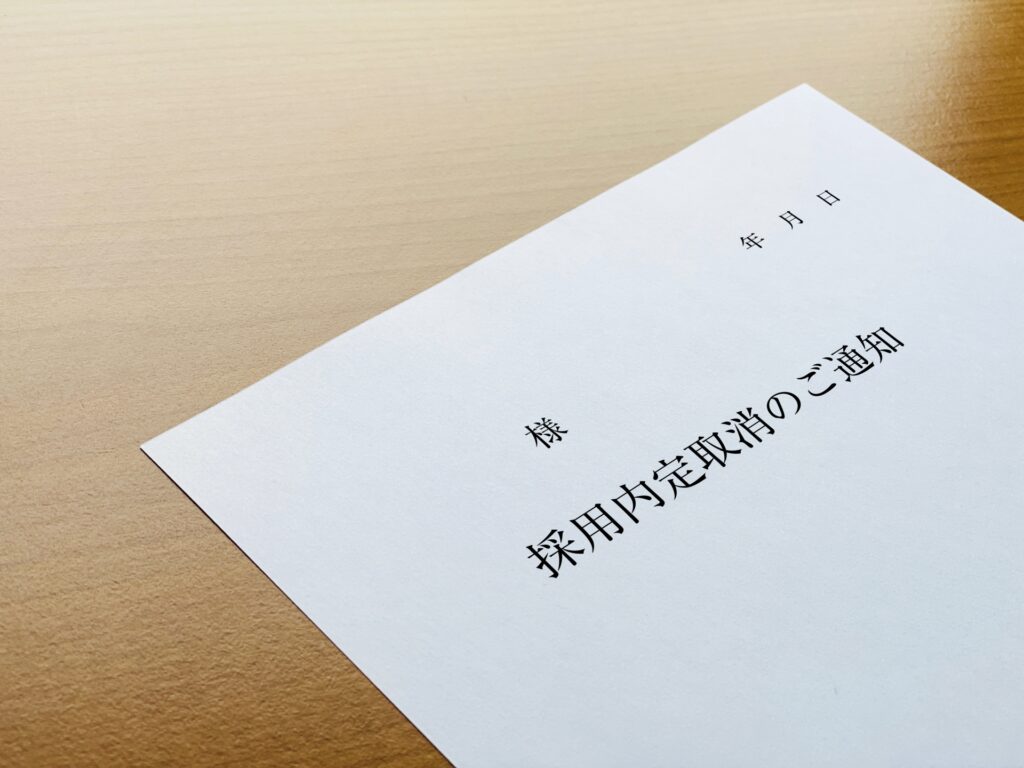
「内定をもらったが、内定取り消しをすると会社から伝えられた」「内定を取り消されてしまうらしいが、どうにかしたい」「内定とは何かよくわからない」このような場面に遭遇した方やそれらについて知りたい方に向けて、内定や内定取消し、これらに関する法律問題について解説します。
採用内定の一般的なイメージ

しばしば耳にする「(採用)内定」とは何でしょうか。
良くイメージするのは、就職活動をする人たちが、内定を得るために必死に努力をされている姿でしょうか。
しかし、内定を得ても、直ちに働き始めることはないでしょう。内定後しばらくの期間を経て、例えば、年度初めの春から働き始めるという方も多いでしょう。
実は、「(採用)内定」は、法律にどのようなものであるかと定義されているものではありません。では、どのようなものなのでしょうか。
法律上の採用内定

わかりやすさを重視していえば、採用内定通知は、会社が「春からうちで働いてください」とメッセージを伝えるものです。これが伝えられた後の状態を我々は、「(採用)内定」があると呼びます。
では、内定がある状態とは、法律上どのようなものなのでしょうか。
大学生4年生だった学生が会社から採用内定通知を受け取ったが、その後採用内定を取り消してしまった、という事件がよく紹介されます(最高裁昭和54年7月20日)。
この事件では、「内定を受けた時点で会社と原告である大学生の間には労働契約が成立していたのだろうか」ということが問題になりました。
この判決において、判例は、「採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難」であると述べつつ、この事件においては、採用内定通知を受け取った人と会社には労働契約が成立するとの考え方を示しました。
ただし、ここにいう労働契約は、(原告の大学生が)大学を卒業したときから就労が開始する契約であり、また、一定の事由がある場合には解約ができることが留保された契約である、との考え方を示しました。
この事件からすれば、多くの場合、採用内定があれば会社と労働者の労働契約は成立したとみられるのが通常であるということが出来るのです。
一方で、採用内定後も就労開始までは、会社は一定の事由(例えば、労働者が犯罪を犯した場合などでしょう。)があると確認した場合に、比較的簡単に辞めさせられるのです。
ただし、裁判所ですら「一義的に論断することは困難」であるというのですから、事案ごとに本当に労働契約が成立したかは難しい判断が必要なこともあります。
採用内定を受けた後は何ができるのか

では、内定を受ける前と内定を受けた後ではどのように変わるのでしょうか。
内定を受けた後、就労開始までの間は、労働者は働く必要はありません。また、給料をもらうこともありません。これでは、労働契約が成立する前と変わらないようにも思えます。
しかし、会社は、内定を受け労働契約が成立した労働者をやめさせるためには、一定に厳しい要件を満たさなければなりません。このルールは、解雇権濫用法理(解雇が認められるか否かについてはこちら)と呼ばれています。
解雇権濫用法理により、労働者は保護されています。単なる業務不適格などを理由とする場合、会社は、簡単に内定者を解雇することはできないと考えられています。
また、解雇のためには解雇予告通知や解雇予告手当等を支払う必要も生じます(解雇予告手当についてはこちら)。
このように、内定の有無は、法律上の保護の程度に関わるのです。
不当に内定を取り消された(解雇された)場合はどうなるのか

上に述べた通り、簡単には内定取消しや解雇は正当化することが出来ません。このような場合、なされた内定取消しや解雇は、「不当解雇」、すなわち本来法律上違法と評価される解雇ではないかという問題があります。
不当解雇を受けた労働者は、解雇をされてからも本来払われるべきだった賃金相当の金銭等を請求することが出来る場合があります(不当解雇の場合に請求できるバックペイについてはこちら)。
事案ごとの事情によりますが、内定を不当に取り消された方も、賃金相当額の金銭を請求できる場合があるのです。ただし、この金銭はあくまで、内定時に就労開始時期とされていた時期(例えば大学生は大学卒業の後)からの賃金相当額であるとされています。
まとめ

以上ご紹介したように、「(採用)内定」を受けた場合、その方と会社との間には労働契約が成立したと認められることが多いです。
しかし、その判断や不当解雇とみられるか否か、一定の金銭を請求できるか否かには法律上難しい問題が多く隠れています。このような状況に対処するためには、弁護士へ一度ご相談されることが推奨されます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






