
下水道設備の保守・点検・工事に携わる方々にとって、マンホール内での作業は日常業務の一部です。しかし、この作業には酸素欠乏、硫化水素中毒、墜落・転落といった重大な危険が潜んでいます。実際に、マンホール内作業で労働災害に遭われた方から多くの相談が寄せられており、中には生命に関わる深刻な事故も発生しています。
本コラムでは、マンホール作業中の労働災害について、労災認定から損害賠償請求まで、弁護士の立場から包括的に解説いたします。
マンホール作業中の労災事故とは?
マンホール関連作業で発生しやすい事故の特徴
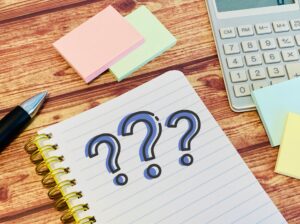
マンホール作業に伴う労働災害には、以下のような特徴的なパターンがあります。
1. 酸素欠乏・硫化水素中毒 マンホール内は密閉空間のため、酸素濃度の低下や硫化水素の充満により、作業者が意識を失って倒れる事故が多発しています。特に下水道関連の作業では、有機物の分解により硫化水素が発生しやすく、短時間で重篤な中毒症状を引き起こします。
2. 墜落・転落事故 マンホールやタンク、その他狭い入口を持った場所での作業は、はしごの昇降を伴い、特にはしご昇降時に手足を滑らせてしまう墜落・転落・落下事故の危険性があります。深さのあるマンホールでは、転落による外傷が深刻な後遺障害につながることも珍しくありません。
3. 救助活動中の二次災害 一人が事故に遭った際、救助に向かった同僚も同様の事故に遭う「二次災害」も頻発しています。酸素欠乏や有毒ガス中毒の場合、適切な安全措置なしに救助に向かうことで、被害が拡大するケースが報告されています。
過去に起きた具体的な労災事例

下水道管等の補修工事において、元請けの現場代理人が補修前の状況の写真撮影中に硫化水素を吸入してマンホール内で意識を失い、その救助にあたった下請けの作業員2名も硫化水素中毒となった事例があります。
また、マンホール内で下水管にゴム板を取り付ける作業をしていた際、作業者1名が硫化水素中毒になった事例では、雨が一時止んだため独断で作業を開始したところ、マンホール内で強い硫化水素の臭いを感じて急いで地上に戻ろうとしましたが、気を失って中で倒れてしまいました。
埼玉県行田市で、下水道管の点検作業をしていた50代の作業員4人がマンホールの中で硫化水素の中毒や中毒にともなう窒息で死亡してしまった事例もあります。この事件では、警察によりますと、1人が下水道管に転落したあと助けようとした3人も次々に転落したとみられるということです。
発生原因と事業者側の安全配慮義務

マンホール事故の主な発生原因として、以下が挙げられます。
事業者側の安全配慮義務違反
- 事前の作業環境測定の未実施
- 適切な換気設備の未設置
- 酸素欠乏危険作業主任者の未選任
- 作業者への特別教育の未実施
- 安全帯・呼吸用保護具の未支給
- 見張り人の未配置
酸素欠乏危険場所で作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を選任し、作業指揮等決められた職務を行わせ、酸素欠乏危険場所において作業に従事する者には、酸素欠乏症、硫化水素中毒の予防に関すること等の特別教育を実施することが法的に義務付けられています。具体的には、
(1)作業に従事する労働者が、酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業方法を決定し、労働者を指揮すること。
(2)その日の作業を開始する前に、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があったときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。
(3)測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。
(4)空気呼吸器等の使用状況を監視すること。
これらの安全配慮義務に違反した結果、労働者が事故に遭った場合、会社側の法的責任が認められる可能性が大きくなります。
労災として認定される条件とは?

業務災害と通勤災害の違い
労災保険による補償を受けるためには、まず「業務災害」または「通勤災害」として認定される必要があります。労災保険は大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」に分類されます。
- 業務災害:仕事中や業務に関連する行為の最中に発生した事故
- 通勤災害:通勤途中に発生した事故
今回のケースである「マンホール作業中の転落事故」は、明らかに業務中の事故であるため、業務災害に該当します。
業務災害の認定要件
- 業務遂行性:労働契約に基づく業務を行っていたか
- 業務起因性:業務と災害との間に相当因果関係があるか
マンホール作業中の事故の場合、作業指示に従って業務を行っていた状況であれば、業務遂行性は比較的認められやすいといえます。問題となるのは業務起因性で、特に作業者の安全配慮義務違反や独断での作業開始が争点となることがあります。
例を想定してみましょう。
- 作業員がマンホール蓋を開け、内部に降りようとした際に足を滑らせて転落
- 暗闇で段差が分からず、転落
- 現場には十分な照明設備がなく、安全帯の使用も徹底されていなかった
このような状況であれば、労災認定は当然ながら、会社の安全配慮義務違反も強く疑われます。
労災認定に必要な証拠と申請の流れ

労災認定を受けるためには、以下の証拠を収集し、適切な申請を行う必要があります。
■必要な証拠・資料
・事故発生状況報告書: 会社が作成するもの、または被災者自身が詳細にまとめたもの(いつ、どこで、どのように事故が発生したか、当時の業務内容など)。
・目撃者の証言: 事故の状況や災害発生時の被災者の状態を具体的に説明できる人物(同僚、上司など)の証言書。氏名、連絡先、具体的な証言内容を記載します。
・現場の写真・図面・動画: 事故現場の状況、危険箇所の状態、災害発生時の状況を示すもの。
・作業指示書・作業手順書・安全教育記録: 災害発生時の作業内容と業務の関連性、会社の安全管理体制を示す資料。
・タイムカード・出勤簿・業務日報: 災害発生時の労働時間や業務内容、勤務状況を証明するもの。
・会社の就業規則・雇用契約書: 労働者としての雇用関係を証明し、給付額算定の基礎となる情報が含まれます。
・医師の診断書・カルテ・診療報酬明細書
・検査結果(レントゲン、MRI、血液検査など)
・作業環境測定結果・化学物質の安全データシート(SDS): 特定の化学物質へのばく露など、職業病を主張する場合に重要です。
・業務歴に関する書類: 長期間にわたる特定の業務による職業病の場合、過去の業務内容や期間を証明する資料。
■申請の基本的な流れ
1.会社への報告と協力依頼:
災害が発生したら、速やかに会社に報告し、必要な書類の作成や申請手続きへの協力を依頼します。会社は労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を提出します(条件により提出しないこともあります)。
2.労働基準監督署へ書類提出
負傷や疾病の種類に応じて、「療養補償給付請求書」、「休業補償給付請求書」、「障害補償給付請求書」など、必要な請求書に記入し、上記で収集した証拠書類を添付して、所轄の労働基準監督署に提出します。会社の証明も必要です。
3.労働基準監督署による調査:
提出された書類に基づき、労働基準監督署が事実関係の調査を行います。これには、会社への照会、被災者や目撃者への聞き取り、医療機関への確認などが含まれます。
4.業務災害(通勤災害)認定・不認定の決定:
調査結果に基づいて、災害が業務上のもの(業務災害)または通勤中のもの(通勤災害)であるかどうかが判断されます。認定された場合、療養補償給付の場合は、直接医療機関に支払われます。
加害者がいる場合の第三者行為災害
マンホール事故においても、第三者の行為が原因となるケースがあります。例えば、
- 他の工事業者の不適切な作業により有毒ガスが流入
- 設備の欠陥により事故が発生
このような場合、労災保険による給付とは別に、第三者に対する損害賠償請求も可能となります。
マンホール事故における損害賠償のポイント

会社の責任(安全配慮義務違反)
労働契約法第5条に基づき、使用者には労働者の生命・身体の安全を確保する義務があります。マンホール作業においては、特に以下の安全配慮義務が問題となります。
具体的な安全配慮義務
- 酸素欠乏症等防止規則に基づく安全措置
- 適切な作業環境の測定と管理
- 必要な保護具の支給と着用指導
- 緊急時の救助体制の整備
- 作業者への十分な安全教育
これらの義務に違反した結果、労働者が事故に遭った場合、会社側に民事上の損害賠償責任が発生します。
下請けや元請けとの関係
建設業、現場作業においては、元請け・下請けの複層構造が一般的です。マンホール工事でも同様で、責任の所在が複雑になることがあります。
元請会社は発注先である下請会社の従業員に対する安全配慮義務を負うことは原則としてありません。しかし、元請会社と下請会社の従業員との間にある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係が認められる場合には安全配慮義務が生じるとされています(最高裁昭和50年2月25日判決)。
特別な社会的接触とは、下請会社の従業員が元請会社の管理する設備や工具を使っていた、元請会社の指揮監督をうけて働いていた、作業内容が元請会社の従業員の作業内容と類似していたなどの事情により、元請会社と下請会社の従業員との間で実質的な使用関係あるいは、間接的指揮命令関係が認められることをいいます。
過失割合の判断と保険対応の違い
マンホール事故では、労働者側の過失も問題となることがあります。
労働者側の過失として考慮される要素
- 安全教育に反する行為
- 保護具の不着用
- 独断での危険作業の実施
- 安全確認の怠り
ただし、使用者側の安全配慮義務違反が重大な場合、労働者の過失が多少あっても、会社側の責任が大きく認定される傾向があります。
弁護士に相談するべき理由

弁護士が介入することで得られるメリット
マンホール事故のような複雑な労災事案では、弁護士の専門的な知識と経験が不可欠です。
1. 適正な後遺障害等級認定の獲得 酸素欠乏や硫化水素中毒による脳損傷、墜落による骨折・神経損傷など、マンホール事故では重篤な後遺障害が残ることがあります。適正な等級認定を受けるためには、医学的知識と法的知識の両方が必要です。
2. 会社の責任追及と損害賠償請求 安全配慮義務違反の立証には、労働安全衛生法等の専門知識が必要です。弁護士が介入することで、会社側の過失を効果的に立証し、適正な損害賠償を獲得できます。
3. 複数当事者との交渉・調整 元請け・下請けが関与する事案では、複数の保険会社や、会社、との交渉が必要になります。弁護士が代理人として一括して対応することで、被災者の負担を軽減できます。
示談交渉・損害賠償請求の具体的な進め方
示談交渉の進め方
示談交渉は、裁判をせずに当事者間で話し合い、損害賠償額や解決条件を決める方法です。労災保険ではカバーされない損害(慰謝料など)を会社に請求することになります。
- 対象となる損害:
- 精神的苦痛に対する慰謝料
- 労災給付で補いきれない逸失利益(将来得られるはずだった収入の減少)
- 将来の介護費用など
- 進め方:
- 証拠の収集: 労災申請で集めた証拠に加え、会社の安全配慮義務違反を示す証拠(危険な作業指示、安全対策の不備など)をさらに集めます。
- 損害額の計算: 弁護士に相談し、適切な慰謝料や逸失利益などの損害賠償額を算出してもらいます。
- 会社への交渉開始: 会社に対し、損害賠償の請求と示談交渉の申し入れを行います。
- 話し合い: 会社との間で、賠償額や支払い方法について話し合いを進めます。
- 示談書の作成: 合意に至った場合、トラブル防止のため、示談内容を明記した示談書を交わします。
労災申請だけでは足りないケースとは?
労災保険による補償は、発生した損害の満額ではなく、休業補償も約8割までであって、精神的苦痛を被ったとして生じうる慰謝料はありません。
そこで、労災保険で補いきれない部分を会社に請求することが考えられます。では、具体的に会社に対してどのような項目を、いくらくらい請求できるのでしょうか。
労災保険から治療費が支払われている場合は、基本的に会社に請求することはありません。しかし、労災が使えない自由診療を選択した場合の差額や、将来必要になる手術・治療費、通院のための交通費(特にタクシー代など)、車いすや義手・義足などの装具費などが対象となります。
労災保険の休業給付ではカバーされない、給料の残り約2割分や、事故がなければもらえたはずの賞与(ボーナス)の減額分なども請求できます。
また慰謝料も請求出来ます。慰謝料には、主に2つの種類があります。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
事故日から症状固定日までの間、入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する補償です。入院期間や通院期間が長くなるほど、金額は高くなります。 - 後遺障害慰謝料
症状固定後も、体に痛みや機能障害などの後遺障害が残ってしまったことによる、将来にわたる精神的苦痛に対する補償です。後遺障害の等級に応じて、金額の相場が決まっています。
具体的な後遺障害慰謝料の金額は、以下の表のとおりです。
| 等級 | 後遺障害慰謝料の金額 |
|---|---|
| 1級 | 2800万円 |
| 2級 | 2370万円 |
| 3級 | 1990万円 |
| 4級 | 1670万円 |
| 5級 | 1400万円 |
| 6級 | 1180万円 |
| 7級 | 1000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
逸失利益について
後遺障害によって労働能力が低下し、将来にわたって得られたはずの収入が減少してしまうことに対する補償です。後遺障害の等級、事故前の収入、年齢などによって計算され、賠償項目の中で最も高額になる可能性があります。
【逸失利益の計算シミュレーション】
- 前提条件:
- 事故時年齢:45歳事故前の年収:500万円
- 後遺障害等級:第9級(労働能力喪失率 35%)
- 計算式:
年収500万円 × 労働能力喪失率35% × 労働能力喪失期間(67歳までの22年)に対応するライプニッツ係数14.029 - 逸失利益:約2,455万円
このケースでは、逸失利益(約2,455万円)と後遺障害慰謝料(690万円)だけでも、合計3,000万円を超える請求が可能になります。労災保険からは、9級の場合、一時金として給付基礎日額の391日分(年収500万円なら約535万円)しか支給されません。その差がいかに大きいか、お分かりいただけると思います。
弁護士相談から解決までの流れ

初回相談で確認すべきポイント
初回相談では、以下の点について詳細に確認いたします。
1. 事故状況の詳細
- 事故発生日時・場所
- 作業内容と指示系統
- 安全対策の実施状況
- 事故の具体的経過
2. 治療状況と後遺症
- 診断名と治療内容
- 入院期間と通院状況
- 現在の症状と日常生活への影響
- 今後の治療予定
3. 会社側の対応
- 労災申請の状況
- 会社からの謝罪や補償の申出
- 保険会社の対応
4. 証拠の保全状況
- 現場写真の有無
- 診断書・治療記録の整備
- 目撃者の存在
費用の目安と着手金・成功報酬の仕組み

損害賠償請求サポート(事故による身体のお怪我など)
着手金 【無料】
成功報酬
示談で解決の場合:経済的利益の18%+税
訴訟で解決の場合:経済的利益の22%+税
※国家賠償等は応相談
その他費用
- 医師面談・意見書作成費用
- 鑑定費用(必要に応じて)
- 交通費・通信費等の実費
詳しくは、こちらをご覧ください。
労災認定・民事請求のスケジュール感

労災認定まで
- 申請から認定まで:1~2ヶ月程度
- 後遺障害等級認定:症状固定後2~4ヶ月
民事請求
- 示談交渉:2ヶ月~1年
- 調停・訴訟:1年程度
- 複雑事案:2年以上
早期の対応により、証拠保全や適切な治療につなげることができますので、労災事故後はできるだけ早期にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所サポート内容

グリーンリーフ法律事務所では、マンホール事故を含む労災事案について、後遺障害等級認定サポートや会社への損害賠償請求サポートを行っております。
上でご説明したように、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、労災からは支給されません。
労災が認められたとしても、されに請求をするためには、自分が所属する会社を相手に損害賠償請求を行う必要があります。
ただ、この損害賠償請求は、会社に過失(安全配慮義務違反)がなければ認められません。
会社に過失が認められるかどうかは、労災発生時の状況や会社の指導体制などの多くの要素を考慮して判断する必要がありますので、一般の方にとっては難しいことが現実です。
弁護士にご相談いただければ、過失の見込みについてもある程度の判断はできますし、ご依頼いただければそれなりの金額の支払いを受けることもできます。
また、一般的に、後遺障害は認定されにくいものですが、弁護士にご依頼いただければ、後遺障害認定に向けたアドバイス(通院の仕方や後遺障害診断書の作り方など)を差し上げることもできます。
そのため、労災でお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
労働災害については、そもそも労災の申請を漏れなく行うことや、場合によっては会社に対する請求も問題となります。
労災にあってしまった場合、きちんともれなく対応を行うことで初めて適切な補償を受けることができますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






