
ベルトコンベアは多くの産業で不可欠な機械ですが、その便利さの陰には深刻な労働災害のリスクが潜んでいます。特に巻き込まれ事故は、重篤な結果を招く可能性があります。
もしベルトコンベアでの労災に遭われたら、適切な補償を受け、再スタートを切るために、法的な知識と弁護士のサポートが不可欠です。
この記事では、ベルトコンベア労災の実態から、労災保険と会社への損害賠償請求について弁護士が詳しく解説します
そもそもベルトコンベアとは?

ベルトコンベアは、物流、製造、建設、農業など、さまざまな産業で大量の物を効率的に運搬するために不可欠な機械です。その基本的な構造は、エンドレスベルトがプーリー(滑車)によって駆動され、荷物を連続的に移動させる仕組みです。
ベルトコンベアは、その用途に応じて多種多様な形状と機能を持ちます。例えば、工場内で製品の組み立てラインを移動させる小型のものから、鉱山で大量の土砂を運搬する巨大なもの、さらには空港で手荷物を運ぶための複雑なシステムまで存在します。
素材も、ゴム、PVC、金属メッシュなど、運搬する物の種類や環境によって使い分けられます。
このように、ベルトコンベアは私たちの日常生活や産業活動において、目に見えないところで重要な役割を担っています。しかし、その利便性の裏側には、常に労働災害のリスクが潜んでいます。
ベルトコンベアで多発する事故類型

ベルトコンベアは非常に便利な機械ですが、その構造や動作特性から、特定の種類の労働災害が多発する傾向にあります。
ここでは、ベルトコンベアで特に注意すべき事故類型をいくつかご紹介します。
巻き込まれ事故
巻き込まれ事故は、ベルトコンベアで発生する労働災害の中でも最も深刻なものの一つです。作業服の袖や裾、手袋、髪の毛などが回転するプーリーやベルトとフレームの隙間などに挟まれ、そのまま身体が機械に引き込まれてしまう事故です。
多くの場合、コンベアの稼働中に清掃、点検、修理、または詰まった物の除去などを試みる際に発生します。
非常に高速で強力な力が働くため、一度巻き込まれると身体の広範囲に及ぶ重傷を負う可能性が高く、骨折、切断、圧挫症候群、さらには死亡事故に至るケースも少なくありません。
特に、停止措置を講じずに作業を行ったり、安全装置が適切に機能していなかったりする場合に、そのリスクは著しく高まります。
挟まれ・切断事故
挟まれ・切断事故は、ベルトコンベアの可動部分と固定部分の間に身体の一部が挟まれたり、切断されたりする事故です。これは、主に以下のような状況で発生します。
- ベルトとローラーの間への挟まれ: 荷物の整理や異常箇所の確認などの際に、手や足がベルトとローラーの間に引き込まれてしまうケースです。
- コンベアの昇降部や旋回部での挟まれ: 可動式のコンベアや複数のコンベアが連結されている場所で、不意の動作により身体が挟まれることがあります。
- コンベア上の荷物による挟まれ: 運搬中の荷物が崩れたり、落下したりすることで、作業者が挟まれることもあります。
これらの事故は、指や手の骨折、切断、重度の挫傷など、深刻な傷害を引き起こす可能性があります。特に、清掃時やメンテナンス時に、安易に可動部に手を伸ばしたり、身体を近づけたりすることで発生しやすい傾向があります。
転倒・落下事故
ベルトコンベア周辺での作業は、平坦な場所での作業とは異なる危険性を伴います。
- コンベア上での転倒: ベルトコンベア上で作業を行うことは原則として禁止されていますが、やむを得ず荷物の修正などでコンベア上に乗ってしまった場合に、バランスを崩して転倒する事故です。
- コンベアからの転落: 高所に設置されたベルトコンベアの周囲で作業中に、足を踏み外して転落する事故です。特に、点検通路が狭い、手すりが設置されていない、あるいは床面が滑りやすいといった状況でリスクが高まります。
- 荷物の落下による転倒: 運搬中の荷物がベルトコンベアから落下し、その衝撃や散乱物によって作業者がつまずき転倒する事故です。
これらの事故は、骨折、打撲、頭部外傷など、多様な傷害を引き起こす可能性があります。高所からの転落は、死亡事故に直結する危険性も伴います。
衝突事故
ベルトコンベアは、単独で稼働するだけでなく、他の機械や設備、あるいは他のベルトコンベアと連携して稼働することが一般的です。この連携の際に、衝突事故が発生することがあります。
- 他の機械との衝突: ベルトコンベアから排出された荷物が、次の工程の機械と衝突したり、あるいは別の搬送機械と衝突したりするケースです。
- 人との衝突: ベルトコンベア周辺を移動するフォークリフトや他の作業者との衝突です。特に、死角が多い場所や、騒音が大きく接近に気づきにくい環境で発生しやすいです。
- 荷物による衝突: ベルトコンベア上で荷物が滞留し、後続の荷物が衝突して崩れたり、あるいは飛散したりすることで、作業者に衝突する事故です。
衝突事故は、打撲、骨折、裂傷など、様々な傷害を引き起こす可能性があります。特に、フォークリフトなどの重機との衝突は、重篤な結果を招くことが多いです。
感電事故
ベルトコンベアは電動機によって駆動されるため、電気設備に関連する感電事故のリスクも存在します。
- 配線の損傷: 経年劣化や外部からの衝撃により配線が損傷し、露出した電線に触れて感電する事故です。
- 漏電: 絶縁不良などにより漏電が発生し、アースが不完全な状態で機械に触れて感電する事故です。
- メンテナンス時の不手際: 電源を切らずに電気部品の点検や修理を行い、誤って活線に触れて感電するケースです。
感電事故は、やけど、心室細動、呼吸停止など、命に関わる重篤な傷害を引き起こす可能性があります。特に、湿度の高い環境や、水を使用する場所での作業では、より一層の注意が必要です。
ベルトコンベアで発生する労働災害の現状

ベルトコンベアは多くの産業で不可欠な存在である一方で、労働災害のリスクも常に伴っています。
厚生労働省が公表している「労働災害発生状況」や、各産業別の労働災害統計を見ると、特定の機械による事故が上位を占めていることが分かります。
ベルトコンベアに特化した詳細な統計データは個別の機械名としては公表されていないことが多いですが、「挟まれ・巻き込まれ」事故や「転倒」事故といった大分類の中には、ベルトコンベアが関与する事故が相当数含まれていると推測されます。
特に製造業、物流業、建設業といった分野では、ベルトコンベアの使用頻度が高いため、これらの産業での事故報告が多くなる傾向にあります。事故の発生要因としては、不安全な作業方法、安全装置の不備・無効化、作業者の不注意、危険に対する認識不足などが挙げられます。
具体的には、以下のような傾向が見られます。
- 稼働中の清掃・点検: 多くの巻き込まれ事故が、ベルトコンベアが稼働している最中に、詰まりを除去したり、清掃を行ったりする際に発生しています。生産効率を優先するあまり、安易に機械を停止させないで作業を行うことが原因となるケースが多いです。
- 安全装置の軽視: 緊急停止ボタンが手の届かない場所に設置されていたり、ガードが取り外されていたり、インターロック機能が解除されていたりするなど、安全装置が適切に機能していない状況下での事故も散見されます。
- 教育・訓練の不足: 新人作業者や不慣れな作業者に対し、ベルトコンベアの危険性や安全な操作方法に関する十分な教育・訓練が行われていない場合、事故のリスクが高まります。
- 作業環境の不備: 照明が不十分な場所、床面が滑りやすい場所、狭い通路など、作業環境自体が不安全であることが事故発生の一因となることもあります。
- ヒューマンエラー: 長時間労働による疲労、集中力の低下、慣れによる油断など、作業者のヒューマンエラーも事故につながる重要な要因です。
これらの現状を踏まえ、企業には労働災害防止のための積極的な取り組みが求められています。具体的には、リスクアセスメントの実施、安全衛生教育の徹底、適切な安全装置の設置と維持管理、作業手順の標準化と遵守などが不可欠です。
巻き込まれのケガが起こるケース

ベルトコンベアによる労働災害の中でも特に深刻なものとして「巻き込まれ事故」が挙げられます。これは、ベルトコンベアの稼働部分に身体の一部が引き込まれることで発生し、非常に重篤な結果を招く可能性があります。ここでは、具体的にどのようなケースで巻き込まれのケガが起こりやすいのかを解説します。
ベルトコンベアの清掃・点検
ベルトの裏側やフレームとの隙間に溜まった粉塵や異物を取り除こうとして、手や工具が巻き込まれるケースです。特に、稼働を停止させずに「ちょっとだけ」と手を出してしまうことが多く、瞬時に巻き込まれてしまいます。
センサーの異常やベルトのズレなどを確認するために、稼働中のコンベアに不用意に近づき、衣服や身体の一部が可動部に触れて巻き込まれることがあります。
詰まりの解消作業
搬送中の物がベルトコンベアに詰まった際に、手や棒などで無理に押し込もうとしたり、引っ張り出そうとしたりして、その手が回転するプーリーやベルトの隙間に引き込まれるケースです。
詰まりを解消する際は、必ずコンベアを停止させ、ロックアウト・タグアウトなどの措置を講じることが不可欠です。
点検窓からの覗き込み
機械の内部状況を確認するため、点検窓や点検口から顔や身体を近づけすぎた際に、稼働中の部品に触れて巻き込まれることがあります。特に、慣れてくると危険に対する意識が薄れがちです。
不適切な服装・装飾品
だぶついた作業服や手袋
袖がだぶついた作業服や大きすぎる手袋が、回転するローラーやベルト、または駆動部分に引っかかり、そのまま身体が巻き込まれるケースです。
特に、手袋は巻き込まれやすいアイテムの一つであり、使用を推奨しない場合や、巻き込まれにくいタイプの手袋を選ぶべきです。
長髪や装飾品(ネックレス、ブレスレットなど)
髪の毛が長い場合、結んでいないとベルトコンベアの可動部に触れて巻き込まれる危険性があります。
また、ネックレスやブレスレットなどの装飾品も、機械に引っかかって身体が巻き込まれたり、締め付けられたりする原因となります。
安全装置の不備・無効化
ガードの取り外し・破損
点検や清掃の利便性から、本来設置されているべきガード(覆い)が取り外されたままになっていたり、破損していたりするケースです。ガードは可動部への不用意な接触を防ぐための最も基本的な安全装置です。
緊急停止装置の不備・操作手順の不徹底
緊急停止ボタンが作動しない、手が届かない場所に設置されている、あるいは作業者が緊急停止装置の存在を知らない、あるいは操作方法を理解していない場合、事故発生時に瞬時に機械を停止させることができず、巻き込まれが進行してしまう危険性があります。
インターロック機能の無効化
点検扉が開いているにもかかわらず機械が稼働してしまう、といったインターロック機能が適切に作動しない状態になっている場合も、巻き込まれ事故のリスクが著しく高まります。
作業手順の不徹底・教育不足
作業手順書の未整備・未遵守
ベルトコンベアの操作やメンテナンスに関する安全な作業手順書が作成されていない、あるいは作成されていても作業者がそれを遵守していない場合に、危険な行動をとってしまうことがあります。
特に、ルーティン作業の中で慣れが生じ、手順を省略してしまうことで事故につながるケースが多いです。
安全教育・訓練の不足
作業者に対し、ベルトコンベアの危険性、安全な操作方法、緊急時の対応、適切な服装などに関する十分な安全教育や訓練が行われていない場合、危険を認識できないまま作業を行い、巻き込まれ事故を引き起こすことがあります。
ヒューマンエラー
疲労や集中力の低下
長時間労働や睡眠不足などにより、作業者の疲労が蓄積し、集中力が低下している状況では、不注意による事故が発生しやすくなります。
慣れによる油断
日常的にベルトコンベアを使用している作業者は、危険に対する感覚が麻痺し、油断が生じやすくなります。「いつもやっているから大丈夫」という思い込みが、重大な事故につながることがあります。
リスクアセスメントの不徹底
事業場において、ベルトコンベアに関するリスクアセスメントが適切に実施されていない場合、潜在的な危険性が認識されず、必要な安全対策が講じられないまま稼働が続けられることになります。
これらのケースは、単独で発生するだけでなく、複数の要因が複合的に絡み合って事故につながることが少なくありません。ベルトコンベアによる巻き込まれ事故を防止するためには、機械的安全対策と人的安全対策の両面からのアプローチが不可欠です。
労働安全衛生法・民法715条と使用者責任
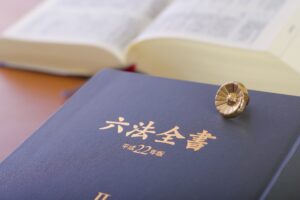
労働災害が発生した場合、被災した労働者は、労災保険からの給付を受けられるだけでなく、会社(使用者)に対して損害賠償請求を行うことができる場合があります。
この際の根拠となるのが、労働安全衛生法と民法715条(使用者責任)です。
労働安全衛生法
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律です。
この法律は、使用者に対し、労働災害を防止するために様々な義務を課しています。
主な使用者の義務としては、以下のようなものが挙げられます。
危険の防止措置義務(労働安全衛生法第20条~第25条の2)
機械、設備、有害物、作業方法などによる労働者の危険を防止するための措置を講じる義務です。具体的には、安全装置の設置、危険な機械の囲い、作業方法の改善、保護具の支給などが含まれます。
ベルトコンベアに関して言えば、稼働部のガード設置、緊急停止装置の設置、定期的な点検・整備、安全な作業手順の確立などがこれに該当します。
安全衛生教育の実施義務(労働安全衛生法第59条、第60条)
労働者に対し、機械の安全な操作方法、作業手順、危険有害性などに関する安全衛生教育を行う義務です。
特に、新しく機械を扱う作業者や、作業内容が変更された場合には、十分な教育訓練が必要です。
リスクアセスメントの実施努力義務(労働安全衛生法第28条の2)
危険性又は有害性を調査し、その結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講じるよう努める義務です。
これにより、潜在的な危険を事前に特定し、対策を講じることが求められます。
作業環境測定、健康診断の実施義務: 労働者の健康管理に関する義務も定められています。
これらの義務に会社が違反し、その違反が原因で労働災害が発生した場合、会社は安全配慮義務違反として損害賠償責任を負う可能性があります。
民法715条(使用者責任)
民法715条は、使用者責任について定めています。これは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者(従業員)がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う、というものです。
労働災害においては、通常、会社と被災した労働者の間に直接の契約関係があるため、民法715条が直接の根拠となることは多くありません。むしろ、会社が負う責任は、契約上の安全配慮義務違反(民法第415条)や、不法行為責任(民法第709条)として問われることが一般的です。
しかし、民法715条が間接的に関係してくるケースとして、以下のような状況が考えられます。
他の従業員の不注意による事故
例えば、他の従業員がベルトコンベアの操作を誤ったり、安全確認を怠ったりした結果、被災した労働者が巻き込まれ事故に遭った場合、その「他の従業員の不法行為」について、会社が使用者責任を負う、という構成が考えられます。この場合、会社は被災者に対して賠償責任を負うことになります。
下請け会社の従業員の事故
元請け会社が、下請け会社の従業員に対して、その業務の執行に関する指揮監督を行っていた場合などには、元請け会社がその下請け会社の従業員に対する使用者責任を負うと判断される可能性もあります。
より直接的には、会社が負う損害賠償責任は、以下のいずれかの根拠によることが多いです。
債務不履行責任(安全配慮義務違反)
会社は、労働契約に基づき、労働者が安全かつ健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」を負っています(労働契約法第5条)。この義務を怠った結果、労働災害が発生した場合、会社は債務不履行責任を負い、損害賠償義務が生じます。
不法行為責任(民法第709条)
会社が故意または過失によって、労働者の生命・身体を侵害した場合、不法行為責任を負い、損害賠償義務が生じます。
労災保険給付と会社への損害賠償を並行して請求する方法

労働災害に遭われた場合、被災した労働者(またはその遺族)は、国が運営する労災保険からの給付を受け取れるだけでなく、状況によっては会社に対して損害賠償を請求することも可能です。
この二つの請求は、それぞれ目的や根拠が異なるため、両方を並行して進めることが、被災者の権利を最大限に守る上で非常に重要です。
労災保険で受け取れる給付の種類
労災保険は、業務上または通勤途中の災害によって労働者が負傷、疾病、障害、死亡した場合に、労働者やその遺族に対して必要な保険給付を行う制度です。
会社側の過失の有無にかかわらず給付が行われるのが特徴です。労災保険から受け取れる主な給付には、以下のようなものがあります。
療養(補償)給付
労災病院や指定病院での治療費、薬剤費、入院費、通院交通費などが全額支給されます。
症状固定までの治療にかかる費用をカバーします。
休業(補償)給付
労災による負傷や疾病のために仕事を休まざるを得なくなり、賃金が受け取れない場合に支給されます。
休業4日目から、給付基礎日額の80%(休業特別支給金を含んだ金額です)が支給されます。
障害(補償)給付
症状が固定し、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
障害の程度に応じて、障害等級が1級から14級に認定され、一時金または年金として支給されます。
遺族(補償)給付
労働者が労災で死亡した場合に、その遺族に対して支給されます。
年金または一時金として支給され、葬祭料も別途支給されます。
傷病(補償)年金
療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治ゆせず、その傷病の程度が所定の傷病等級に該当する場合に支給される年金です。
介護(補償)給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給しており、現に介護を受けている場合に支給されます。
これらの給付は、労働基準監督署に必要書類を提出することで請求できます。
会社への損害賠償請求

労災保険は、あくまで最低限の補償を目的としたものであり、精神的苦痛に対する慰謝料や、事故がなければ得られたはずの賃金(逸失利益)の全額、将来の介護費用など、労災保険だけではカバーしきれない損害も多く存在します。
そこで、労働災害が会社の安全配慮義務違反や不法行為によって発生した場合、被災者は会社に対して、労災保険ではカバーされない部分の損害について、民事上の損害賠償を請求することができます。
会社に損害賠償を請求できる主な項目は以下の通りです。
- 治療費: 労災保険でカバーされない治療費や、保険外診療費など。
- 休業損害: 労災保険の休業(補償)給付では賃金の80%しか補償されないため、残りの20%(差額)や、給付基礎日額を超える部分の損害。
- 逸失利益: 後遺障害により労働能力が低下したり、死亡したりした場合に、将来得られたであろう収入の減少分。これは、労働能力喪失率、平均余命、基礎収入などを基に算定されます。
- 慰謝料:
- 入通院慰謝料: 労災による怪我や病気で、入通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛への慰謝料。
- 後遺障害慰謝料: 労災により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への慰謝料。後遺障害等級に応じて金額が変動します。
- 死亡慰謝料: 労働者が死亡した場合に、その労働者本人および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料。
- 付添費用: 入院中や自宅療養中に家族などが付き添った場合の費用。
- 将来の介護費用: 重度の後遺障害が残り、将来にわたって介護が必要となる場合の費用。
- 葬儀費用: 死亡事故の場合の葬儀費用。
- 物的損害: 事故により破損した衣服や持ち物などの損害。
並行して請求する方法

労災保険給付と会社への損害賠償請求は、それぞれ独立した手続きとして並行して進めることができます。
- まず労災保険給付を請求する:
- 労災事故が発生したら、まずは速やかに労働基準監督署に労災申請を行い、労災保険からの給付を受け取ります。これは、会社側の過失の有無にかかわらず、迅速な補償を受けられるためです。
- 労災保険の給付は、損害賠償額を算定する際に「既に受け取った損害賠償金」として扱われ、会社への損害賠償請求額から控除されることになります。これは、同一の損害について二重に補償を受けることを防ぐためです。
- 会社の責任を追及する:
- 労災保険の給付を受けながら、同時に会社の安全配慮義務違反や不法行為の有無について証拠を収集し、損害賠償請求の準備を進めます。
- 会社との交渉を通じて和解を目指すか、交渉がまとまらない場合は、訴訟を提起することになります。
弁護士に依頼するメリット

ベルトコンベアによる労働災害に遭われた際、弁護士に依頼することには多くのメリットがあります。特に、複雑な法的手続きや会社との交渉が必要となる場合、その重要性はさらに高まります。
適正な損害賠償額の算定
労災事故による損害賠償額は、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料など多岐にわたり、その算定には専門的な知識が必要です。特に、後遺障害の有無や程度に応じた逸失利益や慰謝料の算定は複雑であり、一般の方が正確に算出することは非常に困難です。
弁護士は、過去の裁判例や保険会社の基準、裁判所の基準(いわゆる「赤い本」の基準)などを踏まえ、被災された方が受け取るべき適正な損害賠償額を算定します。弁護士が算定する金額は、保険会社が提示する金額よりも高額になるケースが多く、ご自身で交渉するよりも大幅に増額できる可能性があります。
会社との交渉を有利に進める
労働災害の多くの場合、会社側との間で賠償額や責任の有無について交渉が必要となります。会社は、自社の責任を最小限に抑えようとすることが多く、被災者個人では交渉を有利に進めることが難しい場合があります。
弁護士は、法律に基づいた根拠を示しながら、会社に対して毅然とした態度で交渉を進めます。感情的になりやすい交渉の場面でも、冷静かつ論理的に主張を展開し、被災者の方の代理人として、最も有利な条件での和解を目指します。交渉が決裂した場合でも、訴訟提起を見据えた対応が可能です。
煩雑な手続きからの解放
労災保険の申請手続き、診断書や各種証明書の収集、会社とのやり取り、そして場合によっては訴訟の準備など、労働災害に関する手続きは非常に煩雑で時間と労力がかかります。怪我や精神的な苦痛を抱えながら、これらの手続きを全てご自身で行うのは大きな負担となります。
弁護士に依頼することで、これらの煩雑な手続きの大部分を任せることができます。書類作成から提出、関係機関との連絡、証拠の収集まで、専門知識を持つ弁護士が代行することで、被災者の方は治療や生活の再建に専念することができます。
証拠収集と立証活動のサポート
会社に対して損害賠償を請求するには、会社の安全配慮義務違反や、その違反と事故との因果関係を具体的に立証する必要があります。
そのためには、事故当時の状況を示す写真、会社の安全対策に関する資料、従業員の証言、専門家の意見など、様々な証拠を収集し、整理することが不可欠です。
弁護士は、どのような証拠が必要か、どのように収集すればよいか、そしてそれらの証拠をどのように用いて主張を組み立てるかを熟知しています。証拠収集のアドバイスや、自ら調査を行うことで、立証活動をサポートします。
精神的な負担の軽減
労働災害に遭うことは、肉体的な苦痛だけでなく、精神的にも大きな負担となります。今後の生活への不安、会社とのトラブル、複雑な手続きへのストレスなど、様々な悩みを抱えることになります。
弁護士に依頼することで、これらの精神的な負担を大きく軽減することができます。専門家が問題解決に向けて動いてくれるという安心感は、被災者の方が前向きに治療やリハビリに取り組む上で非常に重要です。
いつでも相談できる相手がいることで、孤独感を感じることなく、問題解決に向けて進むことができます。
適切な法的アドバイスの提供
労働災害に関する法制度は複雑であり、個々のケースによって適用される法律や判例が異なります。ご自身のケースでどのような権利があるのか、どのような選択肢があるのかを正確に判断することは難しいです。
弁護士が就任した場合、個別の状況に応じて、最も適切な法的アドバイスを提供します。
労災保険と損害賠償請求のバランス、今後の治療方針と示談交渉のタイミング、後遺障害申請のポイントなど、専門家の視点から、ご案内します。
交渉決裂時の訴訟対応
会社との交渉がまとまらない場合や、会社が全く責任を認めない場合には、訴訟を提起せざるを得ないこともあります。訴訟は、専門的な知識と高度な戦略を要する手続きであり、個人で対応することは非常に困難です。
弁護士は、訴訟手続きの全てを代行し、裁判所での主張立証活動、証拠提出、尋問など、あらゆる場面で被災者の方をサポートします。裁判官に対して、被災者の正当な権利を主張し、最善の判決を得るために尽力します。
当事務所のサポート内容

当事務所では、ベルトコンベアによる労働災害に遭われた方々に対し、以下のような総合的なサポートを提供し、被災された方々の権利を最大限に守り、適正な補償・賠償を獲得できるよう尽力いたします。
初回無料相談(60分)の実施
労働災害に遭われた直後は、心身ともに大きな負担を抱えていらっしゃるかと思います。当事務所では、まず被災された方のお話をじっくりと伺い、現在の状況や抱えているお悩み、ご希望などを正確に把握するため、初回無料相談を実施しております。この相談を通じて、どのような解決策が考えられるのか、弁護士に依頼することでどのようなメリットがあるのかを具体的にご説明いたします。
労災保険給付の申請サポート
労災保険からの給付は、被災後の生活を支える上で非常に重要です。
しかし、申請手続きは複雑であり、どのような給付が受けられるのか、どのような書類が必要なのかなど、分かりにくい点も少なくありません。
特に、後遺障害等級認定は、その後の損害賠償額に大きく影響するため、医学的知見も踏まえ、適正な等級が認定されるようきめ細やかなサポートを行うことが可能です。
会社への損害賠償請求交渉・訴訟対応
労災保険給付だけでは補いきれない損害については、会社に対する損害賠償請求が必要となります。当事務所では、被災された方の代理人として、会社との交渉から訴訟に至るまで、全面的にサポートいたします。
- 適正な損害賠償額の算定: 治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)、将来の介護費用など、様々な損害項目について、裁判所の基準に基づき、被災された方が受け取るべき適正な賠償額を算定します。
- 証拠収集と立証活動: 会社の安全配慮義務違反を立証するために必要な証拠(事故発生状況、会社の安全管理体制、従業員の証言、診断書、カルテなど)の収集をサポートし、法的観点から強力な主張を構築します。
- 会社との交渉代行: 会社やその代理人弁護士との間で、賠償額や過失割合、示談条件などについて交渉を代行いたします。被災された方が直接会社と交渉する精神的負担を軽減し、弁護士が前面に立つことで、冷静かつ有利な交渉を進めます。
- 訴訟提起・裁判対応: 交渉による解決が困難な場合や、会社が責任を認めない場合には、訴訟を提起し、裁判所を通じて適正な損害賠償を求めます。訴訟手続きの全てを弁護士が代行し、被災された方の権利を法廷で強く主張・立証いたします。
医療機関との連携
労働災害のケースでは、症状や後遺障害の程度を医学的に正確に把握することが、適正な賠償額の算定や後遺障害等級認定において非常に重要となります。当事務所では、必要に応じて、被災された方の主治医や専門医と連携し、適切な診断書や意見書の作成をサポートすることで、医学的根拠に基づいた主張を可能にします。
費用に関する明確な説明
弁護士費用についてご不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、ご依頼いただく前に、弁護士費用(着手金、報酬金、実費など)について、明確かつ丁寧にご説明いたします。ご不明な点がなくなるまで、ご納得いただけるよう努めますので、ご安心ください。
まとめ

ベルトコンベアによる労働災害は、被災された方にとって想像を絶する困難を伴うものです。
当事務所は、法律の専門家として、被災された方々が一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、全力でサポートさせていただきます。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






