
今回は、さいたま市大宮区で開設以来30年以上、様々な法律相談を取り扱ってきたグリーンリーフ法律事務所が、労働災害における安全配慮義務違反についてコメントします。
手指切断事故の起こりやすい業種と場面

製造業(金属加工・木材加工)
製造業の現場では、プレス加工機、旋盤・フライス盤・ボール盤などの回転機械、切断機、のこぎりなど、手指に直接接触する機械を使います。
これらの機械の操作ミスや故障などにより、手指が機械に挟まれる、圧力をかけられる、刃に当たるなどして、手指切断事故が発生します。
建設業
電動工具(グラインダー、チェーンソー、丸ノコ)
不注意による操作ミスや、刃の接触で切断。
型枠大工や鉄筋作業
重量物の落下や鋭利な部材での挟み込み。
運輸・倉庫業
フォークリフトや搬送機の荷物に手を挟まれる
トラックの荷台での固定作業中の誤操作
農業・林業
収穫機や草刈機などの巻き込み
作業中に手を突っ込んでしまい、即切断事故。
チェーンソー作業
特に林業では重大事故が多発。
食品加工業
肉や魚のスライサー・ミンチ機
手袋が巻き込まれたり、掃除中に電源を切り忘れたまま触れてしまう。
手指切断の場合の後遺障害
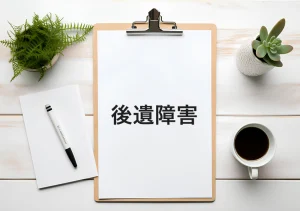
手の指を切断してしまった場合の後遺障害等級
| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
|---|---|
| 3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
| 6級8号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
| 7級6号 | 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指を失ったもの |
| 8級3号 | 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの |
| 9級12号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの |
| 11級8号 | 1手の人差し指,中指又は薬指を失ったもの |
| 12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
| 13級7号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
| 14級6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
後遺障害慰謝料

不幸にして後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料は、等級に応じ、交通事故における後遺障害等級に応じた慰謝料額を参照することが実務上行われています。
【後遺障害等級 慰謝料】
| 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 | |
| 2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 | |
| 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 | 等級無し |
| 830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
後遺障害等級認定とは

後遺障害の認定を受けるためには医師からの診断書が必須になります。しかし、医師の作成した診断書の記載内容によっては、本来であれば認定を受けることができた後遺障害も認定をうけることができないといったケースもあります。
後遺障害の認定に強い弁護士であれば、医師へのアドバイス等を行い、適切な後遺障害の認定を得られる可能性を高くすることができます。
ぜひ早期に後遺障害認定に精通した弁護士に相談をし、どのようにしたら後遺障害認定を受けることができるのか、アドバイスを受けてください。
会社に損害賠償請求する場合

労災給付は、労働者が仕事中に遭難した事故に対する一定の保障を提供しますが、必ずしも、その損害の全額が補填されるとは限りません。
また、事故が、企業や使用者の安全配慮義務違反によるものであった場合には、労災給付では補償されない損害が生じることがあります。
このように、企業や使用者に安全配慮義務違反が認められる場合、企業や使用者に対して民事訴訟を起こし、損害賠償を請求することが可能と考えられます。
裁判例・東京地方裁判所平成27年4月27日判決

勤務先工場内のプレス機械で作業中の原告が、左手をプレス部分に差し込んで左4指切断の負傷をしたという事故に遭ったもの。
原告は、平成24年8月4日付で症状固定と診断され、亀戸労働基準監督署長から同年11月15日,後遺障害等級8級の認定を受け、会社に賠償請求したという事案。
判決は、勤務先会社がプレス機に安全カバー、自動停止装置を取り付けなかった安全配慮義務違反を認め、
- 休業損害 242万0376円(原告主張額・同額)
- 後遺症逸失利益 2701万7003円(原告主張額・4638万0590円)
- 傷害慰謝料 179万円(原告主張額・同額)
- 後遺症慰謝料 830万円(原告主張額・同額)
を認めたうえで、原告の過失も4割認定し、1651万7514円と遅延損害金の支払いを命じました。
弁護士介入のメリット

①会社に対して代理人として交渉を行うことができる
弁護士は、社労士や司法書士と違い、被害者の代理人として交渉を行うことができます。
会社との交渉は在職中であっても退職された後であっても一般の方には負担が大きいと思いますし、法的な内容になると交渉の能力も必要になります。交渉の仕方によっては請求できる金額も変ってきます。
②労災申請のみならず、慰謝料を含めた損害の賠償請求まで可能
労基署に対する労災申請は最低限の補償でしかありません。これとは別に、逸失利益、慰謝料等の賠償請求が可能な場合があります。弁護士であれば、労働者の代理人として、労働審判、民事訴訟等の方法により使用者に対し損害賠償請求が可能です。
③労災保険の申請をサポート
労働災害事故によって、負傷してしまった場合、労災保険の給付が受けられます。
ところが、会社(事業主)が労災保険の申請を拒否することがあります。
しかし、会社の協力を得られなくても、労災保険の申請は可能です。
弁護士に相談・依頼することで、迅速な給付を受けることが可能となります。
④会社を訴えざるを得ない場合もあります。
不幸にして労災事故に遭ってしまい、労災からの給付だけでは損害の填補が不足する場合には、会社を訴えざるを得ない場合があります。
様々な検討点を経て賠償請求をしていくことになりますので、弁護士のサポートは必須と考えています。
賠償請求について、グリーンリーフ法律事務所ができること

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴
開設以来、数多くの労災を含む賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、労災専門チームも設置しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・労災専門チームの弁護士は、労災や賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、労災事件に関して、自信を持って対応できます。
なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。
最後に
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






