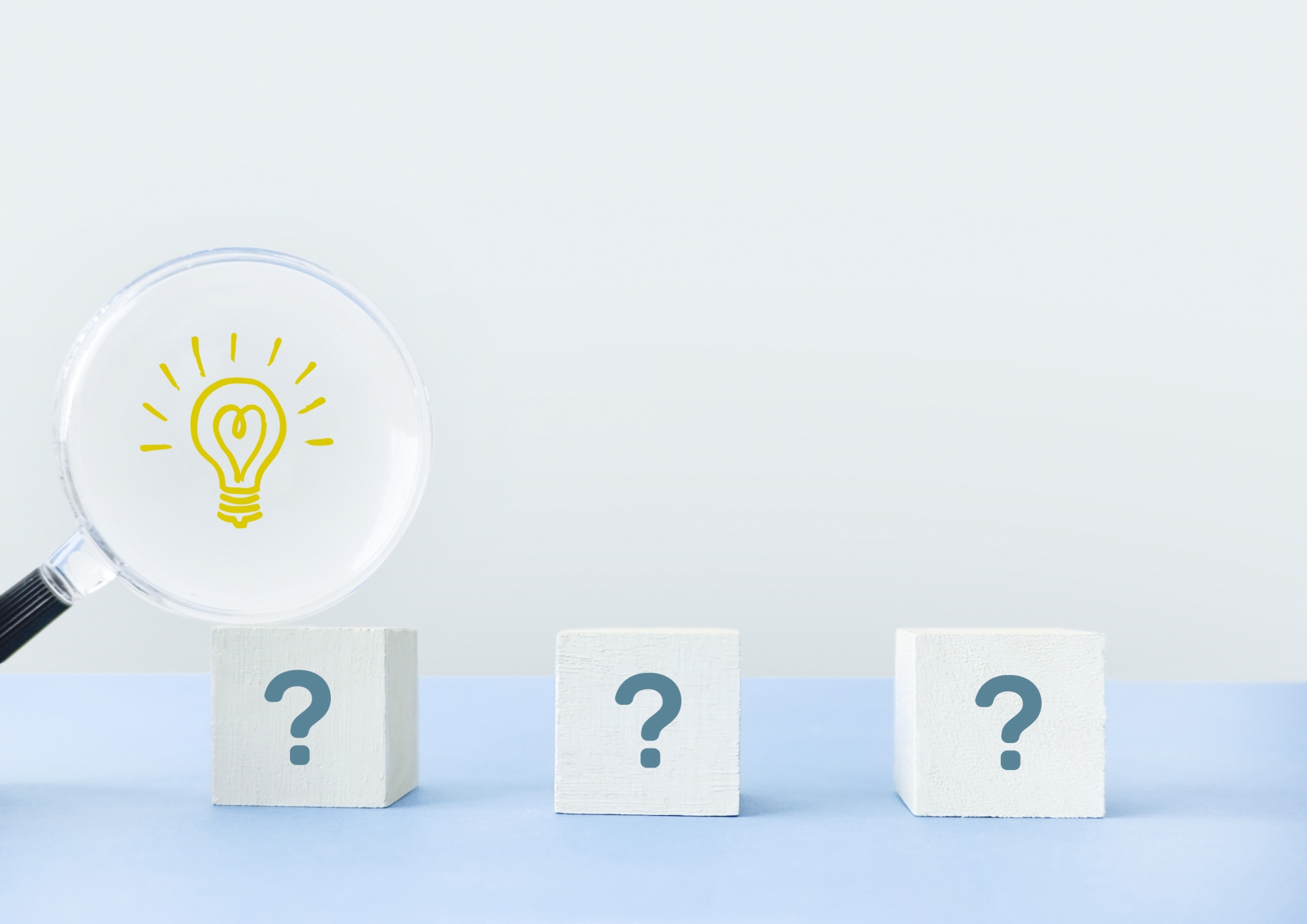
企業活動において、自社で開発・販売する商品が市場で成功を収めると、その成功に便乗しようとする模倣品や極めて類似した商品が出現することがあります。
これら類似品の流通は、会社の築き上げたブランドイメージ、信用、そして売上に直接的な損害を与えかねません。
このような類似品問題に対応するため、日本には知的財産法の枠組みが存在します。
商標権、意匠権、著作権などがその代表ですが、これらの権利を取得していない場合や、権利の保護範囲からわずかに逸脱した巧妙な模倣行為に対して、包括的に対応するための法律として不正競争防止法があります。
本コラムは、弁護士の視点から、会社の商品と類似する商品を発見した場合に、不正競争防止法に限定してどのような法的手段を取ることができるのか、その要件と具体的な手続きについて解説します。
特に、同法が保護対象とする「周知表示の混同惹起行為」と「商品形態の模倣行為」に焦点を当てて詳述します。
不正競争防止法が定める主要な規制行為

不正競争防止法は、公正な競争秩序を維持するために、特定の不正な競争行為を禁止しています。
会社商品の類似品問題に対処する際に特に重要となるのは、以下の二つの類型です。
1. 周知表示に対する混同惹起行為(不競法第2条第1項第1号)
これは、広く知られた(周知な)他人の商品や営業の表示と同一または類似の表示を使用し、需要者に混同を生じさせる行為を指します。
このような行為いえるためには以下の要件を充足している必要があります。
要件①:周知性(表示が広く知られていること)
会社の商品名、ロゴ、パッケージデザイン、あるいは店舗の外観など、商品の出所(誰の会社の商品か)を示す表示が、特定の地域または全国で、需要者の間に広く認識されている必要があります。
たとえば、「A社の〇〇」という商品を見た消費者が、その表示(名称やデザイン)から「これはA社の製品だ」と認識できる程度に知られていることが求められます。
周知性の立証には、販売期間、販売数量、広告宣伝の規模、市場でのシェアなどが証拠となります。
要件②:類似性(表示が似ていること)
相手方の使用している表示が、会社の周知表示と外観、称呼(読み方)、観念(イメージ)のいずれかにおいて類似している必要があります。
要件③:混同惹起(出所の混同を生じさせること)
類似した表示の使用によって、消費者が「相手方の類似品が会社の商品そのものである」と誤認したり、あるいは「会社と相手方の会社が、親子会社やフランチャイズなどの何らかの経済的・組織的な関係にある」と誤認したりするおそれがあることが必要です。
2. 商品形態の模倣行為(不競法第2条第1項第3号)
これは、他人の商品の形態(デザインや形状)を模倣した商品を譲渡・貸渡し等する行為を指します。意匠権などが未登録であっても、「デッドコピー」と呼ばれる露骨な模倣行為を規制するための規定です。
このような行為いえるためには以下の要件を充足している必要があります。
要件①:商品の形態
保護される「形態」とは、商品の外観であり、形状、模様、色彩、またはこれらの結合を指します。ただし、「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」は除外されます。
例えば、ペンの書きやすいグリップの形状が、単に機能を確保するためのものであれば保護対象外ですが、その形状がデザイン性を有し、他社との差別化に寄与している場合は保護対象となり得ます。
要件②:模倣(デッドコピー)であること
「模倣」とは、他人の商品の形態に依拠して、その本質的な特徴を同一に再現した商品を作成することを意味します。
つまり、相手方が会社の商品を見て真似したことが前提となります。
たまたま似てしまった場合は「模倣」にはあたりません。
模倣の認定は、全体的な印象から判断されます。細部の差異があっても、消費者が全体としてほぼ同一の商品と認識すれば模倣と判断されやすいです。
要件③:提供開始後3年以内であること(保護期間の制限)
この規定には時間的制限があります。
会社の商品が最初に日本国内で販売された日から3年を経過した後に模倣された商品については、この規定による保護を受けることができません(不競法第19条第1項第5号イ)。
法的手段:類似品・模倣品への具体的な対応策

先ほど解説した不正競争行為の要件を満たしている場合、会社は以下の法的救済措置を取ることができます。
1. 差止請求(不競法第3条)
不正競争行為によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある場合、その行為を停止または予防することを相手方に請求できます。
具体的な内容として、類似品の製造、譲渡、輸出入、展示などの行為の停止を求めます。
さらに、模倣品の廃棄や、製造設備・金型の除去など、侵害を予防するために必要な措置も同時に請求できます。
上記請求のやり方としては、 まずは内容証明郵便などで警告を行うのが一般的です。
警告にもかかわらず相手方が行為を止めない場合、裁判所に差止を求める仮処分または本訴訟を提起します。
2. 損害賠償請求(不競法第4条)
不正競争行為によって営業上の利益を侵害され、損害を被った場合、その損害の賠償を相手方に請求できます。
損害額の算定方法は、知的財産権侵害訴訟と同様に、損害額の立証は難しいことが多いため、不競法では損害額の算定を容易にするための特則が設けられています(不競法第5条)。
また、相手方がその不正競争行為によって得た利益の額を、会社の損害額と推定できます。
会社が販売することができた商品の数量(または会社が表示を使用できた数量)に、会社が本来得られたはずの利益の額を乗じた額を損害額とすることができます。
3. 信用回復措置請求(不競法第7条)
不正競争行為によって会社の営業上の信用が害された場合、信用を回復するために必要な措置を請求できます。
例えば、相手方による「謝罪広告」の掲載や、誤認を招いた表示を正すための「訂正広告」の掲載などが含まれます。
これは金銭的な賠償だけでなく、企業イメージの回復を図る上で重要な手段です。
訴訟手続きにおける留意事項と事前準備

法的手段を取るためには、不正競争行為の事実(類似品の存在、販売状況)と、先ほど解説しました述べた不正競争行為の要件(周知性、模倣の依拠性など)を立証するための証拠集めが不可欠です。
周知性を満たすか否かの証拠の確保は、会社商品の販売実績(契約書、伝票)、広告宣伝資料(新聞、雑誌、Web広告の出稿記録)、商品に対する報道記事などを時系列で整理する方法があります。
依拠性を満たすか否かの証拠の確保は、相手方が会社の製品を参照したことを示す証拠(内部資料など)を入手できれば強力ですが、通常は困難です。
この場合、両商品の形態の同一性・類似性の高さや、相手方が会社商品の発売後に自社製品を発売した事実などを間接事実として積み重ねて立証します。
まとめ

会社の商品と類似する商品への法的対応は、単に「似ている」という感情論ではなく、不正競争防止法の厳格な要件に照らして、客観的な証拠をもって立証していく作業です。
特に、周知性や模倣の依拠性の立証は高度な専門的判断を要します。
類似品問題に直面した際は、速やかに弁護士などの知的財産専門家に相談し、証拠保全から警告、差止請求、損害賠償請求に至るまで、迅速かつ戦略的な対応を取ることが、会社の営業上の利益を守るために不可欠です。
不正競争防止法を正しく理解し、これを強力な武器として活用することで、公正な市場競争の維持と会社商品のブランド価値の保護を図ることができます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。






