
今回は、遺産の中に非上場株式があり、相続人の一部が海外に居住している場合の遺産分割についてご相談を受けた事例を紹介します。株価の相場が存在しない非上場株式の評価方法や、海外に居住している相続人の協議書作成時の注意点など、参考にして下さい。
とある相続のご相談

Cさんは、半年ほど前に亡くなられたお父様の相続のことで、相談にいらっしゃいました。
相続人は、母のAさん、子2名(長女Bさん、長男Cさん)の合計3名です。
被相続人(お父様)の主な資産
①不動産(自宅兼事務所工場の土地・建物)
②預貯金 合計約5000万円
③車(普通乗用車1台、軽自動車1台)
④株式会社D金属の株式(非上場)300株
家族構成
妻A(70歳、株式会社D金属取締役)
長女B(49歳、大学講師)
長男C(47歳、株式会社D金属代表取締役)
お父様は、金属加工会社(株式会社D金属)の2代目社長として長く会社を経営してきましたが、数年前に重い病気が見つかったのを機に引退し、代表の座を長男のCさんに譲りました。
母(妻)のAさんは、会社の取締役の肩書ですが、実際は経理や事務などを担当します。
Cさんは、大学卒業後から実家の経営する株式会社D金属に入社し、20年以上に渡ってお父様を支えてきました。
一方、長女のBさんは、実家の会社経営にはノータッチの人生で、大学時代からアメリカに留学し、現在もアメリカ在住。あちらの大学で日本語講師として働いています。
お父様は、会社を経営していたこともあり、「生前にきちんと相続対策しなくちゃな」が口癖でしたが、病状が急変して亡くなったこともなり、残念ながら遺言書は残っていませんでした。
このため、相続人3名で遺産分割協議を行う必要がありました。
遺産分割を行うにあたっての問題① 非上場株式の評価

葬儀の際には急ぎ帰国した長女Bさんでしたが、ゆっくりしている時間はなく、仕事の都合で慌ただしくアメリカの自宅に戻っていきました。
49日も過ぎた頃、Cさんから、メールで「そろそろ遺産分割の協議をしたい」と申し入れ、遺産分割協議がスタートしました。
Cさんは、母Bさんと協力してお父様の遺産を洗い出し、一覧表にまとめてBさんにメールしました。また、それと同時に、
■不動産や車については、現実的に言って、日本国内にいる自分達(Bさん、Cさん)が取得する
■自社の株式についても、株式会社D金属の経営者である自分(Cさん)が取得する
■Bさんに対しては、相続分に相当する金銭を支払いたい
との希望を伝えました。
すると、Bさんからは「それにはもちろん反対しない」けれど、「具体的に、私はいくらもらえることになるのか計算して欲しい」との返事が来ました。
そこで、Cさんは、
■不動産については、建物の固定資産評価額+土地の路線価ベースの価格=「約4500万円」
■車については、無料査定を利用して、普通乗用車につき約300万円+軽自動車につき約50万円=「約350万円」
■株式会社D金属の株式300株=「0円」
と評価したうえで、これに預貯金の「約5000万円」を足すと、遺産総額は「約9850万円」になるから、Bさんの取り分は、
9850万円×4分の1=「2462万円」
になると提案しました。
しかし、この提案を受けたBさんから返ってきたのは、
「うちの会社の価値って本当に0円なの?」
「現に売上を上げて、あなた達はそこからお給料を取っているし、300株もあるんだから、さすがに0円ってことはないんじゃないの?」
というメールでした。
非上場株式の評価
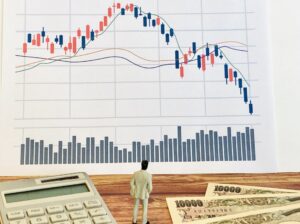
株式会社D金属の株式は、「非上場株式」です。
本件でのCさんは、自社の株式の価値について税理士の先生に聞いてみたところ、「そんなの、0円じゃないの」と言われたことから、「0円」としましたが、Bさんは納得しません。
上場株式の場合は、市場での株価がはっきりしていますから、株式の評価が問題になることはあまりありません。
これに対し、非上場株式は市場における相場がありませんので、遺産分割を行う前提として、これをどのように評価するかが問題となります。
非上場株式の代表的な評価方法には、次のようなものがあります。
純資産方式
1株当たりの純資産額により株価を算定する方法です。
貸借対照表に基づいた客観性のある評価が可能である一方、貸借対照表はあくまである時点での会社の財務状況を示すものに過ぎないため、そこに反映されていない収益力等の事情が考慮されないというデメリットもあります。
配当還元方式
将来期待される1株当たりの予測配当値を、一定の資本還元率(株主資本コスト)で還元することにより、元本である株式の現在価値を算定する方法です。
この方式には、税務上配当を行っていない会社の場合や、内部留保が膨らむばかりで配当金額が低廉に抑えられている会社の場合には、株価が低く算定されてしまうという問題点があります。
収益還元方式
将来期待される法人税課税後の1株当たりの純利益を一定の資本還元率(株主資本コスト)で還元することにより、元本である株式の現在価値を算定する方法です。
この方式には、算定の基礎となる課税後純利益の予想や資本還元率の決定がもともと困難であるうえに、どうしても評価者の恣意が入り込む余地があるため、評価額の妥当性をめぐって争いになりやすいという問題点があります。
DCF方式
将来の各事業年度のフリー・キャッシュ・フローを見積もり、各事業年度ごとに割り引いて算出した現在価値の合計を事業価値として求め、その事業価値に非事業資産の価値を加算して企業価値を求め、その企業価値から負債額を控除して株価を算定する方法です。
将来の収益獲得能力や会社独自の性質を反映させることができる点で、継続企業の株式評価に適していると言われています。
裁判実務での採用方式
上記のとおり、代表的な評価方法には、それぞれ一長一短があります。
このため、家庭裁判所における実務では、複数の評価方法を採用し、各算定結果に対して一定の折衷割合を乗じることで、加重平均を出すという、折衷方式が採られることが多いようです。
会社法上の株式買取請求の際の価格算定方法や税務上の評価基準なども参考にされます。
当事者間で非上場株式の評価について合意が整わない場合、裁判所が選任した鑑定人(公認会計士等の専門家です)による株価鑑定がなされることがあります。
本件での解決方法

株式会社D金属は、家族経営のいわゆる零細企業です。
Bさんの言うとおり、確かに売り上げを上げて、そこからいただく役員報酬でAさんとCさんは生活していますが、だからといって株式にそれほどの価値があるとは思えませんでした。
現に、その後行った税務申告では、株式会社D金属の株式は「0円」として評価されていました。
そこで、Cさんは、再度、税理士に相談して事情を説明し、相続税申告を行った際の株式の評価方法について質問しました。
税理士の回答は、
「株式会社D金属は税法上は『小会社』に当たり、原則として『純資産価額方式』によって評価すべきとされている。その『純資産価額方式』で計算すると、『0円』になる」
というものでした。
Cさんは、上記の回答を文章の形で自分にメールしてもらい、税理士の了解を得たうえで、そのメールをBさんに転送しました。
根拠付けがないと納得しないBさんも、税理士が書いたメールを読んでようやく納得し、「日本の税務署もそれで受け付けたのであれば、株式は『0円』ということでいいわ」と言ってくれました。
遺産分割を行うにあたっての問題② 長女Bの印鑑登録証明書

さて、遺産分割協議が整い、
■不動産はAさんが取得する
■預貯金と車、自社株300株は全てCさんが取得する
■Cさんは、Bさんに対して、代償金として2462万円を支払う
ことになりました。
なお、AさんとCさんの取り分は、価格に直すと法定相続分どおり(Aさんは2分の1、Cさんは4分の1)にはなっていませんが、AさんとCさんとの間でこの割合の取得で良いと円満に決めたことです。
さて、遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名・押印する段階になって、再びBさんとの関係で疑問点が生じました。
不動産の相続登記を行うためには、各相続人の実印が押印された遺産分割協議書と、各相続人の印鑑登録証明書が必要になります。
ところが、Bさんは長くアメリカに住んでいて日本国内に住民票登録がないため、この印鑑登録証明書を用意することができないのです。
そこで、印鑑登録証明書の代わりになるものとして、Bさんには、アメリカにある日本大使館で、サイン証明を取得してもらうことになりました。
このサイン証明は、申請者の署名と拇印が確かに領事の面前で行われたことを証明するものです。
遺産分割協議書の場合は、遺産分割協議書に相続人が領事の面前で署名をします。そして、日本大使館が発行する証明書と遺産分割協議書を合わせて綴って割印をします。
この手続きは、必ず署名する相続人本人が日本大使館に出向いて行わなければならず、郵送や代理ではできません。
Bさんも仕事の都合でなかなか大使館に行けず、時間がかかりましたが、最終的にはサイン証明を取得して遺産分割協議書を返送してくれました。
こうして、ご相談のあったCさんの遺産分割は、非上場株式の評価をどうするか、また海外在住の相続人の印鑑登録証明をどうするかという問題があったものの、それらを無事にクリアし、円満解決となりました。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






