
日本で外国籍の方が亡くなった場合、その方の相続は日本法で解決するのでしょうか。それとも本国法で解決するのでしょうか。この記事では、こういった「国際相続」問題の入り口として、準拠法の考え方を概説します。
日本で亡くなる外国人の人数

皆さんの周囲には外国籍の方はいらっしゃいますか?
地域住民、友達、家族、あるいはビジネス上のお付き合い…様々なかたちで、外国籍の方と関わり合う機会が増えています。
さて、日本に居住ないし滞在している外国籍の方の中には、本国に戻る前に、日本の地で亡くなってしまう人も一定数います。
e-Statという、日本の統計を公開している政府のポータルサイトがあるのですが、ここに載っている2023年の「人口動態調査 人口動態統計 確定数 別表」 によれば、1年間に9051人の外国人の方が日本でお亡くなりになったということです。
多いと見るのか、少ないと見るのかは難しいところですが、ひとつ言えることは、少なくとも9051件の相続が発生した、ということです。
外国人が被相続人である場合の相続の問題点

相続というと、日本に居住していた日本人(日本国籍の人)が、日本国内に預貯金や不動産を遺して亡くなり、その相続人も日本在住の日本人である…という状況がまず想定されますよね。
この場合には、日本の法律(民法等)に基づいて、遺産分割や相続登記等の相続手続が行われていくことになります。
では、亡くなった方が外国人(外国籍の方)だった場合はどうなるのでしょう?
・日本で亡くなったのだから、日本の法律が適用される
・日本に住んでいた人なら、日本の法律が適用される
・日本に住んでいたとしても、日本国籍が無いなら、本国の法律が適用される
・日本の法律と本国の法律が選べる
・日本にある財産や不動産には日本の法律が適用される
などなど、様々な答えが考えられますよね。
実は、あまり一般の方になじみのない法律で、「法の適用に関する通則法」というものがあります。
この法律は、ひとことで言うと、「準拠法を決めるための法律」になります。
「準拠法」って何??と思われた方も多いでしょう。
これは、何かの法的な効果を考えるときに、どの国の法律に基づいて考えるか、ということを指します。
準拠法が日本の法律なのであれば日本の法律に従って考え、準拠法がA国の法律であるのであればA国の法律に則って考える、ということですね。
上記の外国人が亡くなった場合についても、その相続について、準拠法を検討しなければなりません。
「法の適用に関する通則法」によれば…
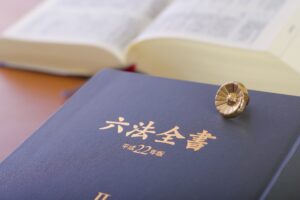
さて、相続に関する「法の適用に関する通則法」の定めは、第36条にあります。
法の適用に関する通則法第36条
https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078#Mp-Ch_3-Se_6-At_36
相続は、被相続人の本国法による。
かなりシンプルな条文です。
準拠法は「被相続人の本国法」によるということですから、アメリカ人が亡くなればアメリカの法律に(厳密には州法でしょうか)、韓国人が亡くなれば韓国の法律に従って、相続を考えていくということになりますね。
例え日本で亡くなったり、日本に遺産があったとしても、日本国籍ではなく外国籍である場合には、まずは「本国法」で考えるということになります。
しかし、ここで終わらないのが国際私法です。
結局、適用される法律は?

被相続人の本国法(すなわち日本以外の国の相続に関する法律)を見ると、実に様々な定めがされています。
この「様々な定め」については、大きい2つの観点があります。
1つ目は、動産と不動産を区別しているか、という点です。
日本の法律では、相続について動産と不動産は別々の規律を受けるのではなく、(具体的な手続きはさておき)同じ相続の規律を受けます。不動産の場合はこのように相続される、動産はこのように相続される、というような定め方はしていません。
これを「相続統一主義」といいます。
「被相続人」という「人」の単位に着目して、相続制度が設計されているということです。
しかし、諸外国の中には、人ではなく遺産である「物」の単位に注目して、相続の制度設計がされているということがあるのです。
これを、「相続分割主義」といいます。
この場合、動産と不動産とは別々の規律を受け、別々の帰趨を辿ることになる場合があります。
次に、2つ目として「反致」があるかという点があります。
反致というのは、日本の通則法に従って本国法を参照した結果、「日本法を適用せよ」という結論に落ち着くという状況のことです。
これはどういうことがというと、例えば、A国籍のXさんが日本で亡くなった場合、通則法では「相続は、被相続人の本国法による」とされていますから、Xさんが国籍を持つA国の法律を参照することになります。
そこでA国の法律を見てみると、同法では「相続は、亡くなった際の最後の住所地の法律を適用する。」と規定されています。
そうすると、Xさんは日本に住んでいて日本で亡くなりましたから、A国の法律に従えば日本法を適用することになります。
このように、本国法を参照した結果、日本法に戻ってくる(日本法の適用となる)のが「反致」という考え方です。
実際には、この1つ目と2つ目の考え方が合わせ技になっている国もあります。
すなわち、例えば上記の例で、A国法で「不動産はその財産の所在地の法律により相続される。動産はその者の本国の法律により相続される。」と規定されているパターンです。
もし、Xさんが日本に自宅の土地建物を所有していた場合、不動産である自宅の所在地は日本ですので、Xさんの自宅は日本法に則って相続の処理をされることになりますが、その他の動産類(現金・預貯金等)は、Xさんの本国であるA国の法律によって処理をされることになります。つまり、不動産だけが反致の状況になるということです。
このように、国籍・住所地・財産の所在地が一致しない国際相続の場合は、通則法により本国法を参照した結果として、結局どの法律が適用となるのかを見極めないといけないということになります。
理屈ではなく実務で決まるという場面もある

もうひとつ気を付けなくてはならない点は、手続・執行はその国の法律に基づかないと現実的にできない可能性があるという点です。
例えば、日本在住の日本人であるYさんが、B国に別荘(不動産)を所有していたとします。
Yさんが亡くなった場合、Yさんの相続は、Yさんの本国法である日本法によって処理されることになります。
しかしながら、B国の法律では「不動産の相続は、その所在地の方により相続される」とされていたとしましょう。別荘があるのはB国であるため、B国の法律に則った場合、B国法により相続されることになります。
こういった場合、日本法とB国法のいずれを適用するか、という点が理屈として解決されません。
しかしながら、遺産は、机上で相続してもあまり意味は無く(相続税的な意味はありますが…)、相続手続きを行って自分の手元に収めてようやく意味が出てくるものです。
そうだとすると、相続手続きが行えるか、執行が行えるか、という点がとても大事ということになりますよね。
上記事例の場合は、不動産の存するB国において相続手続きをすることになるので、B国法に則って相続手続を行った方がよりスムーズに事件を解決に導くことができると考えられるため、B国法で解決できないか検討していくことが多いと思われます。
まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は、被相続人が外国人(日本以外の国籍の方)だった場合を念頭に、いわゆる「国際相続」と呼ばれる分野の入り口として、準拠法の考え方を紹介しました。
入り口としたのは、準拠法が決まったあとは、今度は本国法の理解や解釈が必要になり、その後さらに手続の面で実務上の問題が生じたり等、やはり一筋縄ではいかないことが多いと思われるからです。
相続は、感情的な対立なども起こりやすく、そもそも解決までに時間がかかることが多い分野ですが、国際相続の場合はさらに時間がかかる可能性があります。
こういった難問に行き当たってしまった場合には、一度専門家へのご相談をおすすめいたします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






