
新しい人材を採用する場合、ミスマッチを避けるため、採用した人材が会社で活躍することができるか否かの判断期間を置きたいと考えることは自然な発想です。
そのような会社側のニーズに応えるため法的には試用期間という概念がありますが、同様の効果を狙って有期雇用契約を用いる場合もあります。
今回は、試用期間と有期雇用契約の関係性について解説をしておきます。
試用期間とは?

試用期間は、会社が新たに採用した従業員について、その能力や適性等を見極めるため、労働契約成立後の一定期間を区切って設定するもので、当該期間内に適性等がないと判断される従業員については本採用を拒否し得るという制度のことをいいます。
試用期間が設定された雇用契約の法的性質について、裁判所は、会社に解約権が留保された雇用契約であるとしています。
これは、試用期間中であっても従業員との雇用契約は成立しているため、会社が解約権を行使することは法的には解雇ということになるが、試用期間を設定した趣旨から、通常の解雇の場合よりも広い範囲で解雇の有効性が認められる可能性があるという趣旨で理解されています。
会社として気を付けるべきは、本採用拒否について通常の解雇よりも広い範囲で解雇の有効性が認められるといっても、前提となる判断基準はあくまで解雇の判断基準であり、なんとなく会社のカラーにあわないといった簡単な理由では本採用拒否をすることはできないという点です。
なお、試用期間は通常3~6か月程度の期間で設定されますが、場合によっては延長することも想定されています。
有期雇用契約とは?
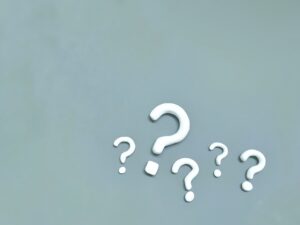
有期雇用契約は、文字どおり、雇用契約に定められた期間に限って従業員を雇用するというものであり、当該期間が経過すれば当然に雇用契約は終了します。
採用後の従業員の適性等を判断するために試用期間を設定するのではなく、同様の期間を雇用期間とする有期雇用契約を利用することができれば、解雇の問題に直面することなく従業員の適性等を判断できることになりますが、それは可能でしょうか?
この点、最高裁は、期間1年の期限付きの常勤講師が期間満了後に更新されなかったという事案について、使用者が新規採用にあたり、労働者の適性を評価・判断するために期間を設定した場合にはその期間満了により雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意があるなどの特段の事情がある場合を除き、設定された期間は試用期間と解することが相当であると判断しています。
この判断に従えば、試用期間と同様の目的を設定した有期雇用契約については試用期間と同視され解雇規制が適用されるように思われますが、有期雇用契約の利用目的が限定されていないこと等から裁判所の判断を一般化すべきではないという見解もあり、また、別の裁判例では、裁判所が試用期間目的の有期雇用契約について有期雇用契約として処理することが相当であると判断したものもあり、必ずしも統一的な結論があるというものではありません。
そのため、試用期間を設定することと同様の効果を狙った有期雇用契約の締結は法的にあり得ないわけではないという結論になります。
有期雇用契約を締結する場合の注意点

試用期間と同様の趣旨で有期雇用契約を利用する場合において、当該契約を有期雇用契約として認めてもらうためには、有期雇用契約の法的性質は維持しておく必要があります。
この点に関しては、3年間の勤務成績を考慮して期間の定めのない職種に異動することがあるとの定めがある中で3年間を限度とする期間1年の有期雇用契約終了後に更新がされなかったという事案についての裁判所の判断が参考になります。
当該事案について、裁判所は、私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約は、当該労働契約において3年の更新限度期間の満了時に労働契約を期間の定めのないものとすることができるのはこれを希望する教員の勤務成績を考慮して当該大学を運営する学校法人が必要であると認めた場合である旨が明確に定められており、当該教員もこのことを十分に認識した上で当該労働契約を締結したものとみることができること、大学の教員の雇用については一般に流動性のあることが想定されていること、当該学校法人が運営する三つの大学において、3年の更新限度期間の満了後に労働契約が期間の定めのないものとならなかった教員も複数に上っていたことなど判示の事情の下においては、当該労働契約に係る上記3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえない、と判断しています。
そのため、試用期間と同様の趣旨で有期雇用契約を利用する場合には、①有期雇用契約の形式は取るがこれはあくまで試用期間であり期間終了後に正社員として採用することが予定されているという採用面接時等における発言、②実際に期間満了で雇用契約が終了した人物はいないという会社内の実績、③有期雇用期間終了後も新たな雇用契約書等のやりとりがないという形式等についてはいずれも好ましくない(=実質的な試用期間と判断される可能性がある)ということになりますので、そのような実情がないかの確認をしておく必要があります。
まとめ

今回は、試用期間と有期雇用契約の関係性について解説をしてきました。
試用期間の趣旨を維持したまま解雇規制を免れようとする場合にはやはり相当程度のハードルがあると言わざるを得ず、前提となる就業規則や雇用契約書等の整備が必須となります。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。






