
仕事中の事故や通勤途中の事故で、足を骨折してしまうケースは少なくありません。もし、労災が原因で足を骨折した場合、労災保険による補償を受けることができる可能性があります。労働災害により足や脚を骨折するケースは、特に建設業、製造業、運輸業などの現場において頻繁に発生します。高所からの墜落事故、重量物の落下、あるいはフォークリフトやクレーンの巻き込みといった事故により、下肢に深刻なダメージを負うことが多く見られます。
こうしたケガは、治療に長期間を要するだけでなく、回復後にも関節の可動域制限や慢性的な神経症状など、後遺障害が残る可能性が高いという特徴があります。
さらに、職種によっては足の機能障害が労働能力に直結するため、復職が難しくなる、あるいは退職を余儀なくされるといった深刻な影響も無視できません。
本コラムでは、労災保険による補償とともに、使用者(会社)への損害賠償請求も視野に入れた法的な対応について、弁護士の立場から詳しく解説いたします。
労災で足・脚を骨折するケースとは?

労災における足や脚の骨折は、日常的な業務の中で突発的に生じるケースがほとんどです。以下のような場面での事故が代表例です。
- 高所作業中の墜落により、大腿骨や脛骨・腓骨を粉砕骨折
- 重量物の落下や転倒によって、足背部や足指を骨折
- 工場内でフォークリフトに巻き込まれて下腿部が開放骨折
労災保険の給付を受けるには、労働基準監督署による「業務災害認定」が必要です。ここでは、「業務遂行性(就業中であったか)」「業務起因性(作業内容とケガの因果関係があるか)」が審査されます。
労災における後遺障害とは?
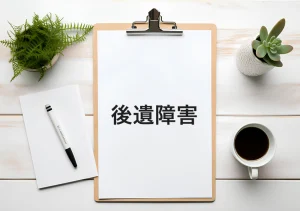
労災においては、後遺障害が問題となることが少なくありません。
後遺障害とは、治療による改善が見込めず将来的に一定の症状が残存する状態をいいます。
通常、これ以上治療しても症状が改善しないと判断されることを、「症状固定」と言います。医師が診断書にそれを書いて決めます。
後遺障害には重い方から順に、1級~14級の等級があります。
これらが認定されると、それぞれに応じた給付がなされることになります。
骨折自体は時間をかけて癒合することが多いものの、治癒してもなお残る可動域制限、痛み、しびれ、変形などがある場合には、「後遺障害」として等級認定の対象になります。労災保険では1級から14級までの障害等級が定められており、下記のような症状が該当します。
(1)関節の機能障害
関節(股関節・膝関節・足関節)が硬直したり、動きが制限された場合、以下の等級が想定されます。
8級7号:足関節がほとんど用をなさない(いわゆる「用廃」状態)
10級11号:可動域が健常側の2分の1以下
(2)骨の変形障害
長管骨(大腿骨・脛骨・腓骨など)に偽関節が形成されたり、明らかな変形が生じた場合、12級8号に該当する可能性があります。
(3)神経障害・慢性疼痛
骨折部位の神経が損傷し、しびれや灼熱感といった慢性的な疼痛が他覚的に認められる場合には、12級13号が適用されることがあります。
(4)足指の切断・短縮
作業機械に巻き込まれて足指を失った場合は、13級10号などが適用され、等級認定の対象になります。
※具体的な等級と損害額については、以下の等級表をご参照ください。
後遺障害等級認定とは?

後遺障害等級認定とは、症状固定後に残存する障害について、その程度を医学的に評価し、労災保険制度に基づく補償額を決定するための制度です。
● 障害補償給付(労災保険)
労災保険における後遺障害給付は、1級~14級の等級に応じて一時金または年金が支給されます。例えば、8級の場合には給付基礎日額の156日分が支給される一時金となります。
● 等級認定の方法
原則として、被災者が症状固定後に障害補償給付請求書を提出し、以下のような資料を添えて認定を求めます。
- 医師作成の「障害診断書」
- X線やMRIなどの画像所見
- 関節可動域測定結果(日本整形外科学会基準等)
- 日常生活動作の制限状況に関する書面
等級の認定は、労働基準監督署を通じて行われ、特に可動域制限の計測誤差や、診断書上の表現のあいまいさによって、適正等級が認定されない事例もあります。
このような場合に、弁護士の関与が重要になってきます。
たとえば、股関節や膝関節の可動域制限があるにもかかわらず、医師がきちんと角度測定を行っていない、あるいはMRI画像で神経障害が示唆されていても、それが診断書に反映されていないといったケースです。
弁護士が介入することで、次のような対応が可能になります。
(1)適切な医証の収集
症状固定前に弁護士が関与すれば、必要な画像検査(CTやMRI)や可動域測定の実施を医師に依頼するよう助言できます。
(2)異議申立て・再請求の実施
不当に低い等級が認定された場合でも、労災保険には「審査請求」の制度があります。これにより、新たな医証を添付して再度認定を求めることができます。
等級が1級異なるだけで、労災の障害補償給付や逸失利益においては数百万円規模の差が出ることが少なくありません。まさに弁護士の介入が、「補償の実質的な差」に直結するといえるでしょう。
会社に損害賠償を請求する場合

事故原因が使用者側にある場合には、民事上の損害賠償請求(不法行為または安全配慮義務違反)を併せて行うことが可能です。
● 使用者に対する法的責任
労働契約法第5条では、使用者に対して「安全配慮義務」が課されており、これに違反した結果、労働者が傷病を負った場合には、損害賠償請求ができます。
たとえば、墜落防止措置(安全帯の未設置)、フォークリフトの運転資格者の不在、危険作業への注意喚起の欠如などが認められれば、会社側の過失が認定されます。
(労働者側の過失も争われることがほとんどです)
● 請求できる損害項目
- 傷害慰謝料(入通院の精神的損害)
- 後遺障害慰謝料(将来にわたる精神的損害)
- 逸失利益(後遺障害による収入減少の補填)
- 将来介護費・装具交換費(等級に応じて)
- 弁護士費用(訴訟等で認容される一部)
労災保険の種類

そもそも労災保険では、どういった給付を受けることができるのでしょうか。
| ①療養(補償)等給 →労災による傷病治癒されるまで無料で療養を受けられる制度 ②休業(補償)等給付 →労災の傷病の療養のために休業し、賃金を受けられないことを理由に支給されるもの ③傷病(補償)等年金 →療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級(第1級から第3級)に該当するときに支給されるもの ④障害(補償)等給付 →傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合に支給されるもの ⑤遺族(補償)等給付 →労災により死亡した場合に支給されるもので、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類が存在する ⑥葬祭料等(葬祭給付) →労災により死亡した場合で、かつ葬祭を行った者に対して支給されるもの ⑦介護(補償)等給付 →傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受給し、かつ現に介護を受けている場合に、支給されるもの ⑧二次健康診断等給付 →労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、身体に一定の異常がみられた場合に、受けることができるもの |
その種類は、
8つとなっており、このうち、後遺障害が残ってしまった場合に関連する給付は④の障害(補償)等給付となります。
障害(補償)等給付の種類

| ・障害等級第1級から第7級に該当:障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金 ・障害等第8級から第14級に該当:障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金 |
障害(補償)等給付としての支給は、傷害の程度により大きく2つにわけることができます。
後遺障害の等級は、大きな後遺障害ほど小さい数字の等級が認定されるので、第1級から第7級という後遺障害のなかでも特に深刻なものについては、年金として、等級に応じた金額が毎年(6期に分けて支給)支払われます。
慰謝料は?弁護士に依頼する必要があります

労災からもらえる金銭以外で、会社に請求できるものがあります。
まずは、
後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という2つの損害を請求できることになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的な損害に対する補償です。
後遺障害の等級により金額が異なり、例えば6級の場合、弁護士基準(いわゆる「赤本基準」)では、1180万円を請求することができます。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害により将来的な稼働能力が低下することに対する補償です。
後遺障害逸失利益は、基礎収入に各等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間(症状固定時から67歳までの期間)に応じたライプニッツ係数を掛けて計算します。
ライプニッツ係数とは、将来にわたって発生する賠償金を先に受け取る場合に控除する指数をいいます。
例えば11級の労働能力喪失率は、67%です。
例えば、年収400万円の正社員で症状固定時に40歳であれば、単純計算、400万円×67%×14.6430=3924万円になります。
判例・解決事例の紹介

ここでは、実際に弁護士が介入し、等級認定・損害賠償で有利に解決できた事例を一部紹介します。
事例① 450万円を獲得したパート従業員(バック走行するフォークリフトに足を踏まれた事案
弁護士に相談・依頼するメリット

後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、労災からは支給されません。
これらを請求するには、自分が所属する会社などを相手に損害賠償請求を行う必要があります。
ただ、この損害賠償請求は、会社に過失(安全配慮義務違反)がなければ認められません。
会社に過失が認められるかどうかは、労災発生時の状況や会社の指導体制などの多くの要素を考慮して判断する必要がありますので、一般の方にとっては難しいことが現実です。
弁護士にご相談いただければ、過失の見込みについてもある程度の判断はできますし、ご依頼いただければそれなりの金額の支払いを受けることもできます。
また、一般的に、後遺障害は認定されにくいものですが、弁護士にご依頼いただければ、後遺障害認定に向けたアドバイス(通院の仕方や後遺障害診断書の作り方など)を差し上げることもできます。
そのため、労災でお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
労働災害については、そもそも労災の申請を漏れなく行うことや、場合によっては会社に対する請求も問題となります。
労災にあってしまった場合、きちんともれなく対応を行うことで初めて適切な補償を受けることができますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






