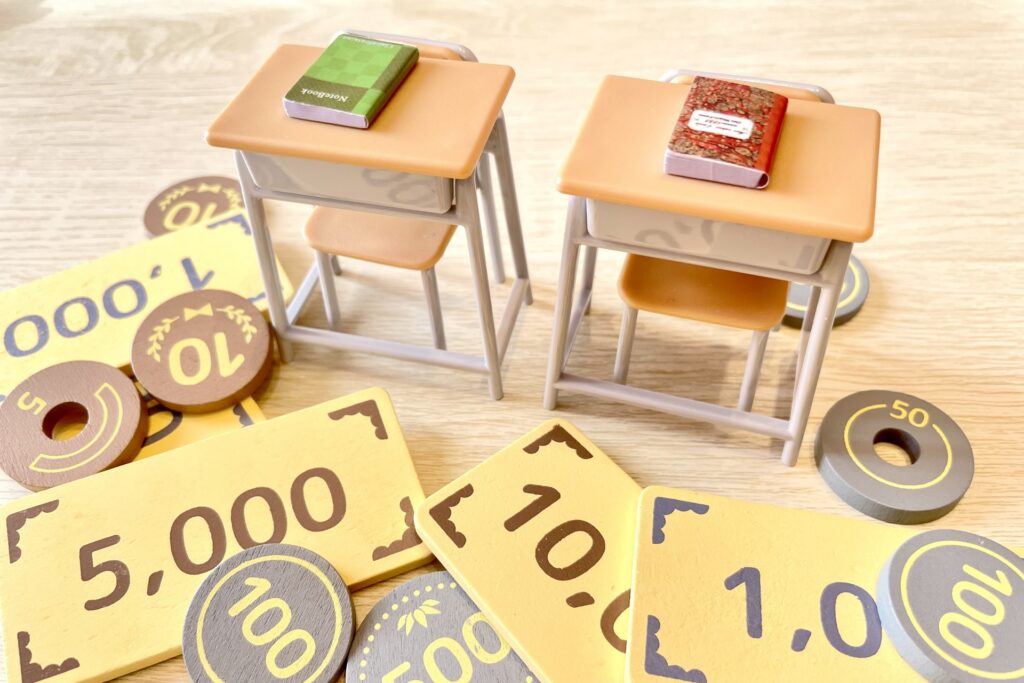
離婚後の子どもの健やかな成長を支えるものとして「養育費」があります。
しかし、離婚後、支払いが滞ってしまうケースは少なくありません。
養育費の不払いは、単なる金銭問題ではなく、子どもの生活と精神的な安定に大きな影響を及ぼします。
本コラムでは、養育費の支払いが滞った際に、泣き寝入りせずに、子どものために毅然と対処するためのステップと、利用できる法的手続きを弁護士が具体的に解説するページとなっています。
1 未払の事実確認と初期対応

養育費の支払いが期日までに確認できなかった場合、まず行うべきは、状況の冷静な確認と初期のコンタクトです。
具体的には、支払いが遅れていることを確認したら、まずは相手に直接連絡を試みましょう。電話、メール、LINEなど、連絡手段は問いません。
その際、感情的にならず、「○月分の養育費の入金が確認できていません。いつまでに振り込んでいただけるかお知らせください」など、事実と要望を明確に伝えましょう。
この初期の連絡で支払いが再開されれば、手間や費用をかけずに問題が解決します。
口頭やメールでの催促に応じない、または連絡を無視される場合は、内容証明郵便を用いて書面で正式に請求を行いましょう。
内容証明郵便を用いるメリットは以下のとおりです。
・心理的プレッシャー: 郵便局が内容と発送日、相手への到達日を証明するため、相手に「法的な手続きに進む可能性がある」という強いプレッシャーを与えられます。
・証拠の確保: 養育費を請求したという確実な証拠を残せます。これは、後の法的手続きで重要になります。
2 裁判所の手続を利用

直接の連絡や内容証明郵便の発送をしたにもかかわらず支払いが再開されない場合、家庭裁判所の制度を利用して、支払いを促す段階へ進みます。
これらの手続きは、原則として養育費の取り決めが、調停調書、審判書、または公正証書(執行認諾文言付き)といった「債務名義」として存在する場合に有効です。
① 履行勧告(りこうかんこく)
履行勧告は、家庭裁判所が、比較的簡単な手続きで相手に支払いを促してくれる制度です。
養育費の取り決めを行った家庭裁判所に対し、履行勧告の申出をします。裁判所が調査官を通じて相手の支払い状況や事情を調査し、電話や書面で支払いを勧告します。
履行勧告を行うメリットは、 費用がかからず、裁判所が間に入ってくれるため、心理的な負担が軽減されます。
もっとも、法的な強制力はありません。勧告を無視しても罰則はありませんが、裁判所からの連絡であるため、プレッシャーを感じて支払いに応じるケースはあります。
② 履行命令(りこうめいれい)
履行勧告でも効果がない場合に利用を検討する手続きです。
具体的には、家庭裁判所が、相当と認めるときに、義務者(支払う側)に対し、一定の期間内に養育費を支払うよう命令します。
正当な理由なくこの命令に従わない場合、10万円以下の過料(行政罰)に処せられる可能性があります。
効力の強さは、履行勧告よりは強いですが、財産を強制的に差し押さえるまでの強制力はありません。
3 最終手段 強制執行(財産の差し押さえ)

裁判所からの勧告や命令にも応じない場合、最終手段として強制執行(差し押さえ)を行い、相手の財産から強制的に養育費を回収します。
債務名義の必要性
強制執行を行うためには、「養育費を支払う義務がある」ことを公的に証明する書類、すなわち「債務名義」が必要です。
債務名義となる書類は、下記の書類があります。
・公正証書(「強制執行認諾文言」が付いているもの)
・調停調書または審判書(家庭裁判所の調停や審判で養育費が定められた場合)
・判決書(確定判決)
口約束や単なる離婚協議書(公正証書でないもの)だけでは、原則として強制執行はできません。
この場合は、まず家庭裁判所に養育費請求調停を申し立て、調停調書や審判書を得る必要があります。
差し押さえの対象と効果
強制執行では、相手の給与、預貯金、不動産などの財産を差し押さえることができます。
一般債権の場合、給与の手取り額の4分の1しか差し押さえられませんが、養育費の場合、原則として手取り額の2分の1まで差し押さえが可能です(ただし、手取り額が66万円を超える場合は上限が変わります)。
預貯金差押えの場合、口座残高が未払分よりも少ない場合、残高分しか差押が出来ませんのでご注意下さい。
強制執行手続きの流れは下記のとおりです。
1 債務名義の準備(執行文付与手続きなど)
↓
2 相手の財産の調査・特定(給与差し押さえの場合は勤務先の特定が重要)
↓
3 地方裁判所への申立て
↓
4 差押命令の発令と送達
↓
5 未払養育費の回収
財産開示制度の強化

「相手の財産がどこにあるか分からない」という問題は、強制執行の大きな壁でした。
しかし、2020年4月に施行された民事執行法の改正により、その状況は大きく変わりつつあります。
この改正により、強制執行に必要な「債務名義」を持っている債権者(養育費を受け取る側)は、裁判所に申し立てることで、債務者(支払う側)に対し、自身の財産状況を裁判所で陳述するよう強制できるようになりました。
まとめ

養育費の不払いは、子どもの生活基盤を揺るがす重大な問題です。
まずは直接の催促から始め、応じない場合は、家庭裁判所の履行勧告・履行命令、そして最終手段として強制執行をためらわずに利用すべきです。
そして、何よりも重要なのは、早い段階で弁護士などの専門家に相談し、最も効果的で確実な回収方法を選択することです。
決して一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






