
交通事故で大切な愛車が損傷したとき、まずは修理をすることが考えられます。
しかし、相手の保険会社から、「経済的全損」として、修理費ではなく時価額を上限に賠償しますと言われることがあります。
この「経済的全損」という概念は、物理的には修理が可能な状態であるにもかかわらず、賠償のルール上、修理費の全額を支払ってもらえないという、被害者にとって厳しい判断基準です。
ここでは、経済的全損がどういう概念であるか、そしてそう判断されたときの対応についてご案内いたします。
経済的全損とは何か?その法的根拠と具体例

経済的全損とは
物損事故における損害賠償の基本的な考え方は、「事故がなかった状態」(原状)に戻すために必要な費用を支払うという「原状回復」の原則にあります。
車両が損傷した場合、通常はその修理費用が損害額となります。
しかし、実務上確立しているルールとして、修理費用が、事故直前の車両の市場での価値(時価額)を超えてしまう場合、賠償額は時価額を上限とするとされています。
なぜなら、市場でその車と同等のものを手に入れる費用(時価額)以上の修理費を請求することは、社会経済的な合理性を欠き、過剰な賠償となると考えられているからです。
この「修理費用 >$車両時価額」という状態を指して、「経済的全損」と呼びます。
経済的全損の具体例
【事例】
被害者Aさんの所有する車は、登録から10年が経過した人気の軽自動車でした。
事故による損傷が大きく、修理工場が出した見積もりは120万円。
しかし、相手保険会社が算定したこの車両の事故直前の市場価格、すなわち時価額は80万円でした。
【保険会社の主張】
保険会社は、修理費120万円が時価額80万円を上回っているため、この車は「経済的全損」であると判断します。
したがって、保険会社がAさんに賠償するのは、修理費全額ではなく、上限である80万円となります。
【Aさんの直面する問題】
この場合、Aさんが車を修理して乗り続けたいとすれば、修理費120万円から賠償金80万円を差し引いた40万円を、Aさん自身が負担しなければなりません。
もし買い替えを選んだとしても、保険会社が提示した80万円では、同程度の状態の車を中古車市場で探し、購入するための費用として不十分である可能性が高いです。
相手方の過失による事故であるにもかかわらず、経済的に大きな不利益を被ることになってしまいます。
経済的全損と判断された際に、被害者が争うべき二つのポイント

保険会社から経済的全損を通知されたとしても、直ちに不利益を被るわけではありません。
この判断の根幹となる「修理費用」と「車両時価額」について、弁護士と連携し、争うべきです。
修理費用の「相当性」を証明する
まず、保険会社が経済的全損と主張する根拠である修理費見積もりについて、その内容が事故前の状態に戻すために必要かつ相当な額であることを確認します。
例えば、修理費が時価額をわずかに超える程度である場合、被害者がその車に特別な愛着を持っている、あるいは代替性のない特殊な車両であるなど、「特段の事情」を主張することで、時価額を上回る修理費の全額賠償が認められるケースが、裁判例上存在します。
時価額の120%〜130%程度までの修理費であれば、全額が認められる可能性もあります。被害者の方の「どうしても修理して乗りたい」という強い要望と、その車に対する特別な事情を具体的に主張し、経済的全損の判断そのものを覆すことを目指します。
車両時価額に異議を唱える
経済的全損の判断において最も重要かつ争いやすいのが、保険会社が提示する車両時価額です。
保険会社は、一般的に業界内で用いられる目安の価格表(レッドブックなど)や、中古車業者の仕入れ価格に近い金額を時価額として提示しがちです。
しかし、時価額とは、被害者が事故車と同等の車両を、中古車販売店から一般の消費者として購入するために必要な費用、すなわち小売価格を基準とすべきです。
保険会社が提示した時価額があまりにも低いと感じた場合、被害者自身が証拠を集め、適正な時価額を主張する必要があります。
具体的には、中古車販売サイトを活用し、ご自身の車と年式、走行距離、グレード、オプションなどが極めて近い類似車両の販売価格を複数検索・印刷して証拠とします。
そして、その検索結果に基づき、保険会社が提示した金額では同等の車両を市場から調達できないことを明確に指摘し、時価額の引き上げを強く要求していくべきです。
具体的な行動と弁護士の役割
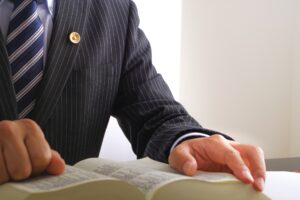
時価額を増額するための具体的行動
先述の通り、時価額を争うためには客観的な証拠が必要です。被害者の方がご自身でできる行動としては、以下の通りです。
【具体的な行動の例】
例えば、あなたの愛車が「2015年式、走行距離8万km、トヨタ・プリウス 」であったとします。
保険会社から時価額80万円を提示されたとすれば、中古車販売サイトで「2015年式、プリウス、走行距離7万~9万km」といった条件で検索を行います。その結果、同等の車両が販売店で110万円から130万円で実際に販売されていることが判明すれば、その検索結果画面を保存(印刷またはPDF化)し、それを根拠として「提示された80万円では同等の車両を購入できないため、時価額は少なくとも120万円を要求する」と保険会社に主張すべき。
また、カーナビや高額なオーディオ、特別なエアロパーツなど、後付けした付属品についても、その価値が時価額に含まれていない場合があります。
これらの付属品についても購入時の証明書や見積書を用意し、車両本体の時価額に加えて個別に賠償を求めるべきです。
弁護士に依頼する経済的メリット
このような時価額の算定や、修理費の相当性に関する交渉は、手間がかかります。
弁護士に依頼することで、弁護士は上記のような証拠収集と交渉を代行し、法的な根拠に基づいて適正な時価額を主張します。
特に、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付帯していれば、その特約を利用することで、実質的な自己負担なしで弁護士の力を借りることが可能です。
まとめ

交通事故の物損事故、特に「経済的全損」の問題は、時に深刻な問題となります。
保険会社が提示する「経済的全損」という判断は、多くの場合、法的な正論ではありますが、その根幹となる車両の時価額の算定において、低い金額が主張されることがあります。
愛着のある車を修理するために自己負担を強いられる、あるいは、買い替え費用が不足し、事故前の生活レベルを回復できないという結果を招く恐れがあります。
このような状況で、被害者の方が愛車の価値と適正な賠償額を守るためには、弁護士の存在が不可欠です。
交通事故の被害者の方にとって、保険会社との煩雑でストレスの多い交渉から解放され、経済的に納得のいく解決を得ることは、事故からの生活再建において極めて重要です。
ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯していれば、費用を気にせず弁護士に依頼することが可能です。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。












