
将来的に自身の判断能力が低下したときのことを考え、今の段階から、次の世代への財産の承継を考えている方もいらっしゃると思います。このコラムでは、財産承継の手段としての家族信託について、後見制度などと比較しながら解説します。
1 相談事例

70代のAさんは、現時点では特に持病などはありません。
また、物忘れなども特にありません。
ただ、年齢のこともあり、自らの財産をどのように次の世代に承継していくか、悩んでいます。
特に心配しているのは、Aさんが所有する複数の収益不動産についてです。
この不動産については、現在、不動産関係の仕事をしており、専門知識をもっている次男に引き継いでもらいたいと思っています。
また、自分の判断能力が低下してから不動産を引き継ぐと、各物件の事情を伝えることができない等、次男に負担になるので、自分が元気なうちから引き継いでいきたいと考えています。
2 家族信託とは
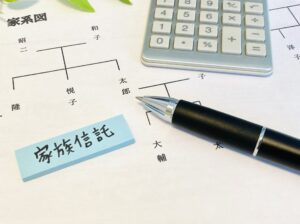
「家族信託」とは、親が子供などに財産を託して、子供がその託された財産の管理をするという制度です。また、財産の承継先を決めることもできます。
家族信託では、大きなところでは、以下の役割の人物が登場します。
①委託者
信託の目的を定めたうえで、現金や不動産などの財産(信託財産)を託す人のことです。
②受託者
委託者から信託財産を託された人のことです。信託の目的に沿って、信託財産の管理・運用・処分をおこないます。
③受益者
財産管理から生じた利益を受け取る人のことです。
上記の相談事例では、Aさんは、家族信託を利用することで、自らの収益不動産について、次男を受託者として移転し、そこからの収益をAさん自身が受け取ることが考えられます。
3 後見制度との違い

財産管理としては、似たような制度として、成年後見制度があります。
家族信託との違いは、以下のとおりです。
⑴ 財産管理がなされるまでの期間
まず、成年後見制度の場合、判断能力が低下したときになってから、はじめて家庭裁判所に後見開始の申立てをおこないます。裁判所が、後見を開始することが相当であると判断すると、成年後見人が選任されます。
よって、判断能力が低下してから、成年後見人による財産管理が開始されるまでに、数か月かかることが通常です。
一方、家族信託の場合、判断能力が低下する前に信託を設定し、受託者が財産管理を開始することが通常です。
よって、誰も財産管理を適切に管理できないという期間が生じることを防ぐことができます。
⑵ 財産を託す人を選ぶことができる
成年後見制度には、法定後見と任意後見がありますが、法定後見の場合、成年後見人は裁判所が職権により選任します。そのため、初対面の人が後見人に選ばれて、自分の財産を管理することもあります。
なお、任意後見の場合、自分の選んだ候補者が成年後見人に就きますが、任意後見人を監督する任意後見監督人が全件で選任されます。任意後見監督人の報酬は、継続して発生します(任意後見人にも報酬が発生すると、二重の費用負担が生じます)。
一方で、家族信託の場合には、自分で受託者を選ぶことになりますので、自らの意向を反映してくれる人に財産を託すことができます。
また、管理費用については、受託者と相談して決めることができます。
⑶ 財産管理の柔軟性
成年後見制度では、家庭裁判所の関与のもとで、後見人が財産管理をおこないます。
この成年後見人は、原則として、ご本人の財産を守ることに重点が置かれます。そのため、例えば、新たに借り入れをして財産を改良するといった、リスクのある選択をすることは困難です。また、本人の自宅不動産を売却するときは、家庭裁判所の許可を得る必要があり、自由に処分することはできません。
これに対して、家族信託では、委託者の財産を積極的に利活用することが可能です。また、自宅不動産を売却する際も、家庭裁判所その他の第三者の許可は不要です。
つまり、信託は、委託者の意向次第では自由度が高く、より柔軟な資産管理や運用が可能となります。
4 家族信託のその他の使い方

家族信託は、財産の承継以外にも、次のような使い方もあります。
⑴ 子どもに障害がある場合
子どもに知的障害や精神障害があるご家庭では、親である自分が亡くなったあとも、障害のある子供のために、財産を有効に使ってほしいという希望をお持ちの方も多いと思います。
このようなとき、家族信託を利用することで、子どもの障害や特性に理解のある兄弟などに、財産を委託することができます。
また、財産管理の方針についても、親と委託者においてあらかじめ決めることができます。委託者が財産を管理するので、子どもがお金を無計画に使ってしまうのを防ぐこともできます。
⑵ 二次相続以降の財産の相続先を指定したい場合
例えば、収益不動産について、まずは次男に相続させ、その次男が亡くなった時には長男に相続させたいという場合、遺言の形式では、二次相続以降の財産の帰趨を指定することはできません。
一方、信託の場合には、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という形の信託により、上記のような指定をすることが可能になります。
5【まとめ】家族信託に関心があるときは、ぜひ弁護士へ相談を

これまで見てきたように、家族信託は、成年後見制度と比べて自由が高く、さまざまなメリットがあります。
一方で、身上保護はおこなわれない、家庭裁判所による監督はなされないといったデメリットも考慮する必要があります。
家族信託は、一般の方にとってはやや複雑ですので、ご関心のある方は、ぜひ一度、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






