
こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。
遺産分割が終わっていない不動産を、相続人の一人が居住・占有しているといった状況は、実務上、他の相続人との間でトラブルになりやすいものです。では、法律はこのようなケースをどのように整理しているのでしょうか。本コラムでは、共有不動産、賃料債権、明渡し請求などをめぐる法的関係を、判例と条文を交えて分かりやすく解説します。
遺産共有について

相続の開始から遺産分割が完了するまでの間、その相続財産は、相続人全員の共有に属するとされています。
したがって、遺産分割協議中、相続財産にあたる不動産の管理は、基本的に、民法の共有の規定に基づいて決されることになります。
共有者に対する明渡請求の可否について

民法の共有の規定に基づくと、共有者である共同相続人間の決定によらずに、相続財産の不動産を単独で使用する者がいた場合、他の共同相続人は、持分の過半数の決定により、その単独使用者に対して、不動産の明渡しの請求をすることができると解釈することもできます(民法252条参照)。
もっとも、それは、共有の規定に基づいた考え方であり、関係当事者間の関係によっては、別途の検討を要します。
例えば、亡き父の相続人である子Aが、亡き父の死亡後も相続財産である自宅に居住していたとして、他に相続人子B・子Cがいる事例を考えてみます。
ここで、その自宅において、亡き父と子Aが一緒に暮らしていたという事情があった場合、亡き父と子Aの間で、その自宅について、使用貸借契約が明示的に、若しくは、黙示的に成立していたと考えられる可能性があります。
この点、同様の事例において判例では、被相続人と同居の相続人がいた場合、特段の事情がない限り、相続開始を始期とし、少なくとも遺産分割終了までの間は、使用貸借契約関係が存続すると判断をされています(最判平成8年12月17日)。
したがって、上記の例では、亡き父と同居していた子Aは、遺産分割が完了するまでの間、子B・子Cに対して、使用貸借契約関係の存在を主張し、自宅の占有権原があると主張することができることとなるでしょう。
使用料の請求の可否について
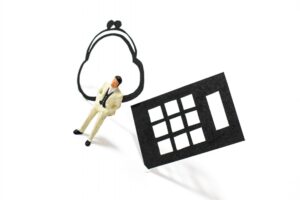
共同相続人のうちの一人が相続財産である不動産を単独で使用している場合、その者に対して、使用料を請求することはできるでしょうか。
まず、各共有者は、共有物の全部について、その持ち分に応じた使用をすることができるとされています(民法249条1項)が、共有物を使用する者は、基本的に、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うとされています(同条2項)。
もっとも、上記の法理は、従前、共有物を単独で使用している共有者に対して、不当利得や損害賠償請求を請求できるとした判例を基にしているため、不当利得の返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求がなしえない場合には、自己の持分を超える使用の対価を請求することもできないと考えられるでしょう。
すなわち、上記の例でいうと、子Aは、亡き父との間で成立した使用貸借契約が存続している場合には、その自宅に居住する権原を有しているため、不当利得の返還請求も、不法行為に基づく損害賠償請求もなしえないこととなります。
したがって、この例の場合には、子B・子Cが子Aに対して、使用の対価を求めることはできないものと考えられます。
他方で、子Aと亡き父が一緒に暮らしていたという事情がなく、相続開始後、子Aが勝手にその自宅に住み始めたということであれば、不当利得の償還請求や、居住の態様によっては、不法行為に基づく損害賠償請求もあり得るため、使用の対価を請求することができるものと考えられます。
無償使用することが特別受益にあたるか

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は、婚姻・養子縁組のため・生計の資本として贈与を受けた者がいるときには、相続財産の価額に、その贈与の価額を持ち戻して、相続財産を計算することになっています(民法903条1項)。
この遺贈や、婚姻・養子縁組のため・生計の資本としての贈与のことを、「特別受益」といいます。
この点、共同相続人のうちの一人が、相続財産の不動産を使用借させていた場合、その者は、自らの住居費の負担を免れたことになりますので、その使用利益が「特別受益」となるかが問題となり得ます。
もっとも、一般的に、建物の使用貸借は、恩恵的な側面が強く、遺産の前渡し的性質が弱いこと、また、建物の使用貸借は第三者に対抗することができず、経済的な価値も低いことなどから、被相続人が生計の資本としていた賃貸物件を使用貸借の対象にしたといった特段の事情がない限りは、この使用利益は、「特別受益」にはあたらないと解されています。
上記の例でも、亡き父が賃貸物件のような不動産を子Aに使用借させたといった特段の事情がない限りは、特別受益には当たらないものと考えられます。
なお、仮に特別受益に当たるとしても、被相続人が持ち戻しを免除する意思表示を行っていないかは、別途留意する必要があります。
まとめ

遺産分割前に特定の相続人が共有不動産を占有している状況では、他の相続人が賃料相当額の請求、明渡請求などの法的措置を検討できる可能性があります。もっとも、その検討には専門的な知見を要するため、相続人間での紛争が長期化する前に、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






