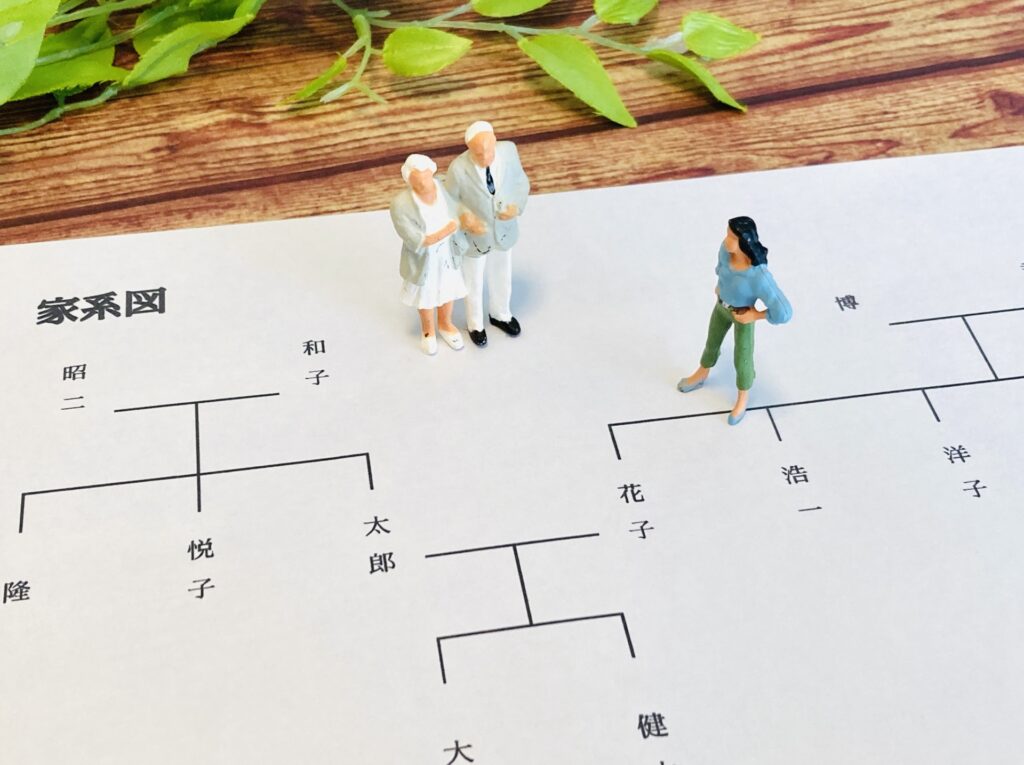
今回は、相続に関する相談事例をご紹介します。3人きょうだいの末娘が高齢の母親と長らく同居し、その面倒を見てきました。母親は遺言書を書くことなく、死亡。遺産分割で「このまま自宅に住み続けたい」との末娘の希望は叶えられるのでしょうか。
とある相続のご相談

C子さんは、2か月ほど前に亡くなられたお母様の相続のことで、相談にいらっしゃいました。
お父様はすでに亡くなっており、相続人は、子3名(長男A男さん、長女B江さん、次女C子さん)とのこと。
C子さんから聞き取った大まかな内容は、次のとおりです。
相談内容

私は3人きょうだいの末っ子で、上に兄(A男さん)と姉(B江さん)がいます。
この度、自宅で私と同居していた母親が高齢により亡くなりました。
父親は10年前に他界しています。
母の遺産としては、父から相続したものも多いのですが、以下のようなものがあります。
①自宅(土地建物):実勢価格で3000万円程度
②預貯金・有価証券:計3000万円
兄と姉は犬猿の仲で、昔から喧嘩が絶えず、母が亡くなった今は、お互いに生前贈与をもらっただろうと言い合っています。
母は生前、そんな上2人の様子を見るのが嫌で、父の死後、未婚の私を呼び寄せて同居することになりました。
私は母の介護もあったので、ここ10年はパート勤めです。
自分の生活費くらいは何とかなりますが、母の病院代や生活費も負担していたので貯金は無く、もう59歳なので正社員としての再就職は望めません。
私の望みは今の自宅にそのまま住み続けることですが、私自身も兄や姉から苛烈な感情を向けられることがあり、自分で話し合いをするのは難しいと感じています。
私はどうしたら良いでしょうか。
遺言書がないので遺産分割するしかないが・・・
上記のように、C子さんは10年近くお母様と同居し、その面倒を見てきました。
パート勤めで貯金も乏しい中、このタイミングで転居するのは困難ですので、「今の自宅にそのまま住み続けたい」という希望はよく分かります。
しかし、「遺言書はありますか?」との問いに、C子さんは浮かない顔で「ないんです」と言います。
「母は、常日頃、私に『面倒を見てくれたのはお前だけだから、全てお前に行くようにしてあげるからね』と言ってくれていたのですが、結局、遺言書などは書かないまま亡くなってしまって・・・」とのこと。
遺言書がない以上、他の相続人であるA男さん・B江さんも含めた3人で、遺産分割の話し合いをする必要があります。
ただ、C子さんが今後の遺産分けの話をしようとすると、A男さん・B江さんから、
「10年も同居してきたんだから、お前も、母から沢山援助を受けているはずだ」
「お前が母のお金を使い込んでいないか調べる必要があるから、母の通帳の履歴を10年分、きちんと出せ」
などと詰め寄られてしまうそうです。
C子さんご本人が、これ以上、A男さん・B江さんと当事者同士で遺産分割の話し合いをするのは困難な状態でしたので、C子さんから遺産分割交渉の依頼を受け、弁護士が代わりに交渉することにしました。
「このまま自宅に住み続けたい」との希望を守るために

蓄えがほとんどない状態での転居は現実的ではありません。
C子さんの希望は、とにかく、今の生活環境を変えたくない、「このまま自宅に住み続けたい」というものでした。
「今後の生活の足しに少しはお金ももらえればもちろん嬉しいですけど、今のパート勤めで何とか、自分一人が暮らしていく分には困らないくらいのお給料はいただけているので、お金が欲しいとは言いません」ともおっしゃいます。
そこで、まず弁護士が検討したのは、遺産の構成と評価、各人の法定相続分を考えたうえで、どのようにC子さんの希望を叶えるかです。
お母様の遺産は、
①自宅(土地建物):実勢価格で3000万円程度
②預貯金・有価証券:計3000万円
です。
ここで、①の不動産の評価方法を、例えば「固定資産評価額」ベースにしたり、「路線価」ベースにするなどして、評価額を下げる方法も考えました。
不動産の評価額を下げることができれば、不動産の取得を希望するC子さんの有利になるからです。
しかし、本件の不動産が位置しているのは郊外とはいえ、駅近の生活の便の良い場所であることから、実勢価格で「3000万円程度」というのは至って妥当な金額だと思われましたし、(失礼ながら)お金にうるさいA男さん・B江さんが敢えて自分達の不利になる評価方法を採用することに同意するとは思えませんでした。
そうすると、遺産の総額は①と②を合わせて合計「6000万円」、3名の相続人の法定相続分が各「3分の1」ですから、各人の取り分は「2000万円」(6000万円×3分の1)となります。
この計算でC子さんが自宅不動産を取得するとなると、C子さんは、「本来2000万円しか取り分がないところ、3000万円の財産を取得する」ことになって、差額の1000万円をA男さん・B江さんに代償金として支払わなければならないことになります(A男さんに500万円、B江さんに500万円を支払う)。
しかし、C子さんに合計1000万円もの大金を用意するだけの資力はありません。
代償金が用意できなければ、最悪は自宅不動産を売却換価したうえで、全てを金銭の形で3等分するしかなくなってしまうかもしれません。
ここまでの考え方をC子さんにお伝えすると、「やはりそうなるのですね。今の家を出て行くとなると、転居費用もかなりかかるでしょうし、もう路頭に迷うしかないですよね・・・」と沈痛な面持ちでした。
兄姉の生前贈与を主張する

このままでは、「このまま自宅に住み続けたい」というC子さんの希望を叶えることは困難になってしまいます。
そこで、弁護士が目を付けたのが、相談の際にC子さんが、
「兄と姉は犬猿の仲で、昔から喧嘩が絶えず、母が亡くなった今は、お互いに生前贈与をもらっただろうと言い合っています」
とおっしゃっていたことです。
もちろん、仲の悪い兄姉が、さしたる根拠もなしに、相手方を牽制するためにそのようなことを言っているだけという可能性もありますが、お母様からA男さん・B江さんに、何らかの生前贈与がなされているのではないかと考えました。
しかし、これを真正面から本人達(A男さん・B江さん)に聞いても、本当の答えは返ってこないでしょう。
この点をC子さんに確認すると、
「兄は、確か、今の自宅を建てる時に結構な金額を母から出してもらって助かった、みたいな話をしていたことがあります」
「10年くらい前に、母が、『子ども達が大きくなってきたのに、いつまでも小さい車じゃ可哀相だから、B江に大きい車を買ってやった』と言っていて、羨ましく思ったのを覚えています」
とのこと。
もちろん、いずれもだいぶ前の話ですので、これらを裏付ける客観的な証拠は残っていないかもしれません。
しかし、お母様は重要そうなものは何でも取っておく性分で、かなり古い通帳も自宅にあるとのことでした。
そこで、C子さんに、2人への生前贈与を裏付ける証拠がないか、探してもらうことにしました。
そうしたところ、お母様名義の古い通帳がそっくり取ってあり、平成27年●月●日に900万円を出金した箇所に、お母様の自筆で「A男へ 新築援助」と書き込まれている履歴が見つかりました。
また、お母様が日々の出来事や料理のメモなどを書き込んでいた雑記帳の中に、「平成25年●月●日、B江に車450万円(トヨタ)」との記載と、ATМの振込票(お母様から現金450万円をB江さんの口座に送金したもの)がホチキスで留められているページがあるのを発見したのです。
以上から、A男さんは900万円の、B江さんは450万円の生前贈与を受けていることが分かり、弁護士からA男さん・B江さんにそれぞれ根拠資料を示して確認したところ、2人とも、お母様からその額の援助を受けた事実を認めました。
寄与分類似の主張

上記のように、A男さん・B江さんの生前贈与が証明できたわけですが、これでも、計算上はまだ、C子さんに代償金の負担が生じてしまいます。
(6000万円+900万円+450万円)×3分の1=2450万円
A男さんの取り分:2450万円-900万円=1550万円
B江さんの取り分:2450万円-450万円=2000万円
C子さんの取り分:2450万円
※3000万円の不動産を取得しようとすると、550万円超過
そこで、次に、弁護士が考えたのが寄与分の主張でした。
裁判実務では、寄与分が認められるハードルは極めて高く、一般的な親族の扶養のレベルを超えた献身と、それにより被相続人の遺産を増加させた(ないし減額を防いだ)と言えることが必要です。
しかしながら、本件でのC子さんは、10年前にお母様に呼び寄せられる形で同居と介護を始めており、しかも、お母様の介護のため、それまで正社員だったのをパート勤めに変更してまで、献身的に面倒を見てきたのです。
何とか報われる方法はないかと思いました。
C子さんは、聞き取りの際、
「母の病院代や生活費も負担していたので貯金は無く・・・」
とおっしゃっていました。
労力による無形の献身部分を金銭で評価するのは難しくても、せめて、お母様の介護や医療費の支払いに充てたものについては、総額を計算して、交渉に使えないかと考えたのです。
まめな性格のC子さんは、お母様の介護が必要になった10年ほど前から、ケースワーカーとのやり取りやお母様の心身の状態と一緒に、自身の預貯金からお母様のために支出した費用を細かく記載した、自称「介護ノート」を持っておられました。
そこには、介護タクシーを手配した時のレシートなど、支払いを証明する資料も貼り付けられています。
お母様ご自身の金融資産もかなりの金額あったのですが、年金の受給額が少なかったためか、お母様は「このままではお金がなくなっちゃう」と騒いで、自分の預貯金から医療費や介護にかかる諸々の費用を出すことを極度に渋っていたそうです。
そこで、C子さんがやむなくそれらの費用を支払ってきたとのことでした。
「介護ノート」によると、入通院や手術、リハビリにかかる費用、介護用品の購入・レンタルなど、この10年間でC子さんがお母様のために支払ってきた費用の総額は、何と、およそ600万円にものぼっていることが分かりました。
つまり、C子さんはお母様の金融資産から600万円が目減りするのを防いでいたと言えるのです。
もちろん、裁判実務ではこうした金額の全てが寄与分として認められるわけではないですし、単純な立替金請求権として処理すべきとの考え方もあるでしょう。
しかし、交渉の段階では、仮に、この600万円をC子さんの寄与分として計算し、
(6000万円+900万円+450万円-600万円)×3分の1
=2250万円
A男さんの取り分:2250万円-900万円=1350万円
B江さんの取り分:2250万円-450万円=1800万円
C子さんの取り分:2250万円+600万円=2850万円
※3000万円の不動産を取得しようとすると、150万円超過
としてみました。
この計算でいけたとしても、C子さんには代償金(150万円)の支払義務が生じてしまいますが、C子さんは「150万円であれば何とかなります」とおっしゃいます。
母が遺してくれた生命保険

お母様のために正社員としての仕事を辞め、また、お母様の医療費や介護費用を負担してきたために、C子さんには蓄えがほとんどありません。
そんなC子さんが、「150万円なら何とかなる」とおっしゃいます。
実は、お母様は生前、受取人をC子さんとする、300万円の生命保険に加入しており、その保険金300万円がC子さんに支払われていたのです。
この300万円を、代償金150万円の支払いに充てることができます。
その後、「介護ノート」の記載や支払いを証明する資料をもとに、A男さん・B江さんに対して、C子さんがお母様のために支出した600万円を寄与分に類するものと見て清算すべきと主張。
代償金として合計150万円を2人に支払うので、自宅不動産はC子さんに単独で取得させて欲しいと交渉しました。
多少時間はかかりましたが、最終的にはA男さんもB江さんも納得してくれ、相続人3名の間で遺産分割協議が成立しました。
C子さんは150万円の代償金を支払う代わりに、これまでどおり自宅に住み続けられることになったのです。
「どうして遺言書を書いておいてくれなかったのかと母を恨んだこともありましたが、最後の最後で、母の遺してくれた生命保険に救われました」と、ほっとした表情を見せるC子さん。
スタート時点では厳しい状況でしたが、「このまま自宅に住み続けたい」というC子さん最大の希望が叶えられて、円満解決した事案でした。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






