
「死亡した親(父母)の面倒を今まで見てきたのに、何もしていない兄弟姉妹が自分と同じ額の遺産を相続した」「遺産分割をする際に問題になる寄与分について知りたい」「相続についての基礎知識が知りたい」という方に向けて、今回は相続に関する「寄与分」という概念やこれに関する制度をご説明します。
初めての方に向けてもわかりやすく解説いたしますので是非ご一読ください。
寄与分とは

寄与分とは、相続が発生した際に、「各相続人がどの財産をいくらもらうのか」を決めるために考慮されるものです。わかりやすさを重視して説明すれば、各相続人の相続財産を維持・増加させたことへの対価、です。
相続が発生する場面を想像してください。
相続人の一人が、闘病中の親の看護をつきっきりでしていることがあります。そして、自身は親のために身を粉にして看病したのに、他のきょうだいなど他の相続人は一切助けてくれなかったとします。
このような相続人一人の頑張りとは関係なく、法律に定められたとおりの取り分による相続(法定相続といわれます。)を認めてしまうとすると、看護をしてきた相続人は、不平等であると感じることでしょう。
このような問題に対処するために、法律上、「寄与分」があると認められる相続人は、これを加味して一定程度相続分を多く算定してもらうことが出来ます。
何をすると寄与分が認められるのか

寄与分が認められるためのポイントは、大きく3つあります。
ひとつは、①被相続人のために貢献をしたこと(寄与行為)です。もう一つは、②寄与行為が被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたと評価できることです。最後の一つは、③通常期待される程度を超えること(特別の寄与)であることです。
ポイント①寄与行為の有無

例えば、被相続人は母親であり、既に父親は死亡している状況で、あなたは母親と同居していたところ母親が亡くなったとします。そして、あなたには、既に離れたところで暮らす弟が一人いたとします。
このような場合、あなたが母親と同居していたことだけでは寄与行為の存在は認められません。
以下の場合に寄与行為が認められます。
被相続人の事業に関して労務の提供をした場合
被相続人の事業に関して労務を提供していた場合には、寄与分が認められることがあります。例えば、被相続人が農業をしていたところ、相続人が農作業を手伝ってきた、被相続人の代わりに農作業を行ってきた場合は、これにあたります。
この場合における被相続人の事業については、特に限定はなく、農業、漁業、自営業、医師等の職業、営利目的ではない活動も含まれると理解されています。
財産上の給付をした場合
生前の被相続人に対して、相続人が金銭を与えていた、不動産を無償で使用させていたような場合にも、寄与行為があったと評価されることがあります。
被相続人の療養監護をした場合
冒頭の例で紹介したのは、この場合です。
被相続人が生前病気療養中に、相続人から介護されていた場合に寄与行為が認められます。ただし、あくまで病気や高齢により動作が難しいなど、生活に支障をきたしている被相続人のために介護をしていた場合に限り、療養監護による寄与行為が認められます。
健常な被相続人に好意で何かをしてあげても、療養監護にはなりません。
その他の場合
上に挙げられたほかにも、被相続人の財産の維持または増加に対して寄与行為をした場合があげられます。
例えば、被相続人が所有している不動産を、相続人の一人が大家として管理しており、これに対して被相続人は管理費用の出費を免れてきたような場合には、寄与行為が認められます。
また、相続人が、被相続人を自宅に住まわせ、生活費を負担していたような浮揚をしていた場合も寄与行為が認められます。
ポイント②被相続人の財産の維持・増加

以上のような寄与行為があったとしても、被相続人の財産の維持・増加が生じていなければ、寄与分は認められないことに注意が必要です。
既にご紹介したように、寄与分とは、相続財産を維持・増加させた対価です。寄与行為によって相続財産が減ってしまっているようなら、相続人は特に貢献をしていないのですから、寄与分に値しません。また、酷な話ではありますが、被相続人の心の支えとなった場合のような、精神的援助も寄与分とは認められません。
ポイント③特別の寄与の有無

一般に、寄与分が認められるためには、その寄与行為が「特別の寄与」と評価されることが必要です。特別か否かは、通常期待される程度を超える特別の貢献があるか否か、わかりやすさを重視すれば「家族にも通常期待できないような相当な苦労を負担したか」によって判断されます。
例えば、「たまに被相続人のもとを訪れて代わりに買い物をしてあげる」程度では足りない可能性があります。
脳梗塞で家業を続けられなくなった親のために仕事を辞めて家業を継いだ、といった寄与が必要とされています。
寄与分が相続分にどのように影響するか

以上のように寄与分が認められた場合、どのように相続に影響するのでしょうか。
寄与分が相続分の算定のためにどのように影響するかについては、寄与の態様によって変わります。例として、事業に労務を提供した場合(家業を継いだ場合)を上げます。
家業を継いで、実家の従業員として働き、被相続人の遺産の維持・増加に貢献したとすれば、その働きへの対価として寄与分が生じます。
この場合、
本来受けるべき年間給与額(1-生活費控除割合)×寄与した年数
といった計算で算定されることがあります。
他方で、事件の性質によっては、こちらの算定式を用いずに、他の方法により寄与分が決定されることもあります。また、事件ごとにあらわれた、その他一切の事情や調整要素を加味して、事件ごとに寄与分が算定されることになります。
このように算定された寄与分については、最終的に各相続人の具体的相続分を計算する段階で算入され、寄与した相続人の取り分に反映されていくことになります。
まとめ
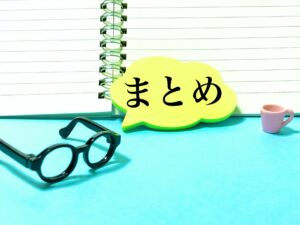
以上で解説してきましたように、寄与分は、相続人が遺産の維持や増加に貢献した場合のその対価です。そして、これらはある程度計算をすることが可能です。
もっとも、現実に寄与分を算定し、具体的相続分を判断するためには、相続に関するすべての事情を考慮しなければなりません。また、上に述べたように、複雑で専門的な判断を必要とします。
寄与分や相続に関する問題の対応には法律上難しい問題が多く隠れています。このような状況に対処するためにも、弁護士へ一度ご相談されることが推奨されます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






