
今回は、農地経営者がおこなった相続対策(遺言書の作成)の事例をご紹介します。相続人となる子ども達は不仲であり、一人に全てを相続させようとすると他の相続人から遺留分を請求される可能性が高く、しかし、遺産の中の流動資産が少ないというケースです。
農地経営者Aさんの悩み
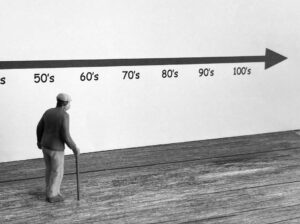
Aさんは埼玉県内で農地を経営していますが、自身が80歳を過ぎて高齢になってきたことから、ご自身亡き後の相続のことを考えるようになりました。
Aさんの家族構成と主な資産は、次のとおりです。
Aさんの主な資産
①不動産(自宅の土地・建物、駐車場として貸している雑種地1筆、田20筆、畑3筆)
②預貯金 合計約350円
③車(普通乗用車1台、軽トラック2台、トラクター3台)
④生命保険(3本で死亡保険金合計約3000万円)
Aさんの家族構成
妻Bさん(78歳、農業手伝い)
長男C(55歳、会社員)
次男D(53歳、農業手伝い)
長女E(50歳、看護師)
Aさんを支えて一緒に農業を経営してきたのは、妻Bと次男Dです。
長男Cは大学卒業と同時に家を出て、都内で就職。結婚後も、ずっと都内で生活しています。
長女Eも短大卒業後に家を出て、埼玉県内の別の市で看護師として働いています。一度結婚しましたが昨年離婚し、今は子1人を抱えて頑張っています。
Aさんの父親も祖父も、ずっとこの地で農業を営んできました。
田畑はご先祖様から受け継いだ、Aさんにとっての宝です。
順当にいって、今も一緒に農業をしている次男Dに、農地を含む全ての不動産を相続してもらい、名実ともに“家を継いでもらいたい”と思っています。
しかし、そんなAさんを悩ませていたのが、子ども達の仲が悪いことでした。
子ども達の不和

Aさんから聞き取った子ども達の様子は、次のようなものです。
長男Cは、「父親は昔から自分と顔形が似ているDばかりを可愛がっていて、自分は長男なのに、家に居づらい状態だった。だから、さっさと東京に出た」と言っているそうで、盆暮れもあまり顔を見せることはありません。
たまにDと顔を合わせた際には、必ずと言っていいほど、「親父の金で食わせてもらっている分際で、偉そうな顔するな」と言って喧嘩になります。
また、長女Eに対しては、離婚した配偶者のことで、「俺は最初からあの男はダメな奴だと思っていた」、「そんな男を選んだ結果、苦労しているんだから、自業自得だ」と言って、冷たい態度をとります。
次男Dは、今でこそ農業一筋で頑張っていますが、「本当は公務員になりたいという夢があったのに、長男のCが農業を継がずに出て行ってしまったので、自分がこの土地に縛り付けられることになってしまった」として、Cを恨んでいるとのこと。
長女Eには、「以前、子どもの学費が必要とかでまとまったお金を貸したのに、いつまで経っても返そうとしない」と言って、Eが実家に帰ってくると、そのお金の返済のことでEと揉めているそうです。
長女Eは、上記のとおり、長男Cからは離婚のことを、次男Dからは借金の返済のことを言われるのが煩わしく、それぞれと仲が良くありません。
同じ埼玉県内ということもあり、孫を連れてちょくちょく実家に遊びに来るのですが、その度に、Aさんから「何かと大変だろうから」と生活援助のためにお金をもらっていることも、C・Dの不満につながっているようです。
Aさんの相続対策

このように3人の子ども達の仲が悪いことを考えると、Aさんが何らの対策もとらずに相続が発生した場合、遺産分割において3人が揉めるであろうことは目に見えていました。
そこで、Aさんは、相続対策として、遺言書を作成しておくことにしました。
Aさんの一番の希望は、「今も一緒に農業をしている次男Dに、農地を含む全ての不動産を相続してもらい、名実ともに“家を継いでもらいたい”」というものです。
不動産の中には駐車場として貸している土地がありますが、この土地は自宅のすぐ裏に位置しているため、他の不動産と一緒にDに取らせたいとのこと。
また、預貯金も、農耕用のトラクターを含む車(合計6台)も、当然ながらDが取得するのがよいだろうと考えていました。
なお、妻Bには、以前、Aさんが親から相続した宅地を生前贈与しており、生命保険の受取人もBになっているため、B自身が「Aの死後もDがこれまでどおり面倒を見てくれるだろうし、これ以上は何も要らない」と言っていました。
このため、Aさんは、
「全ての財産を次男Dに相続させる」
という内容の遺言を書くことにしました。
しかし、ここで立ち止まって考えなければならないことがありました。
それは、長男C・長女Eからの遺留分侵害額請求のことです。
他の兄妹からの遺留分侵害額請求に備える
Aさんが「全ての財産を次男Dに相続させる」旨の遺言書を作成したとしても、奪うことができないのが長男C・長女Eの遺留分侵害額請求権です。
特に、3人の子ども達の仲が悪い本件では、必ずや、C・EがDに対して遺留分(各12分の1です)を請求してくるでしょう。
遺留分は、金銭で支払うのが原則です。
そこで、気を付けなければならないのが、全ての財産を相続することになるDに、C・Eに対して遺留分相当額を支払うだけの金銭的余力があるかどうかです。
本件では、トラクターの一部を最新のものに買い替えたタイミングでもあったため、遺産となる預貯金は350万円しかありませんでした。
そのため、遺産総額の12分の1の遺留分相当額を、しかも2名分、遺産である預貯金から賄うことは不可能という状況です。
D自身の蓄えもそれほど潤沢にあるわけではありません。
かといって、Aさんとしては、不動産を分散して、一部だけCやEに取らせることはしたくないとの考えでした。
生命保険金の活用

そこで、目を付けたのが3本ある生命保険(約3000万円)です。
生命保険は3本とも、死亡時の受取人が「妻B」に指定されていました。
このうちの一部の受取人を次男Dに変更しておけば、Dはその保険金を原資にして、長男C・長女Eに対して遺留分相当額を支払うことができるだろうと考えたのです。
もっとも、上記のように一部の受取人をDに変更することは、妻Bの不利益となります。
妻Bは、生前贈与された不動産とこれらの生命保険金があるため、Aさんの遺産からは何ももらうことを希望しないというスタンスですから、その前提が崩れれば、遺言で自分にも何か残して欲しいと希望するでしょう。
そこで、AさんはB・Cとよく話し合い、「CがこれまでどおりBの面倒を見てくれるなら、生命保険の一部の受取人をDにしてもよい」ということに落ち着きました。
Aさんの遺言作成
以上を踏まえて、Aさんは、
「Aの死後もDが遺産建物にBを同居させ、Bの生活にかかる水道光熱費をDが負担することを条件に、全ての財産をDに相続させる」
という内容の公正証書遺言を作成しました。
また、遺言書の付言事項として、
■先祖から受け継いだ農地に対するAさんの思いと、それらを含めた一切をDに引き継がせるに至った理由
■C・Eに対しては、なるべく遺留分侵害額請求はしないで欲しいこと
■Eに対しては、離婚後の生活援助として相当額を贈与してきたことから、もし、Eが遺留分侵害額請求をする場合は、これら特別受益の総額はきちんと差し引きすべきこと
を記載しました。
そして、C・Eからの遺留分侵害額請求に備えるため、3本の生命保険のうち2本の受取人をBからDに変更したのです。
農地経営者の相続対策で気を付けるべきこと

農地経営者の方が相続対策を考える場合、まず、「農地を誰に引き継がせるか」が出発点となります。
本件のように、相続人の中に農業に従事している人がいる場合はよいですが、昨今では、相続人の中に誰も農業を継ぐ人がいないというケースも見受けられます。
農地を相続によって取得する場合は農業委員会の許可は不要ですので、農業に全く従事していない相続人でも農地を相続することは可能です。しかし、実際問題として、その後、その相続人が農地を活用できなければ、農地は荒れ、耕作放棄地として近隣の迷惑になってしまうかもしれません。
そこで、生前に、近隣の農業従事者に譲渡する、転用の可能性を考えるなどの対策が必要になってきます。
また、農地と実家不動産その他一切を、実家を継いで農業をしている1人の相続人に全て相続させることにした場合には、他の相続人からの遺留分侵害額請求に対する対応策も講じておく必要があります。
特に、本件のように、子ども達が不仲である場合にはなおさらです。
この点、財産の構成として「不動産は沢山あるが、流動資産が少ない」というケースでは、生命保険金を上手く活用して、遺留分相当額の支払いの原資に充てさせる方法もあります。
農地経営者の方で相続対策に悩まれている方は、是非一度、専門家にご相談下さい。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






