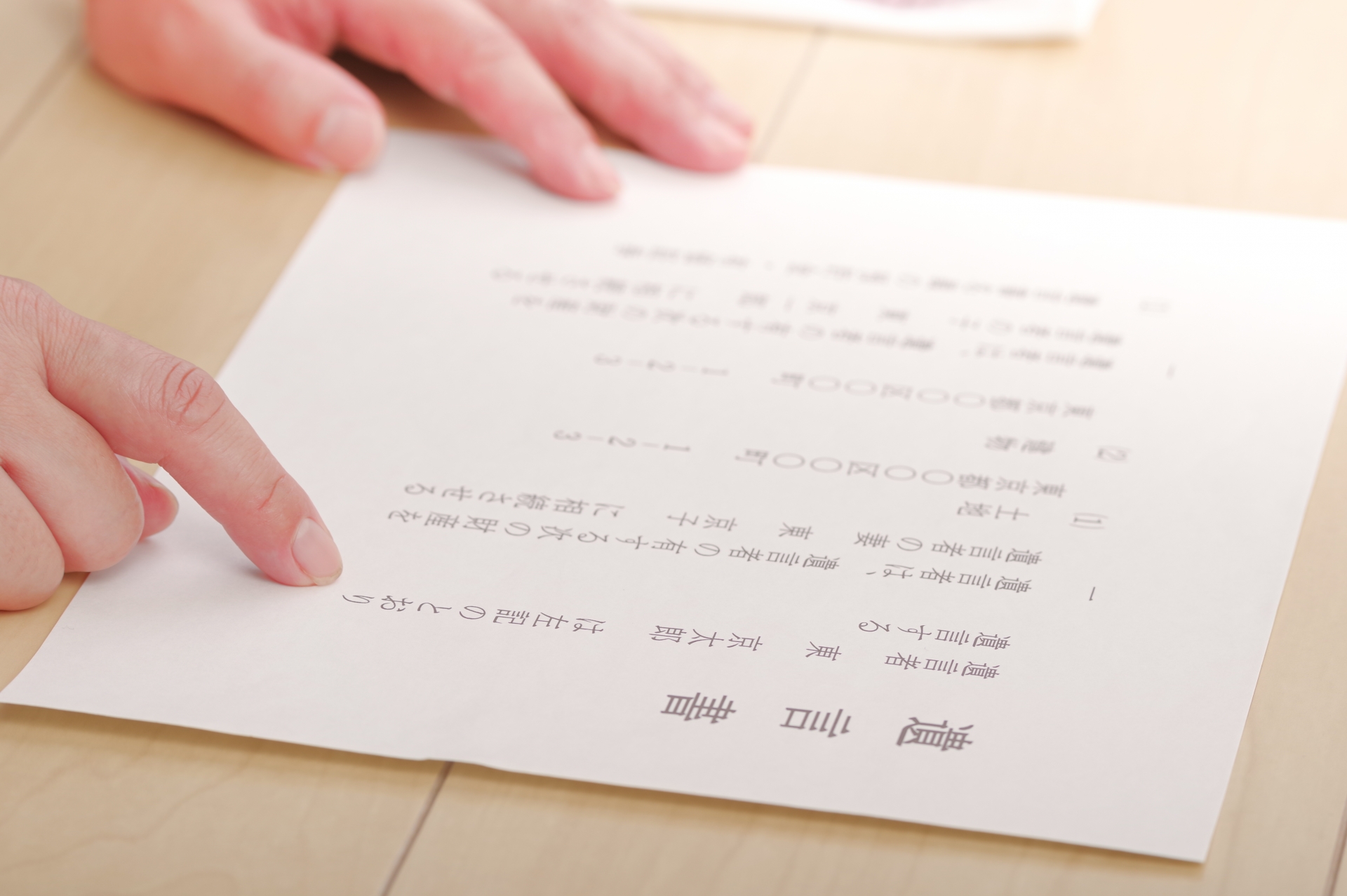
「遺言書を開いたら、特定の兄弟に不動産などの財産が集中し、自分の取り分はごくわずか…」故人の意思とはいえ、あまりに不公平な内容に、納得できないお気持ちを抱えていませんか?
しかし、その遺言書を前に呆然とする必要はありません。法律は、相続人に最低限保障された権利として「遺留分」を定めています。
当コラムでは、この「遺留分」を取り戻すための具体的な方法を、相続問題に精通した弁護士が徹底解説します。絶対に知っておくべき「1年」という時効の重要性から、最初の一歩である内容証明郵便の送り方、交渉、そして家庭裁判所での調停に至るまで、手続きの全ステップを詳述します。
さらに、実際に弁護士が介入し、不動産を売却せずに金銭で解決した事例なども交えながら、あなたの正当な権利を守るための知識を網羅的にお伝えします。泣き寝入りする前に、まずはこの記事で「何ができるのか」を知ることから始めましょう。
遺留分という強力な権利
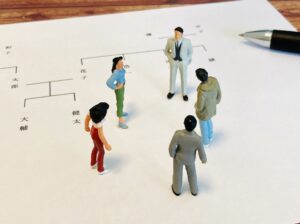
「父が亡くなり、遺言書を開いてみたら、事業用の収益ビルや土地など、価値のある財産はすべて長男である兄に相続させ、自分にはごくわずかな預貯金しか残されていなかった…」
遺言書は故人の最後の意思として尊重されるべきものです。
しかし、あまりにも偏った内容の遺言は、残された家族間に深刻な亀裂を生みかねません。法律は、そのような事態を避けるため、たとえ遺言であっても侵害することのできない、相続人の「最低限の取り分」を保障しています。
それが「遺留分」です。
今回は、この「遺留分」という強力な権利を使い、ご自身の正当な取り分をどう確保していくのか。具体的なケーススタディを元に、請求手続きの詳細、弁護士が介入することで実現できる解決策まで、一歩踏み込んで徹底的に解説します。
より具体的に解説!ケーススタディで見る遺留分計算

登場人物
被相続人(父): 収益ビル(時価2億円)と預貯金600万円の財産を残して逝去。
相続人: 長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんの3兄弟。
遺言書の内容: 「事業を手伝ってくれた長男Aに収益ビルと預貯金300万円を相続させる。次男Bと三男Cには、それぞれ預貯金150万円を相続させる」
この遺言内容では、Aさんが2億300万円を相続するのに対し、BさんとCさんはわずか150万円ずつ。あまりの不公平さに、BさんとCさんは途方に暮れています。
あなたの「遺留分」はいくら?具体的な計算方法
まず、BさんとCさんに法律上いくらの権利があるのかを計算してみましょう。
・遺産の総額を計算する
収益ビル2億円 + 預貯金600万円 = 2億600万円
・遺留分の割合を出す
遺留分の権利があるのは、配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属(父母など)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
今回のケースでは、相続人が子のみなので、全体の遺留分(総体的遺留分)は遺産総額の1/2です。
2億600万円×1/2=1億300万円
・個人の遺留分額を計算する
全体の遺留分を、法定相続分で掛け合わせます。兄弟3人の法定相続分はそれぞれ1/3なので、
1億300万円×1/3=約3,433万円
つまり、BさんとCさんには、それぞれ約3,433万円を受け取る最低限の権利(遺留分額)があります。
・侵害額を算出する
実際に遺言で受け取るのは150万円のみなので、
約3,433万円(遺留分額)−150万円(実際に相続する額)=約3,283万円
この約3,283万円が、BさんとCさんがAさんに対して「遺留分を侵害されているので支払ってください」と請求できる金額(遺留分侵害額)になります。
【STEP別】遺留分侵害額請求・完全マニュアル

権利があることが分かっても、行動しなければ実現しません。ここでは請求手続きの具体的なステップと注意点を詳しく見ていきましょう。
STEP1:請求の意思表示【配達証明付き内容証明郵便】
すべての始まりは「請求する」という意思表示です。後々のトラブルを避け、時効を中断させる「証拠」を残すために、必ず配達証明付き内容証明郵便を利用します。
なぜ内容証明郵便か?
いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるため、「そんな手紙は受け取っていない」という反論を封じることができます。
なぜ配達証明付きか?
相手に手紙が配達された日付を証明してくれるため、時効の起算点を明確にする上で極めて重要です。
この書面には、「被相続人〇〇の相続に関し、遺留分が侵害されているため、民法1046条1項に基づき遺留分侵害額請求権を行使します」といった文言を明確に記載します。
STEP2:当事者間での交渉
請求後は、具体的な支払い金額や方法について相手方と交渉します。ここでの最大の論点は、遺産の適正な評価、特に不動産の評価額です。
不動産評価の難しさ
不動産の価格には、固定資産税評価額、路線価、公示地価、そして実際の取引価格である実勢価格(時価)など複数の基準があります。請求する側は最も高くなる時価を、支払う側は最も安くなる固定資産税評価額などを主張しがちで、ここで交渉が頓挫するケースが非常に多いのです。
弁護士の役割
弁護士は、実勢価格の割り出しに適切なアドバイスを加え、場合により鑑定(費用が掛かります)などを踏まえて準備した資料をもとに、法的な根拠をもって相手方と交渉します。これにより、単なる言い争いではなく、論理的な交渉の土台を築くことができます。
STEP3:家庭裁判所での調停・訴訟
交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。
調停とは?
裁判官と民間の有識者からなる調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら、中立的な立場で話し合いによる解決を目指す手続きです。非公開で行われるため、プライバシーは守られます。
調停調書の効力とは?
調停で合意に至ると、「調停調書」という書面が作成されます。これには、確定判決と同じ非常に強い効力があり、もし相手が合意内容を守らない場合は、強制執行(給与や財産の差し押さえ)をすることも可能です。
訴訟へ
調停でも話がまとまらなければ、最終手段として訴訟(裁判)を提起し、裁判官に法的な判断を仰ぐことになります。
【超重要】請求権が消滅する「時効」というタイムリミット

何度でも強調しますが、遺留分侵害額請求には厳格な時効があります。
相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年
上記を知らなくても、相続開始から10年
「兄弟と揉めたくない」
「いつか話せば分かってくれるはず」
と先延ばしにしている間に、この「知ってから1年」という期間は驚くほど早く経過してしまいます。権利が消滅してから後悔しても手遅れです。納得できないと感じたら、迷わず行動を開始してください。
弁護士に依頼するからこそ実現できる多様な解決策

弁護士に依頼するメリットは、単に手続きを代行するだけではありません。依頼者の希望や相手方の状況に応じた、オーダーメイドの解決策を提示できる点にあります。
メリット1 精神的負担からの解放
身内との金銭交渉は精神的に大きな負担を伴います。弁護士が代理人として矢面に立つことで、依頼者は相手と直接対峙するストレスから解放され、冷静な判断を保つことができます。
メリット2 複雑な財産調査と評価
「遺言に書かれていない預金があるかもしれない」「生命保険金も考慮すべきでは?」といった疑問にも、弁護士は職務上の権限(弁護士会照会など)を用いて財産調査を行い、または調停における調査嘱託などを通じて財産調査を行い、可能な限り、隠れた遺産を見つけ出すサポートができます。
メリット3 柔軟な解決案の提示
【解決事例A:代償金での解決】
冒頭のケースでは、弁護士が介入し、Aさんがビルを売却せずに済むよう、ビルからの家賃収入を原資とした長期の分割払いで遺留分侵害額を支払うという和解案を提示。兄弟関係を維持したまま円満に調停を成立させました。
【解決事例B:不動産そのものでの解決】
別の事例では、財産を多く受け取った相続人に支払い能力がありませんでした。そこで、広大な土地の一部を分筆して遺留分権利者に譲渡する「代物弁済」という形で解決を図りました。金銭での支払いが難しい場合でも、このような現物での解決策を模索できます。
まとめ

その「不公平」を、諦める必要はありません
遺言書の内容は絶対ではありません。法律で認められた「遺留分」は、あなたの正当な権利です。しかし、その権利の上にあぐらをかいているだけでは、時効によってすべてが失われてしまう可能性があります。
「遺言の内容に納得できない」
「どう計算すればいいか分からない」
「兄弟と直接話したくない」
少しでもそう感じたら、手遅れになる前に、相続問題の経験豊富な弁護士にご相談ください。私たちは、あなたの権利を守り、最善の解決へと導くための法的知識と交渉の術を知っています。一人で悩まず、まずは専門家の扉を叩いてみてください。
最後に見ていただきたい相続サポートのこと
私たちは、開所以来35年以上、相続にお悩みの方に一貫して寄り添って参りました。
皆様が苦しい相続人間の紛争を忘れ日常を取り戻していただくために、法的な専門知識と経験を活かして、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。
当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。
お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。
私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






