
「事故を起こしてしまったけど、保険を使うべきなのだろうか?」
交通事故の物損事故に遭った際、誰もが一度は頭を悩ませるのがこの問題です。
特に、ご自身にも過失がある場合や、相手が無保険の場合など、悩ましい問題です。
車両保険を使えば、修理費や買替費用を補填してもらえますが、その一方で、翌年度からの保険料が増額するというデメリットがあります。
保険料の上昇額と、保険を使わずに自己負担する金額、どちらが「得」なのか。この判断を誤ると、長期的に見て大きな損をしてしまう可能性もあります。
本コラムでは、交通事故の物損事故における「車両保険の使用判断」に焦点を当てた解説を致します。
なぜ「車両保険を使うべきか」が問題になるのか?

交通事故の被害者になった場合、原則として相手の保険会社が損害額を全額賠償してくれます。しかし、自分にも過失がある場合、自分の過失分は自己負担となります。
例えば、過失割合が「相手90:自分10」の事故で、修理費が100万円だったとします。
この場合、相手の保険会社から90万円が支払われますが、残りの10万円は自分で負担しなければなりません。
この自己負担分をカバーするために使えるのが「車両保険」です。
車両保険は、自分の車の損害を補償してくれる保険であり、使い方によっては自己負担額をゼロにすることも可能です。
しかし、車両保険を使用すると、翌年度からの保険等級が下がります。一般的な自動車保険では、保険を使用すると「3等級ダウン」し、翌々年度まで「事故あり係数適用期間」が加算されます。これにより、保険料が大きく上がってしまうのです。
したがって、「車両保険を使って修理費を補填してもらうメリット」と「保険料が上がってしまうデメリット」を比較し、より得な方を選ぶ必要があります。
判断基準の鍵を握る3つの要素

最適な判断を下すためには、以下の3つの要素を正確に把握する必要があります。
過失割合
過失割合は、事故の責任を当事者間でどれくらいの割合で分担するかを示すものです。これが車両保険の使用判断において最も重要な要素となります。
過失割合が「自分0:相手100」の場合
この場合、あなたは完全に被害者であり、相手の保険会社が損害額を全額負担します。
自分の車両保険を使う必要は一切ありません。
もし相手が無保険であったり、示談交渉が難航したりする場合は、自分の車両保険を使って修理を行い、後から保険会社に相手への求償を任せる「無過失事故に関する特約」が付帯されていることもあります。この特約を使えば、等級はダウンしないことが一般的です。
過失割合が「自分10:相手90」や「自分50:相手50」の場合
自分の過失分を自己負担することになります。この自己負担分が、車両保険を使うかどうかの判断基準となります。
端的には、「保険料の増額分」と「自己負担すべき過失分の金額」のどちらが高いかで判断すべきと言えます。
過失割合が「自分100:相手0」の場合
単独事故や自損事故の場合、このような過失割合となります(もちろん、ご自身が追突をしてしまったなどの場合にも、このような過失割合となります)。
この場合、修理費用はすべて自己負担となります。この自己負担分を車両保険で補うことになります。
過失割合の決定
過失割合の決定は、事故現場の状況、警察の実況見分調書、ドライブレコーダーの映像などを基に、まずは保険会社同士で交渉が行われます。この交渉結果に納得がいかない場合は、弁護士に相談し、交渉を依頼することも可能です。
損害額(修理費用・買替費用)

車両保険の使用判断は、修理にかかる費用や、買い替える場合の費用と密接に関わっています。
損害額が小さい場合
例えば、修理費用が5万円程度であった場合、車両保険を使わず自費で修理した方が良いケースが多くなります。
保険料が1年間で2万円上がると仮定すると、3年間で6万円の負担増となります。自費で5万円を支払った方が、結果的に安く済むからです。
損害額が大きい場合
修理費用が100万円かかるような場合、自己負担額が10万円だったとしても、この10万円を車両保険で補填するメリットは大きいです。
保険料の増額分を考えても、手元から大きな金額が失われるのを防げます。
ただし、「全損」となった場合は注意が必要です。
全損とは、修理費用が車の時価額を上回る場合、または物理的に修理不可能な状態を指します。この場合、保険会社から支払われる保険金は、「事故時点での車の時価額」が上限となります。
時価額は、車の車種、年式、走行距離などを考慮して決定されますので、しっかりと確認をする必要があります。
保険等級ダウンと保険料の増額
車両保険を使うと、翌年度からの保険料が上がります。この「増額分」がいくらになるのかを具体的に試算することが、最も重要です。
等級ダウンの仕組み
一般的には、車両保険を使うと「3等級ダウン」します。
翌々年度まで「事故あり係数」が適用され、同じ等級であっても事故を起こしていない人と比べて保険料が高くなります。
保険料増額の試算例
・事故前の保険料:年間10万円
・等級ダウンによる保険料増額分:年間2万円
この場合ですと、保険料は3年間で約6万円増額します。
もし、この増額分が、自己負担額を上回るようであれば、車両保険を使わない方が良いということになります。
保険会社に連絡して、「車両保険を使った場合の、翌年度からの保険料を試算してください」と依頼すれば、具体的な金額を教えてもらえることが多いです。
具体的なシミュレーションと判断基準

ここからは、具体的なケースを想定し、車両保険を使うべきか否かを判断するシミュレーションを見ていきましょう。
シミュレーション1:軽微な接触事故(自己負担額が少ないケース)
・事故の状況:駐車場でバック中に相手の車に接触。
・過失割合:自分100:相手0(自損事故)
・損害額:自分の車のバンパーに擦り傷。修理費用は10万円。
・保険料:等級10等級、年間保険料10万円。車両保険を使わなければ、翌年度も10万円。
車両保険を使った場合
・10万円の修理費用が補填される。
・等級がダウンし、翌年度から保険料が年間約2万円増額する。
・3年間で保険料は合計約6万円増額する。
車両保険を使わなかった場合
・修理費用10万円は自己負担となる。
・等級は変わらず、保険料は年間10万円のまま。
【判断】
このケースでは、車両保険を使わなければ10万円の出費ですが、使った場合は3年間で6万円の保険料増額で済みます
修理費用が10万円、保険料の増額分が6万円なので、車両保険を使った方が4万円得をするという計算になります。
しかし、もし修理費用が5万円程度であった場合、保険を使わなければ5万円の出費、使った場合は6万円の増額となります。
この場合は、車両保険を使わない方が1万円得になります。
シミュレーション2:過失割合が自分にもあるケース
・事故の状況:交差点での出会い頭の事故。
・過失割合:自分30:相手70
・損害額:自分の車の修理費用は50万円。
・保険料:等級10等級、年間保険料10万円。
車両保険を使わなかった場合
・相手の保険会社から70%の35万円が支払われる。
・自分の過失分30%の15万円は自己負担となる。
車両保険を使った場合
・自分の車両保険で15万円の自己負担分を補填できる。
・等級が7等級にダウンし、翌年度から保険料が年間約2万円増額する。
・3年間で保険料は合計約6万円増額する。
【判断】
このケースでは、車両保険を使わなければ15万円の自己負担、使った場合は6万円の保険料増額で済みます。自己負担額15万円、保険料増額分6万円なので、車両保険を使った方が9万円得をするという計算になります。
ただし、修理費用がもっと少額だった場合はこの限りではありません。
例えば、修理費用が20万円で自己負担額が6万円だった場合、車両保険を使えば6万円の増額、使わなければ6万円の自己負担で、ほとんど差がありません。
このような場合は、保険を使わないという選択肢も有力になります。
判断をより複雑にする「代車費用」と「修理期間」

ここまで、修理費用と保険料の増額分を天秤にかけるシンプルな考え方を解説しましたが、実際の判断はもっと複雑です。
代車費用
事故で車が使えなくなった場合、修理が完了するまで代車が必要になることがあります。
相手に過失がある場合
相手の保険会社が代車費用を支払ってくれます。しかし、代車のクラスや期間には制限がある場合がほとんどです。
自分にも過失がある場合
代車費用も過失割合に応じて負担することになります。例えば、過失割合が「自分30:相手70」の場合、代車費用も30%は自己負担です。
車両保険の「代車費用特約」
御自身の車両保険に「代車費用特約」が付帯されている場合、この特約を使うことで、自己負担分の代車費用をカバーできる可能性があります。
ただし、この特約を使うと、やはり保険等級がダウンする可能性がありますので、注意が必要です。
修理期間
修理にかかる期間も、判断に影響を与えます。
修理に数週間から数ヶ月かかる場合、その間の代車費用は大きな金額になります。代車費用を考慮に入れると、車両保険を使うメリットが大きくなることもあります。
また、お仕事で車を使っている場合(営業車など)、修理期間中は業務に支障が出ます。
修理期間が長期化しそうな場合、早めに弁護士に相談し、修理業者との交渉や代車の手配を任せることも検討しましょう。
まとめ
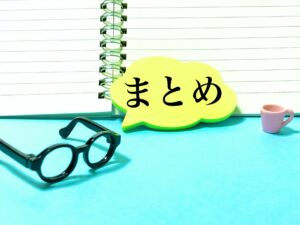
車両保険を使うべきか否かの判断は、「自己負担額」と「将来の保険料増額分」を比較することが基本となります。
しかし、その判断には、過失割合、損害額、代車費用など、複数の要素が複雑に絡み合います。
これらの情報を正確に把握し、最適な選択をするためには、専門的な知識が必要です。
特に、保険会社が提示する過失割合や損害額に納得がいかない場合、安易に示談に応じてしまうと、大きな損をしてしまう可能性があります。
このような状況に直面した際には、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
最近の保険では、弁護士費用特約が付帯されていることが多いです。弁護士費用特約があれば、弁護士を等級が下がることなく利用できることが一般的です。
つまり、デメリットなしで弁護士に依頼できます。
弁護士に依頼することで、過失割合の適正な判断、損害額の交渉、車両保険の使用判断まで、法的な視点から最適なアドバイスを提供できます。
「自分の車を守るため」そして「将来の金銭的な損失を防ぐため」に、弁護士に依頼することをぜひご検討ください。
物損事故は、一見するとシンプルな事故に見えるかもしれませんが、その裏には多くの法的問題や交渉の落とし穴が潜んでいます。
適正な賠償金を受け取るための交渉、煩雑な手続きや交渉からの解放、精神的負担の軽減、示談交渉の早期解決など様々なメリットがあります。
これらのメリットは、あなたが物損事故で最大限の利益を得るために、また精神的な安定を手に入れるために重要です。
「物損事故だから」と諦める前にまずは一度、交通事故問題に詳しい弁護士に相談してみてください。
物損事故に遭ってしまったら、一人で悩まず、弁護士という強い味方を頼ることをぜひ検討してみてください。あなたの人生を立て直すための一歩を、弁護士が全力でサポートします。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。












