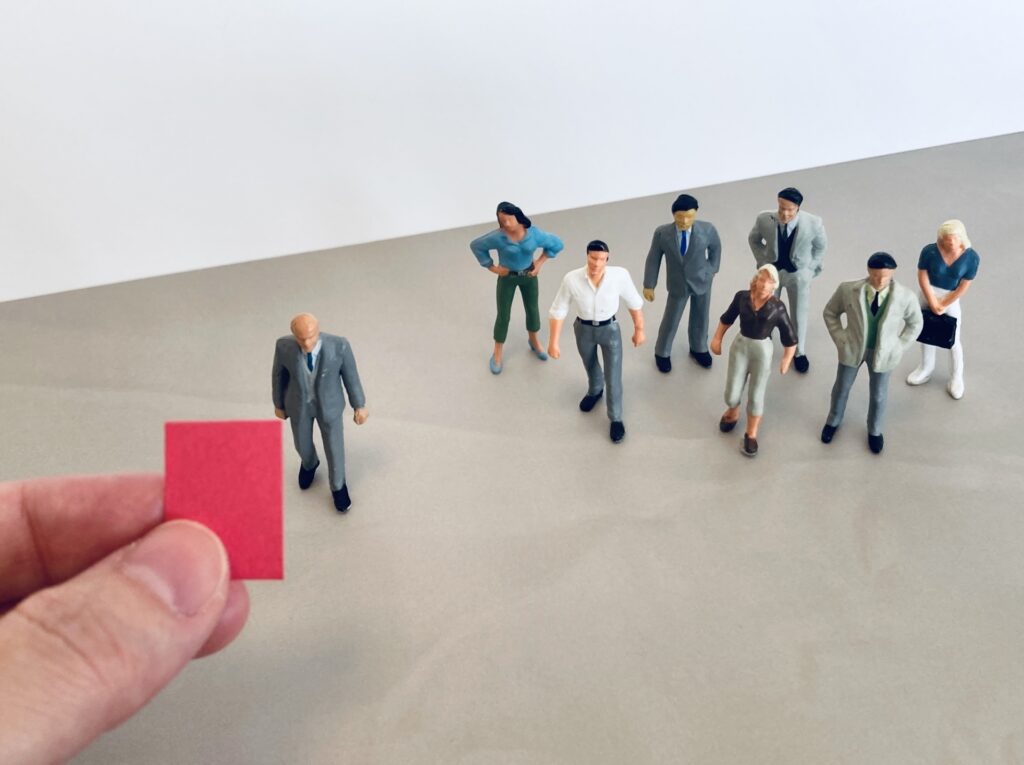
「退職を考えてはもらえないか」「あなたが会社を退職すると、会社の問題が解決する」といった、従業員に対して任意に退職することを求める行為(退職勧奨)を受けた場合、どのような対応をするべきなのかについて解説します。
退職勧奨とは

例えば、上司から「会社のために退職をしてはもらえないか」と持ち掛けられるような場合として、退職勧奨が挙げられます。
あくまで上司は、あなたを解雇(クビに)するのではなく、あなたと上司やあなたと会社の間で話し合ってあなたが自主的に退職するよう働きかけるような場合です。
このように、会社が雇用している従業員に対して自発的に退職をするように促す行為を「退職勧奨」といいます。解雇は従業員がどのように反応するかにかかわらず退職をさせるものであるのに対し、退職勧奨は自発的に退職させるものです。
そして、退職勧奨は、会社が従業員をやめさせる手段の一つとして用いられることがあります。
退職勧奨に簡単に応じるべきではない場合も

本コラムでは、退職勧奨への対応について解説しますが、最もお伝えしたい点は、退職勧奨に応じるか否かは慎重に検討すべき、という点にあります。
退職は従業員が応じれば効力が生じる
まず、会社と従業員の間の雇用契約は、会社(上司)と従業員の間で合意をすることによって解消することができます。すなわち、従業員が退職勧奨に応じれば(「では、退職します」などと上司に伝えてしまえば)、直ちに退職となってしまうこともあり得ます。
しばしばドラマなどで散見される「退職願」や事例書の交付等が想像されますが、退職の意思表示はその形式を問いません。退職をすると理解される口約束だけでも、法律上は退職に応じた(合意退職をした)と判断されてしまうこともあり得ます。
退職の条件が提示されて、それが非常に魅力的であれば従業員にとっても退職は良いものなのかもしれません。例えば、会社都合退職として退職をする場合には、退職勧奨に応じるメリットもあると考えられます。
一方で、「他の退職した従業員に話を聞くと自分より有利な条件で退職していた」「その場の勢いで応じてしまったが、退職をすべきでなかったと後悔した」といったこともあるかもしれません。
退職の意思表示の撤回・取消しは難しい
法律上、一度退職に応じる(一度退職の意思表示をする)と、その退職を不当解雇として争うことはできないと考えられています。そこで、一度なされた退職の意思表示を撤回・取消しによりなかったことにできないかが問題になります。
しかし、退職の意思表示の撤回や取消しが認められる場合は、非常に少ないとされています。
法律上、会社側が合意退職に応じる前に、従業員が退職の意思表示を撤回したと判断される場合や錯誤(民法95条に定められたもので、「勘違い」などをご想像ください。)による取消しの場合には退職をなかったことにする余地があるのですが、これを証拠によって証明することが困難と考えられるのです。
したがって、退職勧奨を受けた場合にこれに応じるか否かは、慎重に考えるべきなのです。
退職勧奨にはどのように対応するべきか

上でも述べたとおり、退職勧奨を受けてもこれに応じるか否かは慎重に検討する必要があります。また、これを拒む理由を明示する必要もありません。
退職をしないのであれば、明確に「退職はしない」と言えば足ります。
また、会社側に対して、退職勧奨の趣旨であるのか、解雇通知であるのかをはっきりさせるように求めることも考えられます。ただし、解雇通知が改めてなされれば、不当解雇として解雇の有効性などを争うべきことになります。
さらに、退職勧奨を受けてお困りであれば、弁護士へ相談することにより、より状況に即した合理的なアドバイスを受けられます。
退職勧奨は違法と判断される場合もある
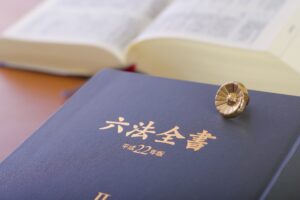
なお、会社がしつこい退職勧奨をする場合や、従業員への嫌がらせ等を併用しながら退職勧奨をする場合には、これらが違法と判断されることもあります。違法な退職勧奨に及んでいるのであれば、法的根拠に基づいて、それをやめるように求めることも得策です。
退職勧奨に関するルール
退職勧奨は、原則として、法律に違反するものではありません。もっとも、一定の場合には退職勧奨が違法になります。これについて先例として参考にされるのが、日本アイ・ビー・エム事件(東京地判H23.12.28)です。
日本アイ・ビー・エム事件判決
日本アイ・ビー・エム事件は、会社が、従業員に対して退職勧奨を行ってきたことに対し、従業員がその退職勧奨が違法である旨を主張した事件です。
同事件判決は、「労働者の自発的な退職意思を形成する・・・・・・ために社会通念上相当と認められる限度を超えて、当該等同社に対して不当な心理的圧力を加えたり、又は、その名誉感情を不当に害するような言辞を用いたりすることによって、その事由な退職意思の形成を妨げるに足りる不当な行為ないし言動をすることは許されず、そのようなことがされた退職勧奨行為は、もはや、その限度を超えた違法なものとして不法行為を構成する」旨を判示しました。
この判決は、原則として法律に違反することのない退職勧奨も、社会通念上相当と認められる限度を超えて従業員に①心理的圧迫を与えたり、②名誉を害するような言動をした場合、もはや退職勧奨は違法な行為になるという考え方の判決です。
本判決は、他の裁判例においてもしばしば引用される重要な先例となっています。
例えば、何度も長時間にわたり退職勧奨を行うこと、退職をさせるために下位車内で従業員に対する暴言・いじめをすること、「追い出し部屋」のような不当な配置転換をして自主退職を迫ることなどが、違法なものとされています。
まとめ

以上のように、退職勧奨に応じるか否かは、従業員の自由であり、かつ、退職勧奨に応じるか否かは慎重に検討する必要があります。
また、退職勧奨がしつこくなったり、不当に従業員を害する場合には、違法となることもあります。
退職勧奨を受けてお困りの場合には、弁護士への相談もご検討いただくのがよろしいものと考えます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






