
近年、個人・法人問わず、自動車の利用形態としてリースが普及しています。新車の購入と比較して初期費用を抑えられたり、メンテナンスの手間が軽減されたりといったメリットがある一方で、万が一、リース車両が交通事故に遭った場合の損害賠償請求については、複雑な法的問題が生じがちです。本コラムでは、リース車両の交通事故における損害賠償請求の法的構造と実務上のポイントについて、解説いたします。
リース契約の法的性質と種類
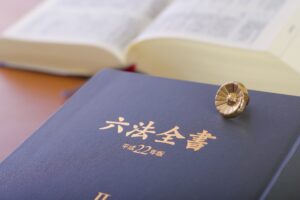
交通事故における損害賠償請求を理解するためには、まずリース契約の基本的な法的性質と種類を押さえる必要があります。リース契約は、リース会社(賃貸人)がユーザー(賃借人)の希望する物件を調達し、これをユーザーに一定期間賃貸し、その対価としてリース料を受け取る契約です。法的には「動産賃貸借」の一種と解されています。
リース契約は大きく分けて「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2種類に分類されます。
- ファイナンス・リース: この契約形態は、原則としてリース期間中の途中解約が不可能であり、かつリース期間中にリース物件の取得価額や資金コスト、税、保険料などの諸費用を含め、リース会社が投下した資金のほぼ全額(フルペイアウト)をリース料としてユーザーが負担します。経済的実態としては、ユーザーが分割払いで物を購入したのと同視できる性質を持つものです。
- オペレーティング・リース: ファイナンス・リース以外のリース契約を指します。オペレーティング・リースでは、リース期間終了後の残存価値が予め設定されており、リース料はこの残存価値を差し引いた金額に基づいて計算されます。 比較的短期間の契約が多く、リース期間終了後も所有権はリース会社に留まり、複数のユーザーに再リースされることを前提としているため、賃貸借に近い性格が強いとされます。
オペレーティング・リースでは、契約終了時に清算を行うか否かにより、オープンエンド方式とクローズドエンド方式に区分されます。
いずれのリース形態においても、自動車の損傷や滅失に関する危険負担は、多くの場合、リース契約の約款によりユーザー側が負うと定められています。
修理費用に関する損害賠償請求権の帰属

リース車両が交通事故によって損傷した場合、修理費用の損害賠償請求権が「誰に」帰属するのかが、実務上、最も問題となる点です。原則として、損害を受けた物件の所有者であるリース会社が損害賠償請求権を有すると考えられます。しかし、リース契約においてユーザーが修理義務を負うとされている場合、ユーザーが加害者に対して修理費用を請求できるかが争点となります。
特に、ユーザーがまだ修理費を工場等に支払っていない時点で加害者への修理費の損害賠償請求が認められるのかどうかです。
この点について、学説・判例では、ユーザーによる修理費用相当額の損害賠償請求を認める見解が有力です。特に、川原田寛裁判官の講演録(『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2017年下巻55頁』)では、その法理が詳細に示されています。
川原田裁判官は、リース契約では、多くの場合、ユーザーが契約上、車両の修理義務を負う旨が約款で定められていると指摘します。そして、車両が損傷し修理が必要な状態になった場合、「ユーザーが当該車両を修理しなければならない状態にある」ため、ユーザーに「修理費用相当額の具体的な損害」が生じていると解釈すべきであると述べています。
この立場に立つと、ユーザーが修理費用に関して加害者への損害賠償請求を行うためには、以下の点を主張・立証する必要があるとされます。
- 加害者の過失によって、ユーザーが使用するリース車両が損傷したこと。
- 当該車両のユーザーがリース契約の当事者であり、その契約約款において、ユーザーが車両の修理義務を負うと明記されていること。
- ユーザーが実際に当該車両を修理し、修理費用を負担した、あるいは将来的に修理費用を負担する予定があること。
修理未了の場合の請求可能性と大阪地裁の判断

特に重要なのが、ユーザーがまだ修理費用を支払っていない、あるいは修理が完了していない「修理未了」の場合でも、損害賠償請求が認められるかという点です。この点について大阪地方裁判所平成26年11月4日判決(平成26年(ワ)第3974号・平成25年(ワ)第9663号)は、この問題に対する重要な判断を示しました。
この事例では、ファイナンス・リースのユーザーが車両の修理費用を請求した事案であり、裁判所は以下の理由を挙げてユーザーの請求を認めました。
- リース契約上、車両の修理はユーザー(被告会社)が行う旨が定められており、リース会社自身が修理を行うことは想定されていなかったこと。
- ユーザーが既に一部の修理を行い費用を負担している部分があり、また未修理の部分についても将来的に修理を行う予定があること。
- 仮に修理が行われない場合、リース会社は、契約に基づき、車両を損傷した状態で返還されたことによる損害(例えば、使用価値の喪失など)をユーザーに対して請求することが考えられること。
- リース会社側から、加害者に対して直接修理費用を損害として請求するような動きが見られないこと。
これらの事情を総合的に考慮し、裁判所は、リース契約の「合理的解釈」として、ユーザーに修理費用相当額の損害賠償請求権を認めるのが相当であると判断したのです。
他方で、ユーザーがそもそも車両を修理する意思がない場合には、「具体的な損害」が発生しているとは言えず、修理費用相当額の損害賠償請求は認められない、という解釈になる可能性があります。
代車費用に関する請求権

リース車両が修理中の期間に代車を必要とした場合の代車費用については、その利用によってユーザーの利用権が侵害されたことによる損害であるため、ユーザーが加害者に対して請求できるとされています。
代車費用は、あくまで使用利益に対する補償であり、所有権とは直接結びつかないためです。
もし物損と同時にケガをしている場合

ケガをしている場合は、加害者に治療費を請求できますし、通院終了後に慰謝料も請求することができます。交通事故の慰謝料とは、被害者が交通事故によって受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償です。交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
入通院慰謝料は、入院期間や通院期間の長さによって決まりますし、後遺症慰謝料は、後遺障害の等級によって決まります。なお、死亡慰謝料は、被害者の属性や年齢などによって決まります。
慰謝料の金額は、保険会社と争いになることがほとんどです。
慰謝料は、通称「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準・財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)と言われる専門書に記載されている表が、基本的に基準として採用されています。
以下では、裁判基準の表を公開します(骨折等の場合)。

●表の見方
・入院のみの方は、「入院」欄の月に対応する金額(単位:万円)となります。
・通院のみの方は、「通院」欄の月に対応する金額となります。
・両方に該当する方は、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額となります。
(別表Ⅰの例)
①通院6か月のみ→116万円
②入院3ヶ月のみ→145万円
③通院6か月+入院3ヶ月→211万円
弁護士に依頼をすることによって、正しい慰謝料相場で保険会社と交渉したり、裁判の手続を代理で行うことができます。
まとめ

リース車両の交通事故における損害賠償請求は、リース契約の種類、約款の内容、車両の損害状況(分損か全損か)、ユーザーの修理意思など、多岐にわたる要素が複雑に絡み合います。特に、修理費用についてはユーザーによる請求が認められる可能性が高いものの、「具体的な損害」の認定には詳細な事実関係の立証が不可欠です。
もし、リース中の車両が交通事故に遭い、損害賠償請求に関してご不明な点やご不安な点がある場合は、ご相談ください。
もし弁護士特約に加入されていたら、弁護士費用の自己負担がなくなる可能性が高いです。
【弁護士費用特約】とは、ご自身が加入している、自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯している特約です。
弁護士費用特約が付いている場合は、交通事故についての保険会社との交渉や損害賠償のために弁護士を依頼する費用が、加入している保険会社から支払われるものです。
被害に遭われた方は、一度、ご自身が加入している各種保険を確認してみてください。わからない場合は、保険証券等にかかれている窓口に電話で聞いてみてください。
弁護士特約の費用は、通常300万円までです。多くのケースでは300万円の範囲内でおさまります。
物損だけではなく、骨折や重傷の場合は、一部超えることもありますが、弁護士費用特約の上限(通常は300万円)を超える報酬額となった場合は、越えた分を保険金からいただくということになります。
なお、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する場合、どの弁護士を選ぶかは、被害に遭われた方の自由です。
※ 保険会社によっては、保険会社の承認が必要な場合があります。
弁護士費用特約を使っても、等級は下がりません。弁護士費用特約を利用しても、等級が下がり、保険料が上がると言うことはありません。
弁護士費用特約は、過失割合10:0の時でも使えます。被害者に過失があっても利用できます。
まずは、ご自身やご家族の入られている保険に、「弁護士特約」がついているか確認してください。火災保険に付いている事もあります。
ご相談 ご質問
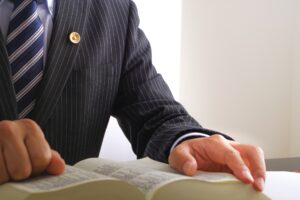
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
お悩みの方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。












