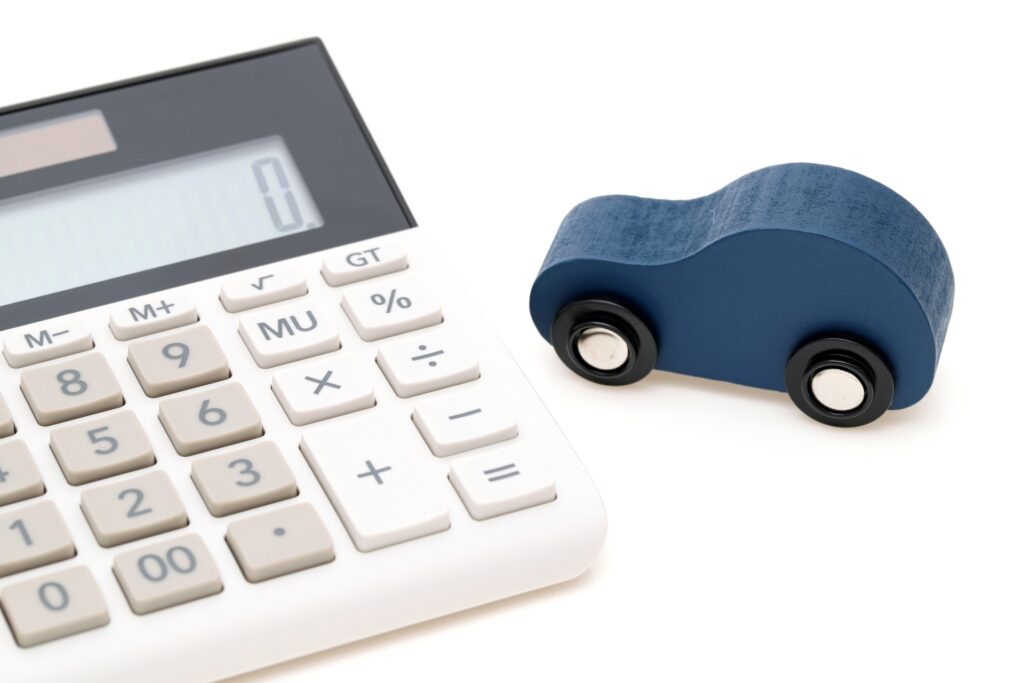
このページを見ている方は、交通事故に遭われ、大変な思いをされていることと存じます。治療を続けても、残念ながら身体に不調が残ってしまうことがあります。これが「後遺障害」です。
「後遺障害っていつ認定されるの?」
「保険金はいつ支払われるの?」
「手続きが複雑そうで不安…」
こうした疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、交通事故の数多くの案件を取り扱ってきた弁護士が、後遺障害の認定から保険金が支払われるまでの流れ、そして期間の目安について、分かりやすく解説します。
そもそも後遺障害とは?

治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。
症状固定と診断された時点で残ってしまった症状について、その内容や程度に応じて1級から14級の等級が認定されるのが「後遺障害」です。
1級が一番重く、14級が一番軽いということになっています。14級より下はないので、その場合は、非該当=後遺障害とは認定できないということもあり得ます。
等級が重いほど(数字が小さいほど)、支払われる保険金額も大きくなります。
後遺障害認定から保険金支払いまでのステップ

交通事故に遭ってから後遺障害が認定され、保険金が支払われるまでの大まかな流れは以下の通りです。各ステップを詳しく見ていきましょう。
【全体の流れ】
- 交通事故発生 ~ 治療開始
- 治療期間 ~ 症状固定
- 症状固定 ~ 後遺障害申請準備
- 後遺障害申請 ~ 認定・保険金支払い
- 認定後 ~ 示談交渉・解決
(1)交通事故発生 ~ 治療開始
最初にすること:
- 警察への通報、交通事故証明の取得、実況見分への立ち会い(人身事故として届出の場合)
- 保険会社への連絡
- 速やかな治療開始(救急搬送される場合もあります)
ポイント:
治療開始が遅れると、事故との因果関係を疑われる可能性があります。少しでも痛みや違和感があれば、すぐに医療機関を受診しましょう。また、接骨院や整骨院は、診断書を発行できないので、まずは病院を受診してください。その後、状況に応じて接骨院などに通うことになります。
初診の病院選び:
緊急搬送される場合はそこが初診です。その他の場合、まずは迅速に診察してもらえる医療機関を選びましょう。病院は理由があれば後から変更も可能です。
(2)治療期間 ~ 症状固定
病院選びの重要性:
症状に合った適切な治療を受けてください。あなたの症状に詳しい医師か、リハビリなど、希望する治療が受けられるか、仕事終わりに通院しやすい体制か等。
病院を途中で変更する場合:
事前に加害者の任意保険会社(治療費を立て替えている場合)に連絡しましょう。可能であれば、現在の病院から新しい病院への紹介状をもらうとスムーズです。
整骨院・接骨院の利用:
希望する場合は、まず通院中の医師に相談し、施術を受けても良いか確認しましょう。
整骨院・接骨院の施術は医師の指示があれば治療費として認められることが多いですが、医師の指示がない場合、後で治療費として争われる可能性があります。
「症状固定」とは?誰が決めるのか?

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと判断される状態です。
症状固定の時期は、客観的に決まるのが原則です。ただし、実際は、医師と患者がある程度話し合って決定しているのが現状です。
しかし、保険会社は、保険会社の判断で、治癒や症状固定の時期がきたという理由で、治療費の打ち切り(一括対応の終了)をすることがあります。しかし、これはあくまで保険会社の判断であって、それが直ちに症状固定を意味するわけではありません。
争いが長引いた場合、最終的には、裁判所の認定によって症状固定時期が決まるということにもなります(後見的に見て、症状固定日は、この日だったという認定)。
症状固定日までの治療費や入通院慰謝料が請求の対象となり、後遺障害の有無もこの時点の状態で判断されます。
(3)症状固定 ~ 後遺障害申請準備
後遺障害診断書の作成依頼:
症状固定後、医師に「後遺障害診断書」(自賠責保険提出用)を作成してもらいます。
注意点:
診断書の書式はご自身で用意し、病院に渡す必要があります。
医師が診断書の記載に不慣れな場合、自覚症状や検査結果、可動域制限などを正確に伝えて記載してもらうよう、補足説明が必要なこともあります。記載漏れや日付の間違いなどがないか確認しましょう。
また、自賠責保険はレントゲン、CT、MRIなどの画像所見を重視します。治療期間中に必要な画像検査を受けておくことが肝心です。
後遺障害申請には2つの方法があります。
①事前認定: 加害者の任意保険会社に手続きを任せる方法。
②被害者請求: ご自身(または代理人弁護士)で必要書類を集めて自賠責保険会社に直接請求する方法。被害者請求は、被害者側で提出書類をコントロールでき、認定されると保険金が直接振り込まれます。弁護士に依頼する場合、多くはこちらの方法を選択します。
(4)後遺障害申請 ~ 認定・保険金支払い

必要書類の取り寄せ:
後遺障害申請には、事故日から症状固定日までの全ての診断書やレセプト(診療報酬明細書)が必要です。弁護士に依頼した場合、これらの書類は加害者の任意保険会社から取り寄せることが多いです。
期間の目安:
症状固定月の診断書・レセプトが保険会社経由でそろうまで、症状固定日から1~2ヶ月かかることがあります。(例:2月1日症状固定の場合、書類がそろうのは3月下旬頃)
申請後の追加資料収集:
被害者請求を行うと、自賠責保険の調査事務所から、受付通知や追加資料(主に画像)の提出依頼が届くことがあります。画像取り付け費用は、一旦立て替えますが、後日自賠責保険から支払われます。
後遺障害認定までの期間:
通常: 申請から約3ヶ月程度(書類準備、画像取り付け期間を含む)。
頚椎捻挫(むちうち)など比較的軽傷な場合は2ヶ月程度の期間で認定されることが多いです。
重度・複雑な場合: 高次脳機能障害など専門部会での審査が必要な場合や、本部審査となる場合は、申請から認定までに4~6ヶ月、あるいはそれ以上かかることもあります。
認定結果の通知と保険金の支払い:
後遺障害等級(1~14級、または非該当)が認定されると、その理由が記載された書類が届きます。保険金の振込は、この認定結果の通知とほぼ同時期に、申請時に指定した口座に行われます。
例:「突然75万円が振り込まれた」という場合、14級の後遺障害が認定された可能性が高いと推測できます。(等級ごとの保険金額については後述します)
(5)認定後 ~ 示談交渉・解決
示談交渉の開始:
後遺障害等級が確定したら、それに基づいて加害者の任意保険会社と損害賠償全体の示談交渉を開始します。
ポイント:
弁護士が介入することで、「弁護士基準(裁判基準)」という最も有利な基準で賠償額を算定し、交渉を進めることができます。
後遺障害の認定結果に不服がある場合(異議申し立て):
「非該当」や認定された等級に納得がいかない場合、新たな医学的証拠などを添えて「異議申し立て」(再審査)を行うことができます。
再審査には平均3ヶ月程度かかり、一度出た認定を覆すのは容易ではありません。しかし、当事務所でも異議申し立てにより有利な結果を得たケースは多数あります。
示談成立または裁判等による解決:
示談交渉がまとまれば解決となります。
交渉が難航する場合は、交通事故紛争処理センターの利用や、裁判による解決を目指すこともあります。
解決までの期間:
事案の内容(ケガの程度、後遺障害等級、過失割合、保険会社の対応など)により大きく異なります。スムーズに進めば1ヶ月以内、争点が多い場合は6ヶ月以上かかることもあります。
交通事故により認められる後遺障害等級について
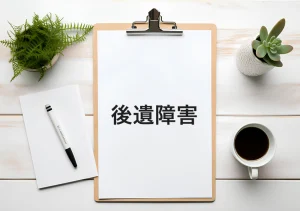
交通事故により後遺障害が生じる可能性があります。
後遺障害が認定されると、後遺障害等級によって、「後遺障害慰謝料」を請求できます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
保険会社は、大抵は、【自賠責基準】に近い金額で慰謝料額を提示してきますが、弁護士が入ることにより、正当な金額で交渉が可能です。正当な金額は、以下の表のとおりです。
| 後遺障害等級 | 裁判基準 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 | 100/100 |
| 第2級 | 2,370万円 | 100/100 |
| 第3級 | 1,990万円 | 100/100 |
| 第4級 | 1,670万円 | 92/100 |
| 第5級 | 1,400万円 | 79/100 |
| 第6級 | 1,180万円 | 67/100 |
| 第7級 | 1,000万円 | 56/100 |
| 第8級 | 830万円 | 45/100 |
| 第9級 | 690万円 | 35/100 |
| 第10級 | 550万円 | 27/100 |
| 第11級 | 420万円 | 20/100 |
| 第12級 | 290万円 | 14/100 |
| 第13級 | 180万円 | 9/100 |
| 第14級 | 110万円 | 5/100 |
例えば、表の通り、12級に該当した場合は、290万円が正しい相場です。
1級だと2800万円にもなります。等級が高い方が慰謝料額が増加します。
交通事故による後遺障害で請求出来る金銭について

後遺障害慰謝料の他に、交通事故によるケガで、後遺症が残った場合に受け取れる賠償金には、以下のような項目の金銭があります。
- 治療費:治療にかかった費用
- 休業補償:仕事を休んだ場合に支払われる費用(主婦も含む)
- 交通費:通院にかかった費用
- 入院雑費:入院したときにかかる諸費用
- 入通院慰謝料:通院や入院による精神的慰謝料
- 逸失利益:事故に遭わなければ今後得られるはずだった収入の補償
これらを漏れなく計算して、その合計が、賠償金となります。
治療関係費
治療費や入院費は、「必要かつ相当」な範囲で実費が認められるとされています。したがって、特殊な治療をうけても、「相当では無い」と判断されることもあります。
症状固定の後の治療費は、原則として認められません。もっとも、症状の内容・程度に照らして必要かつ相当なものは認めた例があります。
入院中の特別室使用料(個室ベッド)は、医師の指示があった場合や、症状が重篤であった場合、空室がなかった場合等の特別な事情がある場合にかぎり、認められる余地があります。
整骨院・接骨院の施術費用は、医師の指示の有無が重要で、それを参考にして、相当額のみ認められます。針灸、マッサージ、温泉治療も同様です。
入院雑費
1日あたり1500円の額を基準とします。
交通費

入退院や通院の交通費は実費となります。ただし、タクシーの場合は、ケガの程度によります。自家用車利用の場合は、1kmあたり15円でガソリン代を認めます。
※近年、ガソリン代が高騰化していますが、実務では、1km15円で変る気配はありません。
装具・器具等購入費
装具・器具等の購入費用については、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で認められます。
車椅子・義手・義足・電動ベッド・歩行具、車いす、サポーター等がよくあてはまります。
一定期間で交換が必要なものは、将来の費用も加算されます。
※将来の装具・器具購入費用は、取得額相当額を基準に、使用開始の時及び交換時期に対応して、中間利息を控除する。
入通院慰謝料
ケガで入院・通院をしたら「入通院慰謝料」をもらうことができます。
後遺障害が残った時の、「後遺障害慰謝料」とは別で請求できます。
「慰謝料はいくらもらえるのか?」「慰謝料の相場はいくらか?」「保険会社から提示された慰謝料は正しいのか?」と疑問を持つ方も多いかと思います。
色々な基準がありますが、まずは、以下の表が、「正しい相場」になります。
慰謝料は、通称「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準・財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)と言われる専門書に記載されている表が、基本的に基準として採用されています。
骨折を伴う重傷の場合は、別表Ⅰをみます。
むちうちや捻挫のみの場合は、別表Ⅱをみます。


●表の見方
・入院のみの方は、「入院」欄の月に対応する金額(単位:万円)となります。
・通院のみの方は、「通院」欄の月に対応する金額となります。
・両方に該当する方は、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額となります。
(別表Ⅱの例)
①通院6か月のみ→89万円
②入院3ヶ月のみ→92万円
③通院6か月+入院3ヶ月→148万円
逸失利益
逸失利益とは、具体的には、交通事故がなかったとしたら、本来得られるはずだった利益のことをいいます。得べかりし利益ともいいます。
逸失利益としては、「死亡による逸失利益」と「後遺障害による逸失利益」があります。
「死亡による逸失利益」は、被害者の方が生存していれば得ることのできた収入をいい、この損害を賠償することを請求することで本来得られたであろう利益を補填します。
対して、「後遺障害による逸失利益」は、事故によって体に痛みが生じたり、関節が動かしにくくなる(可動域制限)などの後遺障害が残ってしまったことで、労働能力が低下し、将来の収入の減少が予想される場合の減収に対する補填をいいます。
後遺障害による逸失利益の計算は、下記の計算式で求められます。
一年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
こちらで詳しく解説しています。
交通事故による大腿骨骨折について弁護士に依頼するメリット

後遺障害が残ると保険金額が大きくなるので保険会社と争いになることがほとんどです。
特に、慰謝料や逸失利益は金額が大きくなります。
弁護士に依頼するのとしないのでは、数十万~事案によって数千万円の違いがでる可能性もあります(実際に当事務所でありました)。
弁護士に依頼をすることによって、保険会社との交渉や手続、裁判を代理で行うことができます。
また、弁護士特約に加入されている場合は、弁護士費用が原則として300万円まで保険ででます。
弁護士特約に加入している場合は、法律相談費用も特約ででますので、まずは相談ください。
ラインでの相談も行っています。友達登録して、お気軽にお問い合わせください。
弁護士特約については、こちらをご覧ください。
ご相談 ご質問

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
入院中でお悩みの方や、被害者のご家族の方に適切なアドバイスもできるかと存じますので、まずは、一度お気軽にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。












