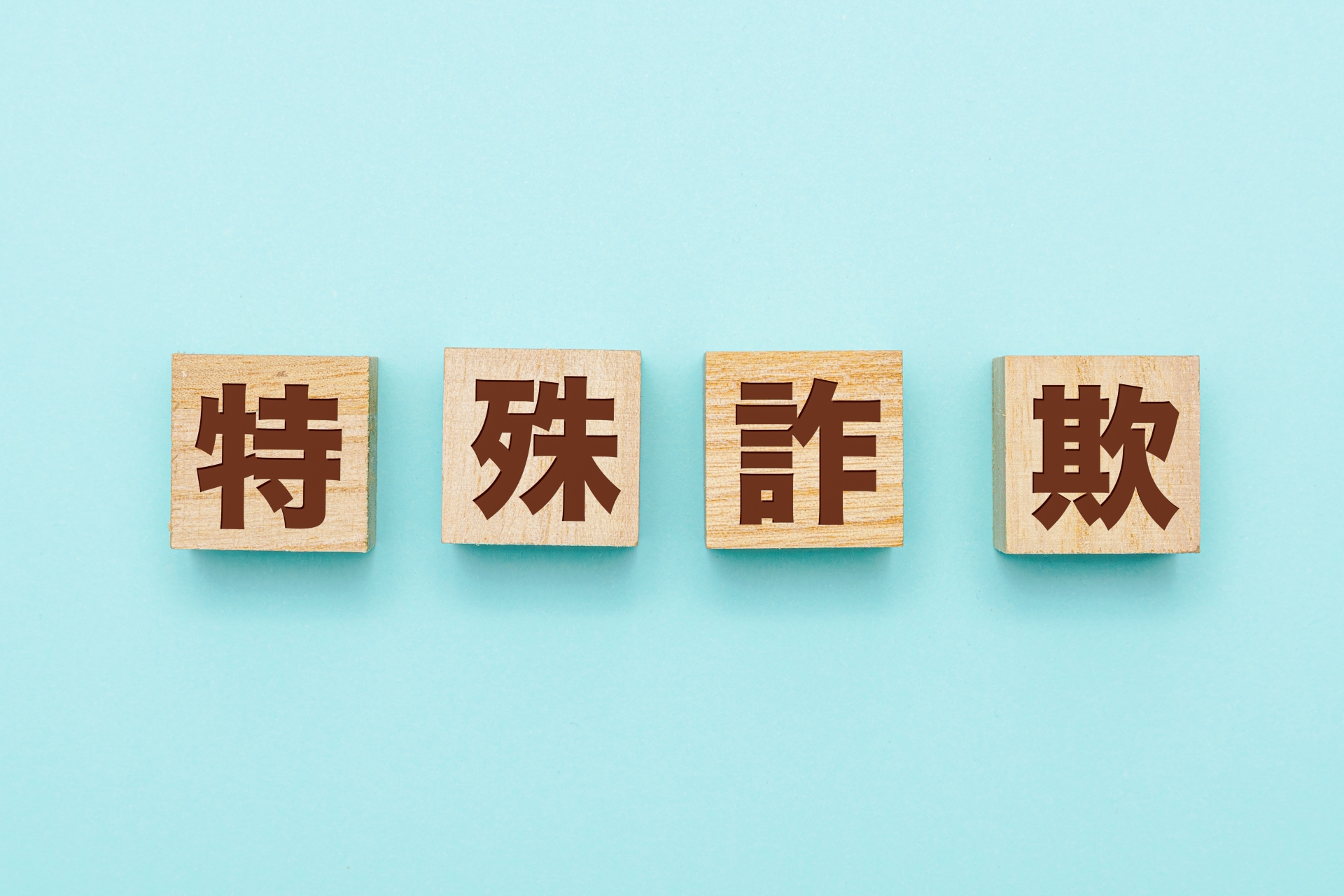
特殊詐欺事件において、直接被害者と接する「受け子」や、ATMから現金を奪取する「出し子」は、組織の末端でありながら最も逮捕のリスクが高いポジションです。
逮捕された被疑者の多くは、「高額バイトだと思った」「違法な仕事とは知らなかった」と主張しますが、実務上、この「故意(認識)」の有無を巡る争いは、被疑者にとって極めて過酷なものとなります。
裁判所は、客観的な状況証拠から「未必の故意」を広く認める傾向にあり、初犯であっても実刑判決が下されるケースが少なくありません。
本コラムでは、特殊詐欺における立証の構造と、実行役が直面する法的な現実について、実務的な観点から埼玉県大宮の弁護士が解説します。
特殊詐欺における「故意」の認定と未必の故意

特殊詐欺の実行役として起訴された際、最大の争点となるのが「詐欺の認識(故意)」です。日本の刑法では、明確に「詐欺である」と確信していなくても、自分の行為が犯罪に加担している可能性を認識しつつ、それを容認して行為に及んだ場合には「未必の故意」が認められます。
実務上、裁判所は以下の客観的事実から故意を推認します。
第一に、仕事の内容に比して報酬が著しく高額である点です。
第二に、秘匿性の高い通信アプリ(テレグラム等)の使用や、指示役からの不自然な指示(スーツの着用、偽名の使用、頻繁な移動など)です。
第三に、荷物の受け取りや現金引き出しの際に行う不自然な警戒行動です。これらの状況が揃っている場合、「何らかの犯罪であることは分かっていたはずだ」と判断され、知らなかったという弁解は法的に退けられる可能性が高くなります。
組織犯罪処罰法の適用と重い刑罰の現実
特殊詐欺は、多くの場合「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)」の適用対象となります。単なる刑法の詐欺罪よりも法定刑が重く設定されており、組織的に行われた詐欺の実行役には、非常に厳しい刑罰が科されます。
かつては「末端の使い捨ての駒」として情状が考慮される余地もありましたが、現在は社会的な被害の甚大さを背景に、たとえ初犯で利得が少額であっても、原則として実刑判決(刑務所への収容)が検討される運用となっています。
特に、被害者が高齢者であり、老後の資金を根こそぎ奪うような悪質な事案では、裁判所の姿勢は一層厳格になります。執行猶予を勝ち取るためには、単なる反省を超えた、極めて強力な情状立証が必要となります。
逮捕直後の接見と「供述の整合性」への対応

特殊詐欺で逮捕された直後、警察は「上部組織(指示役)」の特定を急ぐため、連日厳しい取調べを行います。被疑者は「組織の報復が怖い」あるいは「自分も騙された被害者だ」という思いから、事実と異なる供述をしたり、黙秘を選択したりすることがあります。
しかし、初期段階での不自然な供述や、客観的証拠(スマートフォンの解析結果など)と矛盾する弁解は、後に「反省の情がない」と判断される決定的な要因となります。
弁護士は、逮捕直後の接見において、本人が置かれている法的な立場を正確に伝え、どの範囲で事実を認めるべきか、あるいは沈黙を守るべきかを精査します。
組織の実態を正直に話すことが、後の「捜査への協力」として情状評価に繋がる可能性もあり、その判断は極めて慎重に行われなければなりません。
スマートフォンの解析(フォレンジック)と客観的証拠
現代の特殊詐欺捜査において、最も重要な証拠は被疑者のスマートフォンです。削除されたメッセージや通話履歴であっても、デジタルフォレンジック技術によって復元されることが多く、そこには指示役との生々しいやり取りが残されています。
「中身を知らずに運んだだけだ」という主張に対し、メッセージ内で「警察に気をつけろ」「回収したら即座に移動しろ」といった指示があれば、故意を否定することは不可能になります。
逆に、本当に何も知らされていなかったことを裏付けるやり取りが発見されれば、無罪や処罰軽減の大きな根拠となります。
弁護士は、押収された端末の解析結果を精査し、検察官が提示する証拠の解釈に誤りがないかを法的にチェックします。
特殊詐欺における示談交渉の困難さと重要性

実行役の弁護において、実刑を回避するための最大の鍵は「被害者への被害弁償と示談」です。しかし、特殊詐欺の被害者は、組織全体による多額の被害を受けており、末端の一人が自分の取り分(数万円程度)を返金したところで、示談に応じてもらえるケースは稀です。
実務上、示談を成立させるためには、本人の利得に関わらず、その被害者が失った「被害全額」を賠償することが求められる傾向にあります。実行役の家族が多額の資金を工面し、被害者に対して真摯に謝罪と賠償を行うことで、ようやく執行猶予の可能性が見えてきます。
被害者が複数いる場合、どの被害者に対して優先的に賠償を行うかといった優先順位の判断も、弁護活動の重要な戦略となります。
「受け子」から「出し子」への役割変化と重罪化のリスク
被疑者の中には、最初は「荷物を受け取るだけ(受け子)」と言われて参加したものの、途中で「現金を引き出してこい(出し子)」と指示が変わるケースがあります。
この際、ATMで他人のキャッシュカードを使用して現金を引き出す行為は、詐欺罪とは別に「窃盗罪」が成立します。
複数の罪が成立することで、刑期は加算(併合罪)され、より重い刑罰の対象となります。「断れなかった」という主張は、組織の脅迫的な背景がある場合には一定の考慮要素となりますが、自らの意思で継続したとみなされれば、犯罪への深い関与として厳しく評価されます。
弁護士は、役割が変更された経緯や、当時の心理的強制状態を詳細に分析し、過剰な責任を負わされないよう主張を展開します。
自首と捜査協力による刑の減免の可能性

特殊詐欺に加担してしまったことに気付き、警察に検挙される前に自ら出頭する「自首」は、極めて有効な防御策です。
また、逮捕後であっても、指示役の連絡先や組織の拠点を特定するための情報を提供する「捜査協力」を行うことで、検察官の求刑や裁判所の判決において、大幅な減軽が検討されることがあります。
ただし、捜査協力は本人や家族に対する組織からの報復リスクを伴うため、慎重な判断が必要です。弁護士は警察や検察と交渉し、安全を確保した上での協力を模索します。単に罪を認めるだけでなく、組織の壊滅に寄与する姿勢を見せることは、実刑を回避するための数少ない、しかし強力な手段の一つとなります。
家族による監督体制と「環境調整」の立証
実行役の多くは、経済的困窮や交友関係の悪化を背景に、SNSの「闇バイト」募集に手を出してしまいます。裁判所に対して更生の可能性を信じさせるためには、二度とこのような犯罪に加担しないための「環境の激変」を証明しなければなりません。
具体的には、親族が同居して24時間の監督を誓約すること、不適切な交友関係を完全に遮断すること、そして何より、安定した就労先を確保することが重要です。弁護士は、家族との面談を重ね、単なる「厳しく見守ります」という抽象的な言葉ではなく、スマートフォンの使用制限や定期的な報告義務など、具体的な監督プランを裁判所に提示します。この「更生への基盤」が整っていることが、執行猶予判決を得るための必要条件となります。
公判での「情状立証」と被告人質問の戦略

公判において、実行役の被告人が語るべきは「安易な考えで犯罪に手を染めてしまったことへの深い後悔」と「被害者の苦しみへの想像力」です。「自分も騙された」という被害者意識を強調しすぎると、かえって「事態を過小評価している」とみなされ、厳しい判決を招くことになります。
弁護士は被告人質問において、なぜそのバイトに応募してしまったのか、どの時点で「おかしい」と思ったのか、なぜその時にやめられなかったのか、という心理的プロセスを丁寧に引き出します。その弱さを認めた上で、現在はどのように自身の考えを改めているかを論理的に説明させることが、裁判官の心証を動かすことに繋がります。
特殊詐欺加担後の社会的更生と責任の継続
刑事裁判が終わった後も、実行役には重い責任が残ります。被害者から民事訴訟を提起され、多額の損害賠償義務を負うことは避けられません。また、一度特殊詐欺に関わったという記録は、その後の就職活動においても大きな障壁となります。
しかし、弁護士は判決を得て終わりとするのではなく、本人が真の意味で社会復帰できるよう、負債の整理や就労支援の窓口への橋渡しを行います。特殊詐欺の実行役という「使い捨て」の立場から脱却し、自分の足で人生を再建する意思を、手続全体を通じて育んでいくことが、真の弁護活動の目的です。
特殊詐欺実行役の弁護における「現実」と「希望」

特殊詐欺の実行役に対する刑事弁護を淡々と総括するならば、それは「厳しい司法の壁」に挑むプロセスです。「知らなかった」という弁解が通用する場面は極めて限定的であり、多くの場合、重い実刑の危機にさらされます。
しかし、事実を真摯に認め、可能な限りの被害弁償を尽くし、組織の全容解明に協力する姿勢を示すことで、最悪の結果を回避できる道はゼロではありません。
当事務所は、特殊詐欺事件の特殊な立証構造を熟知し、被疑者が置かれた複雑な事情を法的に整理することで、適正な処罰の範囲に留め、更生への一歩を踏み出すための論理的かつ粘り強い弁護活動を提供いたします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






