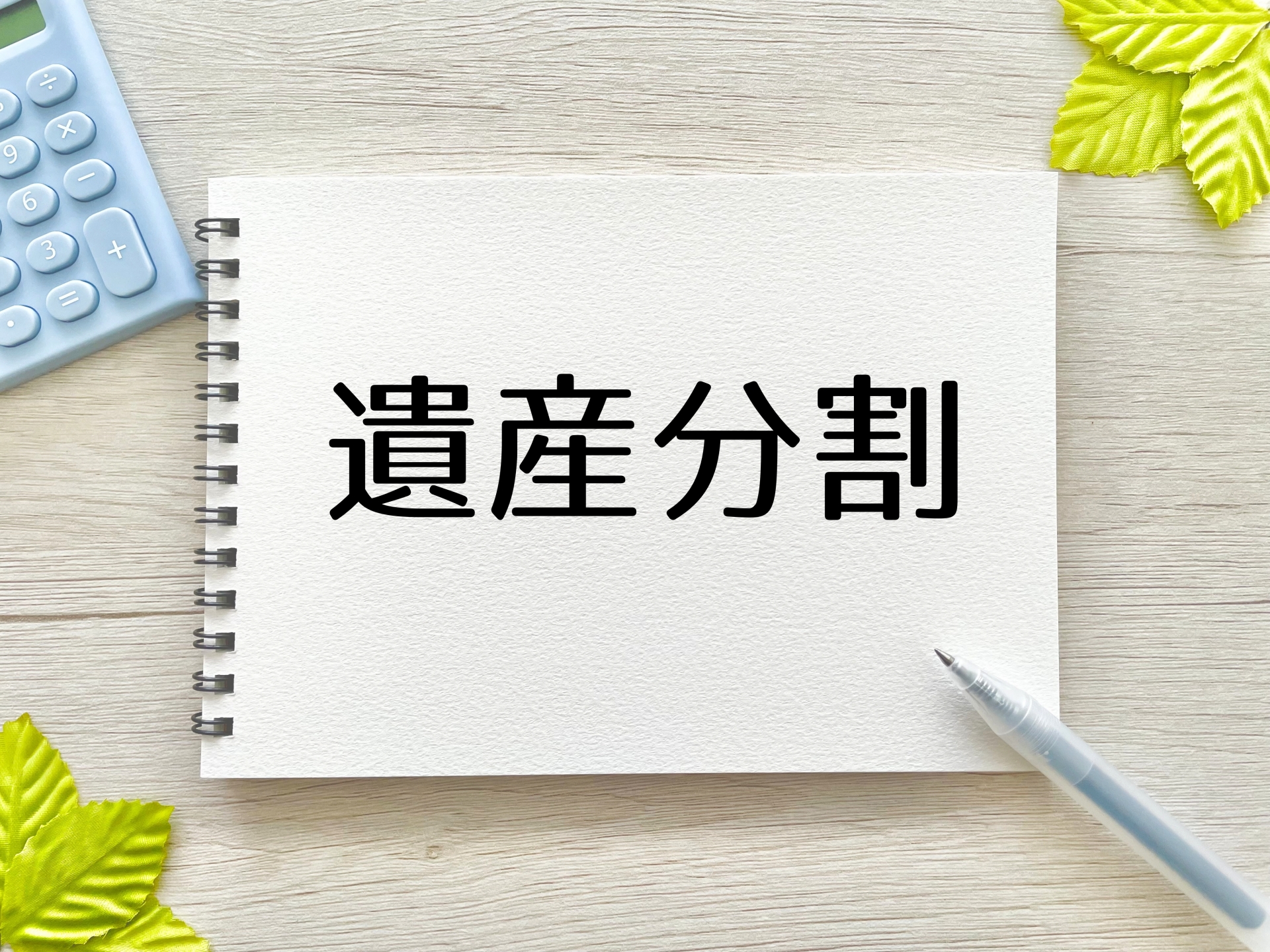
今回は、さいたま市大宮区で開設以来30年以上様々な法律相談を取り扱ってきたグリーンリーフ法律事務所が、相続で問題になる、遺産の分割方法についてコメントします。
相続とは

そもそも相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産上の地位を相続人が引き継ぐことをいいます。
相続人は民法で定められており、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人のうち、第1順位は子(およびその代襲者)、第2順位は父母(直系尊属=祖父母など)、第3順位は兄弟姉妹(およびその代襲者・ただし、この場合の代襲相続は1代=甥姪まで)となっています。
次順位の人が相続人になるのは、先順位の相続人がいない場合や相続放棄がなされた場合です。
現在の法律では、遺言がない限りは配偶者・血族が相続人となり、被相続人の遺産を引き継ぐことになります。
相続は、被相続人の死亡時から自動的に開始されます。
この相続において、どのように遺産を分けるかが遺産分割であり、その分割方法が問題となります。
遺産の分割方法

1.現物分割(げんぶつぶんかつ)
これは、遺産それ自体(現物)を、相続人間で分ける方法です。
例えば、長女が自宅の土地建物を、長男が預金を、長女が車を相続する、等の分け方です。
この方法は、シンプルで分かりやすく、売却などをせずに済むため手間が少ないというメリットがある反面、各財産の価値が異なるため公平に分けにくい、不動産が多く現預金が少ない場合などは偏りが生じやすい、というデメリットがあります。
2.代償分割(だいしょうぶんかつ)
これは、ある特定の相続人(一人とは限りません。複数でも可)が遺産を現物で相続し、他の相続人に対して金銭などを支払い、公平な分配を実現する方法です。
例えば、配偶者が自宅の不動産を相続する代わりに、長男と長女に500万円を支払う、というようなやり方です。
この方法は、現物の形を保ちながら公平な分割ができる、不動産を売らずに済む場合が多い、財産の散逸を防げる、等のメリットがあります。
他方、代償金を支払う側に資金力が必要、代償金額の算定根拠となる不動産の評価をめぐってトラブルになりやすい、不動産の評価額が高くその他の資産がない場合にはこの方法は採用しづらい、というデメリットがあります。
3.換価分割(かんかぶんかつ)
これは、遺産(不動産・株・車など)を売却して現金化し、その現金化したお金を相続人間に分配する方法です。
この方法は、公平に分けやすい、金銭で分けるため後の共有問題が生じにくいというメリットがある反面、売却手続きに手間と費用がかかる、財産を維持できずに手放さざるを得ない、市場価格が低下していると損をする場合もある、等のデメリットがあります。
4.共有分割(きょうゆうぶんかつ)
これは、遺産を複数の相続人が共有の形で相続する方法です。
例えば、ニュータウンの戸建て(土地建物)を、配偶者が1/2、長女・長男がそれぞれ1/4の法定相続分で共有(の登記)するという方法です。
この方法は、売却や代償金の準備をしなくても済むというメリットがある反面、将来、利用・管理・処分方針で意見が割れる可能性があることや、次の代で意見対立が発生するなど、暫定的な解決の側面があることは否めません。
いずれ共有を解消する手続き(再分割や売却など)が必要になることが考えられます。
遺産の分割方法の紛争に備えてグリーンリーフ法律事務所ができること

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴
開設以来、数多くの相続案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所では、遺産の分割方法多くの知見を有している他、経験に基づいて解決の見通しを立てることが可能です。
遺産の分割方法へのお悩みに、自信を持って対応できます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






