
親の遺言によって、法律上認められていたはずの分よりも少ない財産の相続を余儀なくされることがあります。このような場合、最低限これだけはもらえるという遺留分と言う権利がありますので、本日は事例を紹介しながら解説いたします。
1. 相談内容

埼玉県在住のAさん(50代・会社員)は、父親の遺言書をめぐって弟Bさん(40代・自営業)とトラブルになっています。
Aさんの父・Xさんは、2023年に他界しました。遺言書には次のように記されていました。
「長男Aには自宅の仏壇と父の思い出の品を相続させる。
それ以外の財産(預貯金・不動産・株式)はすべて次男Bに相続させる。」
財産の総額はおよそ6,000万円。Aさんには実質的な金銭的相続はありませんでした。
父は生前、経営に行き詰まっていたBを何度も援助しており、最期の遺言でも「Bの生活を守りたい」と語っていたといいます。
しかし、Aさんは納得できません。
「兄として父を支えてきたのに、なぜ何ももらえないのか。法律的に取り戻せる方法はないのか」と相談に訪れました。
2. 弁護士の見解 ― 遺留分侵害額請求の可能性
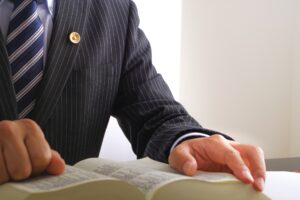
Aさんのケースでは、「遺留分」 という制度が重要になります。
遺留分とは、相続人の生活の安定や公平を守るため、一定の割合を法律上確保する権利です。
簡単に言えば、「どんなに偏った遺言があっても、最低限これだけはもらえる」という保障のことです。
遺留分の割合
民法1042条によれば、遺留分は次のように定められています:
直系尊属のみが相続人の場合 → 相続財産の 1/3
それ以外(配偶者・子などがいる場合) → 相続財産の 1/2
今回、相続人はA(長男)とB(次男)の二人の子です。
したがって、相続財産6,000万円のうち、遺留分の全体は 3,000万円(1/2)。
さらに、AとBで法定相続分が1/2ずつですから、Aの遺留分はその半分、つまり 1,500万円 となります。
Aは父の遺言によって財産を一切もらっていないため、
Bに対して1,500万円の「遺留分侵害額請求」 を行うことが可能です。
3. 遺留分侵害額請求の手続きと注意点

(1)請求方法
2020年の民法改正により、遺留分の権利は「物の返還」ではなく、「金銭による支払い請求」に変わりました(民法1046条)。
したがって、Aは「遺留分相当額1,500万円を支払ってほしい」とBに請求します。
請求は、まず内容証明郵便で正式に意思を伝えるのが一般的です。
それでも支払いがなければ、家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停を申し立てることになります。
(2)期限
注意すべきは、遺留分侵害額請求には期間制限がある点です。
民法1048条によると:
相続開始および遺留分侵害を知ったときから 1年以内
または、相続開始から 10年以内
この期間を過ぎると、権利は消滅します。
したがって、Aさんのように「気持ちの整理がつかないまま放置してしまう」と、取り戻せなくなる危険があります。
4. 感情の対立と調停の現場

Aさんが家庭裁判所で遺留分調停を申し立てたところ、Bは強く反発しました。
「父は生前、兄に十分支援していた。会社の資金繰りのときも兄の協力を得られなかった。父の意思を無視するのか!」
Aも譲りません。
「父の意思は尊重する。でも、私は父の介護もしたし、最低限の取り分は認めてほしい。」
このように、遺留分の問題は感情的な衝突を伴うことが多く、「お金の問題」だけでなく「親の愛情の公平さ」という心理的側面も大きく影響します。
家庭裁判所の調停委員は、両者の気持ちに配慮しながら、法的な枠組みを説明して合意を促します。
最終的に、調停の中でBはAに対し「1,200万円を分割で支払う」という内容で和解が成立しました。
父の遺志をできるだけ尊重しつつ、法律の定める公平さも保つ、現実的な解決といえるでしょう。
5. 法的ポイントの整理

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遺留分とは | 相続人に保障された最低限の取り分(民法1042条) |
| 対象となる相続人 | 配偶者・子(直系尊属のみの場合は1/3) |
| 計算方法 | 相続財産 × 遺留分率 × 各相続人の法定相続分 |
| 請求方法 | 金銭による請求(内容証明 → 調停・訴訟) |
| 請求期限 | 知ったときから1年、または相続から10年以内 |
| 実務上の留意点 | 感情面への配慮・証拠(遺言・資産評価)の準備が重要 |
6. 弁護士からのアドバイス

遺留分問題は、「法律上の計算」と「家族の感情」の両方を扱う難しい分野です。
特に、相続人同士の関係がこじれると、調停や裁判に発展しやすく、結果的に時間も費用もかかります。
まずは冷静に、自分の遺留分額を正確に計算すること。
そのうえで、円満な話し合いで解決できる方法を検討することが大切です。
遺言書を作成する側も、遺留分に配慮した内容にしておくことで、将来の紛争を防げます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






