
遺産分割が終わった後に被相続人に負債があることが判明することがあります。
そのような場合、相続人としては、適切な対応をとることが重要です。
このコラムでは、遺産分割後に負債が発覚した場合の対処法について詳しく解説します。
1 はじめに

亡くなった方の遺産について遺産分割を行った後、負債が発覚することは珍しくありません。
被相続人が生前、周囲に秘密で借入等していた場合、相続人が借り入れに気付くことは難しく、債権者からの連絡などにより負債の存在に気付くということがあります。
このコラムでは、そのような場合に相続人としてはどのような手段をとることができるかを詳しく解説します。
2 負債の負担割合について再協議する
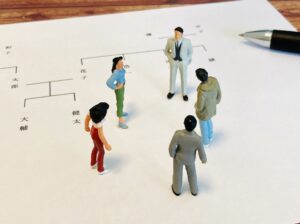
負債は法定相続分で各相続人に承継されますが、相続人同士の間で、誰がどれだけ負担するかを話し合って決めることは可能です。
プラスの財産と同様に負債も法定相続分での相続するのが原則ですので、債権者に対しては、各相続人は自分の法定相続分に応じた額の返済義務を負います。
遺産分割協議で特定の相続人が負債の全額または一部を負担すると合意しても、その合意は債権者に対して主張することはできません(債権者が同意した場合を除く)。
特定の相続人が負債の全額を支払った場合、その相続人は合意に基づき、他の相続人に求償(負担すべき分を請求)できます。
3 相続放棄または限定承認を検討する

(1)注意点
原則として、相続放棄や限定承認の手続きは、「自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内」(熟慮期間)に行う必要があります。
遺産分割後に負債が発覚した場合は、すでにこの期間が経過している可能性が高いです。
もっとも、このような場合でも「負債の存在を全く知らず、知ることができなかった」など、特別の事情がある場合は、負債の存在を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、遺産分割協議に参加していることなどから、家庭裁判所が個別に判断するため、必ずしも認められるわけではありません。
(2)相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の相続について、一切相続しないというものです。
これをすることによって、相続放棄した相続人は、相続人でなかったことになります。
そのため、プラスの財産は相続しないことはもちろん、マイナスの財産も相続しないことになります。
相続放棄は、原則として、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
申立には、所定の書類や戸籍等の添付書類が必要になります。
(3)限定承認とは
限定承認とは、被相続人の遺産について、相続したプラスの財産(預貯金、不動産など)の範囲内で、マイナスの財産(借金など)を支払う相続方法です。
被相続人の遺産について、マイナスの財産の方が多いことが見込まれる場合には、この方法をとることがあります。
4 消滅時効の援用を検討する

発覚した負債が成立してから長期間経過している場合、消滅時効が成立している可能性があります。
時効期間は、債権者が権利を行使できることを知ったときから5年、または権利を行使できるときから10年(いずれか早い期間)が原則です。
時効の効果を主張するためには、時効が成立したことに加え、時効の援用(時効の利益を受ける意思表示)を債権者に対して行う必要があります。
ただし、債務の存在を認める発言や一部弁済などをすると、時効がリセット(時効の更新)されてしまうことがあるため、注意が必要です。
5 債権者との交渉や債務整理を検討する

相続放棄や消滅時効の援用が難しい場合は、負債の返済義務を負います。
その場合、 債権者と交渉し、分割払いの相談や減額交渉を行うことが考えられます。
任意での返済が難しい場合、任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理手続をとることを検討します。自己破産が認められれば、負債の支払義務を免除(免責)してもらうことが可能です。
6 おわりに

以上見てきたように、遺産分割後に負債が発覚した場合、相続人がとれる手段にはいくつかあります。
どの手段が適切かを判断する必要がありますが、その判断は容易ではありません。
そのため、本コラムのようなケースに直面した場合は、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






