
「公正証書遺言があれば相続は安心」とは限りません。ある姉妹は「不動産はすべて次女に」という遺言をきっかけに関係が断絶しました。
しかし、弁護士が双方の代理人となり、感情的な対立を避けつつ交渉を開始。法的に保障された最低限の取り分である「遺留分」を根拠に、不動産の評価額に相当する金銭での解決を模索しました。
結果、不動産は遺言通り妹が取得し、姉は約1500万円の支払いを受ける形で円満に解決。本コラムでは、この実例を基に、一枚の合意文書の裏にある葛藤と、専門家だからこそ描ける未来志向の解決策を、弁護士が詳しく解説します。
「公正証書遺言さえあれば、相続で揉めることはない」というのは本当ですか?
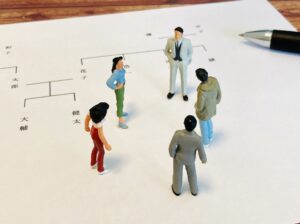
多くの方が、そう信じていらっしゃいます。
しかし、法律の専門家として数々の相続案件に携わる中で、私はその「神話」が、時として残酷な現実を招く場面を目の当たりにしてきました。
遺言書は、故人の最後の意思として尊重されるべきもの。ですが、その一枚の紙が、長年連れ添った家族の絆を、修復不可能なまでに引き裂いてしまうことがあるのです。
今回ご紹介するのは、まさにそのような、深刻な感情的対立の末に、弁護士が介入することでようやく着地点を見出した、あるご家族の物語です。
一枚の「遺産分割協議書」の中に記された数字や法律用語は無機質に見えるかもしれません。しかしその行間には、壮絶な葛藤と、再生への祈りが込められています。
「なぜ、妹だけに…」―公正証書遺言が招いた断絶

お父様が亡くなられた後、長女のAさんと、次女のBさんの間で相続が始まりました。お父様は生前、ご自身の意思を明確にするため、公証役場で作成した、法的に最も信頼性が高いとされる「公正証書遺言」を遺されていました。
その遺言書には、こう記されていました。
「主な財産である不動産(実家)は、次女Bに相続させる」
おそらく、そこにはお父様なりのお考えがあったのでしょう。晩年、お父様の身の回りの世話をし、同居していたのは次女のBさんでした。「最後まで面倒を見てくれた娘に、安心して住める家を遺したい」。その親心は、痛いほど理解できます。
しかし、遠方で家庭を築いていた長女Aさんにとって、その遺言は到底受け入れられるものではありませんでした。
「私だって、父さんが心配で何度も電話していた。帰省のたびに、できる限りのことはしてきたつもりだ。それなのに、なぜ…」
問題は、単純な金額の不公平さだけではありませんでした。その不動産は、姉妹が生まれ育った、かけがえのない思い出の詰まった実家です。そのすべてが一方的に妹のものになるという事実は、Aさんにとって、父親からの最後の「拒絶」のように感じられたのです。
電話口でのお互いをなじる言葉の応酬。送られてきた手紙には、これまでの鬱憤が綴られ、感情の溝は決定的なものになりました。かつては仲の良かった姉妹の対話は、完全に途絶えました。
弁護士が「翻訳家」となり、交渉のテーブルを作り出す

遺言は存在する。しかし、感情のしこりは日に日に固くなっていく。
当事者同士での解決が不可能だと悟った姉妹は、それぞれ別の弁護士に未来を託しました。これが、解決への最も重要な転換点でした。
弁護士は、まずお互いの「盾」となり、直接の感情的な衝突を避けるための緩衝材となります。そして、依頼者の「悔しい」「悲しい」「分かってほしい」という感情的な言葉を、「法的には、これだけの権利が保障されています」という客観的な法律言語に翻訳していくのです。
Aさんの代理人弁護士は、直ちに財産を評価し、Aさんの「遺留分」(法律で保障された最低限の取り分)を算出しました。それは、単なる「不公平だ」という感情論ではなく、「私には、法的に約1500万円を受け取る権利がある」という、揺るぎない交渉の土台となりました。
一方、Bさんの代理人弁護士は、「お父様の遺志を尊重したい」というBさんの気持ちを受け止めつつも、遺留分を無視し続けた場合のリスク(長期化する裁判、高額な弁護士費用、そして最終的には敗訴する可能性)を冷静に説明しました。
凍り付いていた姉妹の関係は、弁護士という「翻訳家」を介することで、ようやく「交渉」というステージへと移行できたのです。
1500万円~合意文書に刻まれた「現実的な落としどころ」

数か月にわたる両代理人間の交渉の末、姉妹はついに合意に至ります。その到達点が、遺産分割協議書です。
そこには、極めて現実的で、緻密な解決策が記されていました。
まず、遺言どおり、不動産は次女Bさんが取得する 。お父様の最大の願いは、ここに尊重されました。
その代わり、長女Aさんは、不動産の価値に相当する約1000万円を、お父様の遺した預貯金から受け取る 。
Bさんが立て替えていた葬儀費用などを預貯金から精算し 、残った預貯金と死亡保険金(100万円)を公平に分け合う 。
その結果、Aさんが受け取る金額の合計は約1500万円となる 。Bさんは、その支払いを【令和7年●月末まで】という、資金を準備するための猶予期間を得て、指定された口座へ振り込む 。
この合意は、Bさんが思い出の実家を売却することなく、Aさんが法的に保障された権利を金銭で確保するという、まさに「Win-Win」の解決でした。もし弁護士がいなければ、感情的な対立の末に不動産を競売にかけ、姉妹の元にはわずかなお金と、修復不可能なほどの憎しみしか残らなかったかもしれません。
まとめ~最良の解決は、法律と心の両輪から~

この協議書の最後の条項には、「本協議書に定めるものを除き、甲乙間に何らの債権債務が存在せず、互いに金銭その他の請求をしないことを確認する」 とあります。これは「清算条項」と呼ばれ、この合意をもって、すべての紛争を過去のものとする、という法的な約束です。
遺言書は、時として家族の間に残酷な問いを投げかけます。
もし、あなたが相続の問題で「納得できない」「どうしていいか分からない」と悩んでいるのなら、どうか一人で抱え込まないでください。法律の専門家である弁護士は、あなたの法的な権利を守るだけでなく、絡み合った感情の糸を解きほぐし、未来志向の解決策を共に探す伴走者となります。
一枚の合意文書の裏には、必ず、そこに至るまでの家族の物語があります。その物語を、憎しみや断絶で終わらせないために。私たちは、法律と心の両面から、あなたにとって最良の解決を導き出すお手伝いをいたします。
最後に見ていただきたい相続サポートのこと
私たちは、開所以来35年以上、相続にお悩みの方に一貫して寄り添って参りました。
皆様が苦しい相続人間の紛争を忘れ日常を取り戻していただくために、法的な専門知識と経験を活かして、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。
当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。
お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。
私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






