
令和6年(2024年)に民法が改正され、これまでどおり離婚後に単独親権とすることもできれば、父母が共同親権とすることも可能になりました。裁判所や父母という当事者が、子の監護教育権を行使する指針として「子の利益」を考慮せねばならないと考えられます。民法改正後の親権の定めについての意味と、裁判所の関与について説明したいと思います。
民法改正後の親権者の指定について
「子の利益」が考慮される意義

従前、「子の利益」という概念は、裁判所が家庭内にその判断を及ぼす正当化の根拠として用いられたり、父母などの家庭内の当事者が定める内容を覆すための正当化の根拠として用いられることが多かったといえます。
しかし、その後平成23年に民法が変わり、「子の利益」というのは上記のような正当化の根拠というよりは、子の監護をする親の権利行使をする指針として、あるいは親が親権を行使するにあたって制約を受けることの根拠として用いられるようになったのです。
さらに、令和4年から6年にかけての法改正により、「子の利益」という概念は、父母の子の養育における指針となり、親は子の人格を尊重し、年齢及び発達の程度に配慮すべきという義務も伴うものになりました。
親権の行使、養育の指針としての「子の利益」とは何か
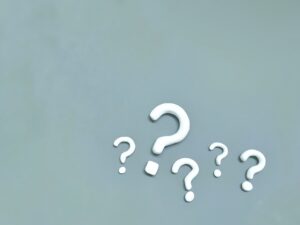
民法818条1項の定め
令和6年に成立した改正民法818条1項は、「親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない」と定め、子の利益が親権行使の指針であることを条文上明らかにしました。親権の行使の場面だけではなく、養育の指針として子の利益があることも定めており、親は親として親権を行使するだけではなく、子の養育に関し適切な形で子の養育に関わり、責任を果たすべき、と考えられるのです。
「子の利益」を判断するのは誰か
「子の利益」をどのように判断するのかは、まずは親権者である父母が判断するということになりますが、その判断に当たっては民法に定める子の人格尊重などの義務があることが前提です。
親権者たる父母が採った選択について、「子の利益」に反するものと考えられた場合には、親権が制限されたり、親権者の変更がされるということが考えられ、また場合によっては子から親権者に対する損害賠償請求がされるということもあり得るでしょう。
親権者を定める場合の「子の利益」について

令和6年の法改正前は、父母の婚姻中は父母双方が親権者となり、離婚後は父母のいずれかを単独親権者と決めることになっていました。
しかし、法改正により、離婚後も父母双方を親権者とすることもできるようになりました、離婚後の親権者を単独親権とするのか、それとも共同親権とするのかは、父母の協議または家庭裁判所が「子の利益」を判断して定める、としています。
単独親権も共同親権も選択できるようにはなりましたが、法律上はいずれが原則であるかを定めているわけではありません。
このような法改正がなされた背景には、「子の利益」のために父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましい、ということであって、どのような関わり方が「適切な形」と言えるのかは、まさにケースバイケースであり、法律上原則が明らかになっていないことからも明らかなとおり、単独親権だから良い、共同親権だから良い、ということではなく「適切な形」となるように「子の利益」に即して決めていくべき、ということではないかと思われます。
当事者の協議による親権者の定め
当事者の協議で親権者を定める場合は、具体的な事情に応じて、子の利益の観点から判断することになります。子の意見を適切に考慮し、子の人格を尊重せねばならないことは当然のことですが、離婚時に父母が対応に協議できない場合もあるでしょう。
従前、離婚の際には未成年者の親権者を決めなければならない としていたところ、改正民法では父母の協議ができない場合に備え、親権者を指定する審判・調停が申し立てられていれば協議離婚もできるようになりました。
もし父母の協議で子の利益に反する親権者の定めがされた場合には、事後的に親権者変更の手続をすることも考えられ、その中では「親権者変更」が「子の利益」のために必要かという判断と、その判断の前提として親権者の定めの協議の経過も考慮されることになりました。
家庭裁判所による親権者の定め
父母の協議で親権者を定めることができない場合、家庭裁判所は、親権者を一方(単独親権)か、双方(共同親権)か定めることができるとされ、その考慮要素も法律上定められることになりました。
父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所は「必ず」父母の「一方」を親権者として定めなくてはならないとされたのです(改正民法819条7項後段)。
典型的な例としては、父または母が子や他方に対し暴力等を加える恐れがある場合、などがあると考えられています。このようなケースでは、父母が共同して親権を行うことが困難であるため、「共同親権としない」場合について規定をしているのです。
そこでは、「子の利益」として、子自身及び父または母の安全が重要であるという視点が示されているとも考えられるでしょう。
現在、日本国内の離婚の9割は協議離婚であり、裁判所が関わらない、あるいは弁護士も関わらない、という離婚は決して珍しいものではありません。夫婦の関係が対等であれば、親権についても十分に協議をした上で、また一方的な主張にならぬように合意をすることも可能でしょうが、残念ながらそのような夫婦ばかりではないでしょう。また、そもそもそのような対等な関係を築けなかったからこそ、夫婦という形を維持できなかったという場合も多いと思われます。
上記のとおり、協議離婚によって父母の一方あるいは双方に親権を定めたとしても、その後「親権者変更」という方法をとって、離婚時に定めた親権者を変更するということも選択肢としてないわけではありませんが、「判断の前提として親権者の定めの協議の経過も考慮する」とされていますので、その協議の過程に問題点があったことを主張できるか、主張した上でその裏付けがあるか、ということはリスクとして十分考慮しなければなりません。
親権の定めについての課題

上記のような「親権者を単独とするか、共同とするか」という協議事項があるほか、仮に共同親権とした場合に、「父母の親権行使についての意見が一致しなかった場合」の問題として、究極的には家庭裁判所に当該事項の親権行使者を指定してもらう、という手続があります。
改正民法では、親権を単独で行使できる事項・場面も定めていますが、単独行使できない事項・場面の場合、結局父母間で紛争が生じてしまい、家庭裁判所で争わなければならないという課題が残ってしまうことは十分理解しておく必要があるでしょう。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






