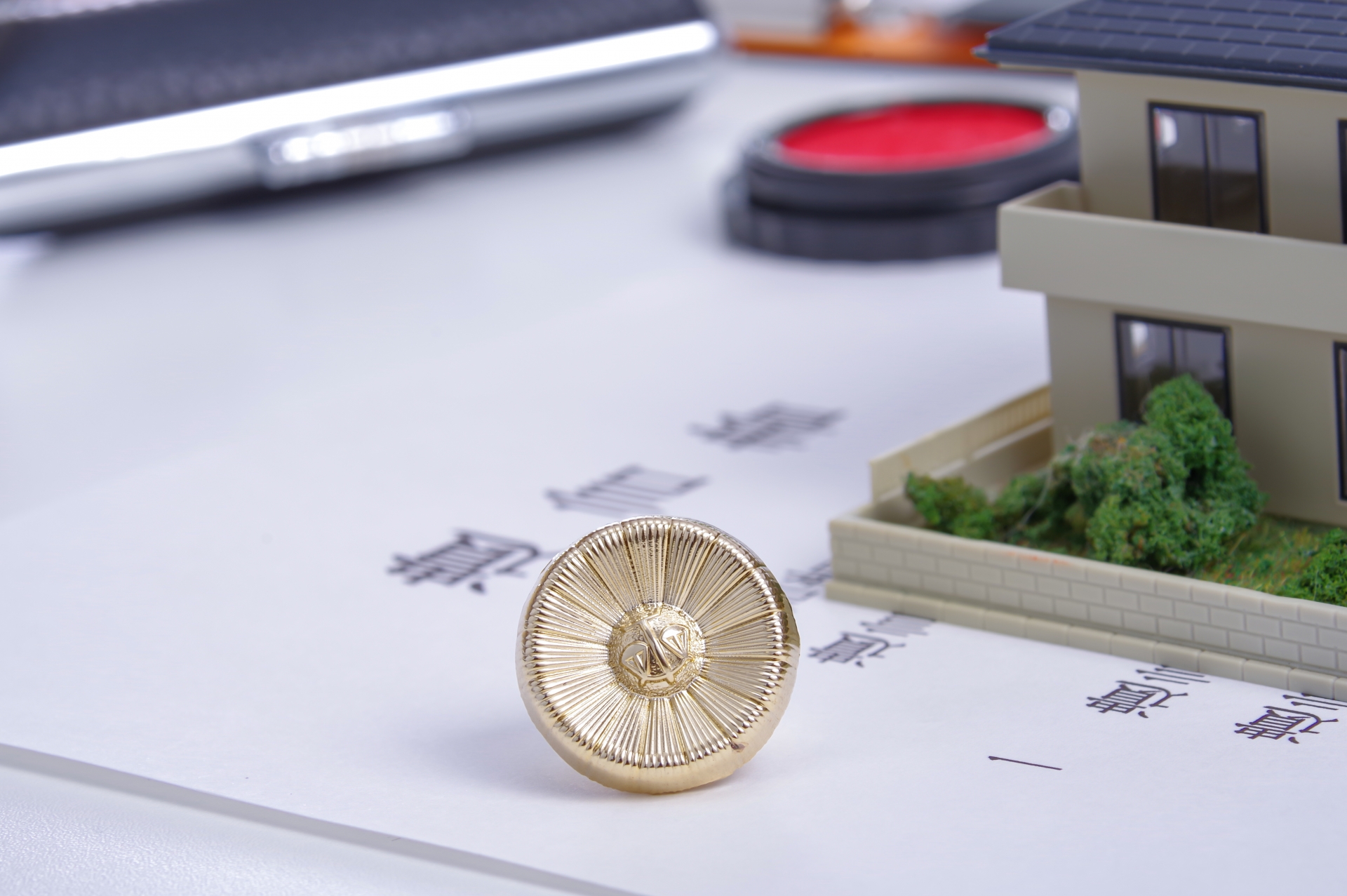
遺言は、故人の最後の意思を尊重するための重要な法的手続きです。
しかし、時にその遺言が法的に無効とされるケースがあり、親族間で激しい争いが生じることがあります。
遺言の効力を争う方法として「遺言無効確認訴訟」がございます。
本ページは、遺言が無効となるケースや遺言無効確認訴訟の流れなどについて弁護士が解説いたします。
遺言無効確認訴訟(遺言無効確認の訴え)とは?

遺言無効確認訴訟は、「故人が作成した遺言書が、法律上の要件を満たしておらず無効である」ことを裁判所に認めてもらうための訴訟を指します。
遺言書がある場合、基本的には、その遺言書に従って遺産が分けられることになります。
したがって、遺言書が存在すれば、もし遺言書に何らかの無効事由があったとしても、その有効性が争われない限り、その遺言書に従って遺産が分けられてしまうおそれがあるため、
遺言書の無効性を争うためには、「遺言無効確認訴訟」を提起する必要があります。
遺言が無効だと主張されやすいケース

次に、遺言書が無効と主張されやすいケースについて解説いたします。
1 認知症等で遺言能力が無い
遺言を行うためには、遺言能力(「遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる意思能力」)が必要となります。
遺言者が遺言を行った当時、遺言内容を全く理解していないのにもかかわらず作成された等の事情がある場合には、遺言が無効となる可能性があります。
医師の診断記録や遺言作成前後の遺言者の状況等を述べる供述等の証拠でもって、遺言能力が欠如していることを主張立証する必要があります。
2 遺言書の様式に違反している
遺言書の作成に関するルールは、法律によって定められており、そのルールに則っていないものは無効となります。
例えば、自筆証書遺言は、原則全文自筆(財産目録は自筆でなくても問題ありません)が必要であり、署名、日付、押印が必要です。
また、公正証書遺言の場合、法定されている証人の人数(2人以上)を満たしていなかったり、証人に欠格事由があるなどの場合、無効とされる可能性があります。
3 詐欺・強迫による遺言
遺言書の中で、財産について書かれた部分については、民法の意思表示に関する規定の適用があるため、遺言者に対する脅迫や詐欺等がある場合、取消・無効原因になり得ます。
被相続人が、遺言書作成当時に、脅されたり騙されたりして、それによって遺言書を作成したことを、客観的に立証する証拠(録音データ等)が必要となります。
4 公序良俗・強行法規に反する
例えば、愛人との関係性維持のために、配偶者に一切の財産を渡さず、全て愛人に渡るように作成された遺言書のように、推定相続人の生活基盤を崩すものや、内容があまりに不合理な遺言書等は、公序良俗に反するとして、無効原因となり得る場合があります。
遺言無効確認訴訟の流れ

遺言無効確認訴訟の提起に向けた準備から、訴訟終了までの流れについて解説いたします。
1 証拠準備
遺言無効を主張するためには、それを裏付ける証拠が重要となります。
例えば、被相続人の遺言能力を争うためには、医師の診断記録や遺言作成前後の遺言者の状況等を述べる供述等が証拠となります。
なお、遺言書の偽造の有無という観点から、筆跡が問題となることがありますが、裁判実務上、筆跡鑑定の信用性はそれほど認められておりませんのでその点ご注意ください。
2 調停の申立て
いきなり遺言無効確認訴訟を提起することは原則として認められておりません。
まず、先に家庭裁判所に対し調停を申し立てる必要があります。
調停の申立先は原則として、他の相続人のうちひとりの住所地を管轄する家庭裁判所です。
調停では、中立である調停委員が各相続人の主張を聞き、遺言無効や遺産分割に関する合意をサポートしてくれます。
3 訴訟提起
調停が不成立に終わった場合は、遺言無効確認訴訟を提起することになります。
遺言無効確認訴訟を提起する場合、請求相手「被告」を特定する必要があります。
「被告」になる者として以下の者が挙げられます。
被告相続人、あるいは受遺者、承継人、遺言執行者
※遺言無効確認訴訟は、相続人全員を被告にする必要はありません。
申立先の裁判所は、被告の住所地、または、被相続人の相続開始時(死亡時)の住所地を管轄する裁判所となります。
4 訴訟提起後
原告及び被告が書面でもって主張をし合い、その後裁判官による判決が下されます。
訴訟で勝った場合、負けた場合について

次に、遺言無効確認訴訟にて勝訴した場合、敗訴してしまった場合のその後の対応について解説いたします。
1 勝った場合
遺言書の無効が認められた場合には、遺言書が存在しないこととみなされますので、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
もっとも、形式的な不備が認められて無効となった場合であって、死因贈与として有効と認められる場合には、その遺言書の内容に従って手続きが進められることになります。
2 負けた場合
裁判官の判断に不服があるとして控訴しなければ、一審の判断が確定します。
その場合には、遺言書=有効となりますので、その遺言書に従って遺産の分配がなされます。
まとめ

以上、遺言無効確認訴訟までの流れなどについて解説しました。
遺言の無効が認められるためには、「証拠」が重要です。
「この遺言は無効なのでは?」とお悩みの方はぜひ弁護士にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






