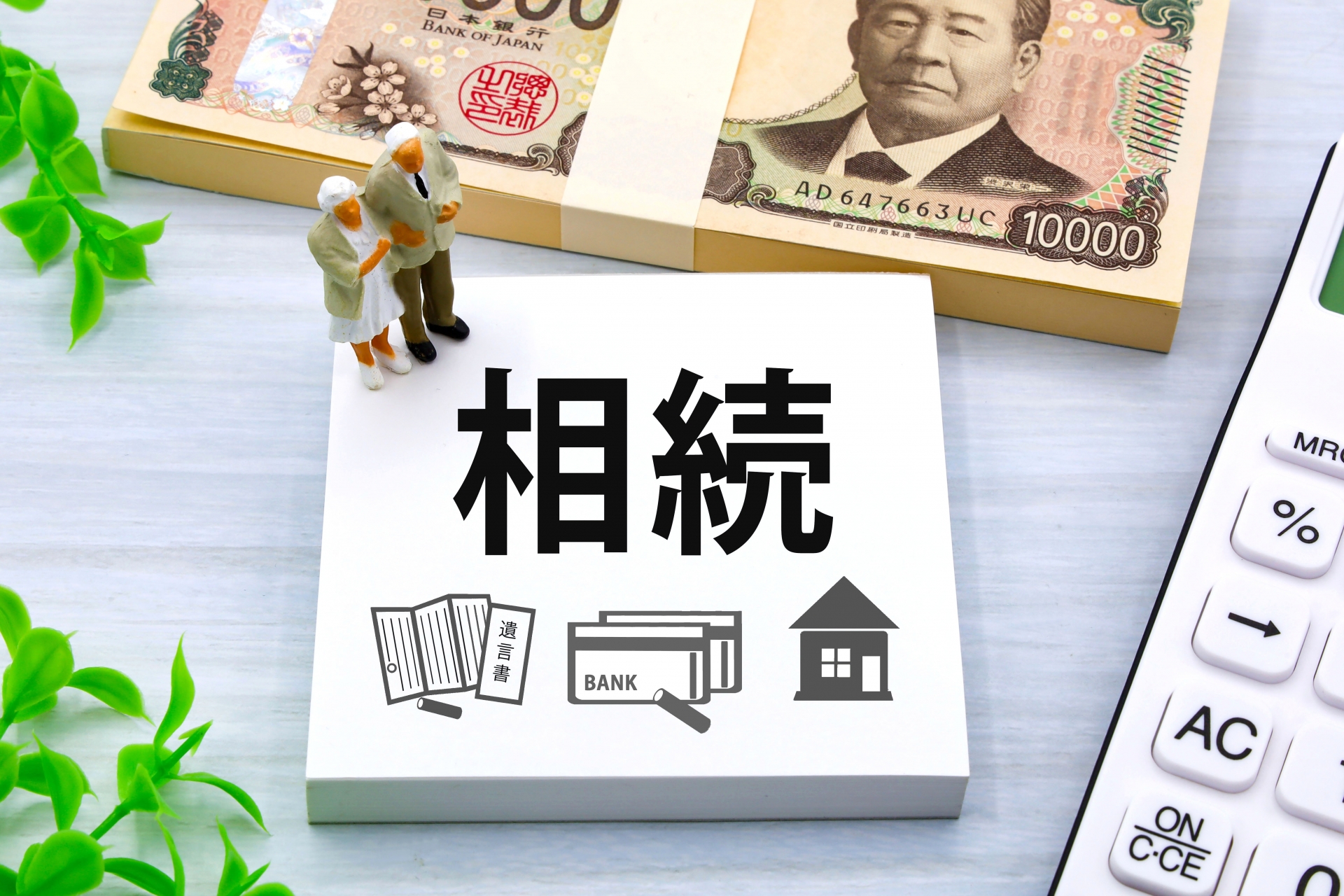
相続が発生したとき、悲しみに暮れる間もなく、やらなければならない手続きが山積します。その中でも、特に重要でありながら、どこから手をつけて良いか戸惑うことが多いのが「相続財産の調査」です。
相続財産は、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金やローンなど)も含めて、全てを正確に把握しなければなりません。この調査を怠ると、後々の相続トラブルや、相続税の申告漏れといった重大な問題に発展する可能性があります。
本コラムでは、相続財産の調査がなぜ重要なのか、そして具体的にどのようなステップで調査を進めていけば良いのかについて、ご案内いたします。
なぜ相続財産の調査が必要なのか?

相続財産を正確に把握することの重要性は、主に以下の2つの理由に集約されます。
円満な遺産分割協議に向けて
遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、故人の財産をどのように分けるかを決める手続きです。この話し合いをスムーズに進めるためには、まず「何が、どれだけあるのか」という、財産の全体像を正確に把握することが不可欠です。
もし、調査が不十分で、後から新たな財産が見つかった場合、遺産分割協議をやり直す必要が出てきますし、「なぜ最初に教えてくれなかったのか」と、他の相続人との間に疑念や不信感が生まれる可能性があります。これは、相続トラブルの大きな火種となりかねません。
透明性の高い財産調査こそが、円満な相続を実現するための第一歩となります。
相続税の申告義務とリスク回避のために
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続人は税務署に相続税を申告し、納税する義務が生じます。
もし、相続財産の調査が不十分で、申告すべき財産を漏らしてしまった場合、過少申告と見なされ、追徴課税などのペナルティが課されるリスクがあります。
特に、隠し口座や名義預金、多額のタンス預金など、把握が難しい財産がある場合は注意が必要です。
相続税の申告にも期限があります。限られた期間内に、全ての財産を正確に把握するためには、迅速かつ計画的な調査が求められます。
相続財産調査の基本ステップ

相続財産の調査は、まず故人の日常的な手がかりを探すことから始めます。
遺言書の有無を確認する
遺言書は、故人の最後の意思が記された重要な書類です。遺言書に財産の分け方が記されている場合、原則としてその内容に従って相続手続きを進めることになります。
まずは、遺言書がどこかに保管されていないか確認することが大切です。
公正証書遺言
公証役場で作成された遺言書で、原本が公証役場に保管されています。
全国の公証役場に遺言書の有無を照会することができます。故人の住民票上の住所地や本籍地などを手掛かりに、最寄りの公証役場に問い合わせてみましょう。
自筆証書遺言
故人が自筆で作成した遺言書です。自宅の仏壇や机の引き出し、書斎、貸金庫などに保管されていることが多いです。
近年、法務局で自筆証書遺言書を保管できる制度が始まりました。法務局に保管されている場合は、遺言書情報証明書を発行してもらうことで、内容を確認できます。
遺言書が見つかった場合でも、その内容を法的に有効なものとして取り扱うためには、家庭裁判所での検認という手続きが必要になるケースがあります。
故人の生活の痕跡を探す
遺言書が見つからない、または遺言書がない場合は、故人の生活の痕跡を丹念に探していくことが重要です。
郵便物
金融機関からの取引明細、通帳やキャッシュカード、クレジットカードの請求書、生命保険の案内、不動産の固定資産税納税通知書など、財産に関する重要な書類が送られてきている可能性があります。
契約書・権利書
不動産の登記権利証、売買契約書、借地借家契約書、株券、会員権の証書などが、書類棚や金庫に保管されていないか確認しましょう。
パソコンやスマートフォン
オンラインバンキングやインターネット証券の履歴、メールのやり取りなどを確認することで、取引のある金融機関や証券会社を特定できる場合があります。
これらの手がかりを基に、どのような財産があるのか、一つずつリストアップしていきます。
積極的に調べるべき相続財産の種類と調査方法

故人の生活の痕跡から手がかりを得たら、次は具体的な財産調査に進みます。
財産は大きくプラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)に分けられます。
プラスの財産(積極財産)の調査
プラスの財産は、基本的に故人の名義で所有していたものです。
預貯金・株式
まずは預貯金や株式などの財産が残されていることが考えられます。
故人の通帳やキャッシュカード、郵便物から、取引のある金融機関を特定します。
金融機関が特定出来たら、金融機関の窓口に、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を持参し、故人の口座の「残高証明書」と「取引履歴」の発行を依頼します。
これにより、故人が亡くなった時点の正確な残高と、過去の入出金記録を確認することができます。
なお、全国各地に支店を持つ金融機関の場合、口座が複数ある可能性があります。念のため、全国の支店に照会をかけることも検討しましょう。
また、近年多いネット銀行やネット証券の場合、通帳がないため、パソコンやスマートフォンからログイン情報を探す必要があります。
不動産

不動産を調査するために、名寄帳(なよせちょう)の取得をすることが考えられます。
名寄帳には、その市区町村内にある、故人名義の土地や建物の全てが一覧で記載されています。これにより、故人が所有していた不動産の全容を漏れなく把握できます。
なお、不動産が所在する市区町村ごとに名寄帳を請求する必要があるため、故人が複数の市区町村に不動産を所有していた場合は、それぞれの役場に問い合わせる必要があります。
また、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書も、故人が所有していた不動産を特定する重要な手がかりとなります。
生命保険・死亡保険金
また、保険証券の確認も必要です。
故人の契約書類の中から、生命保険の保険証券や保険証券番号がわかる書類を探します。
こういった書類が見つからない場合、故人が契約していた可能性のある保険会社に直接問い合わせることで、契約の有無や保険金の受取人を確認することができることもあります。
なお、生命保険金の受取人が相続人以外に指定されている場合、その保険金は相続財産とはならず、受取人固有の財産となります。
その他の財産
その他には、以下の財産についての調査が考えられます。
①自動車: 故人名義の自動車は、車検証で所有者を確認します。
②ゴルフ会員権、リゾート会員権など: 会員権の証書や契約書を探します。
③貴金属、骨董品、書画など: 鑑定が必要な場合もあります。
④貸付金(誰かにお金を貸していた場合): 金銭消費貸借契約書など、お金を貸したことを証明する書類を探します。
マイナスの財産(消極財産)の調査
マイナスの財産(債務)の調査も、プラスの財産と同様に重要です。借金は、プラスの財産を上回る可能性があるため、特に注意が必要です。
借金やローンなど
万が一、故人の方に債務があった場合、対策が必要です。
そこで、消費者金融やクレジットカード会社からの督促状、明細書、ローン契約書などを探すことが重要です。
また、故人の方が消費者金融や銀行、クレジットカード会社などから借り入れをしていた場合、その情報は「信用情報機関」に登録されています。
主な信用情報機関である、CIC(クレジット情報)、JICC(消費者金融、クレジット情報)全国銀行個人信用情報センター、KSC(銀行ローン情報)などの機関に故人の情報開示を請求することで、故人がどの金融機関から、どれだけの借金をしていたのかを正確に把握することができます。
未払金
故人の方が亡くなった時点で支払いが完了していなかった費用も、マイナスの財産となります。
例えば、未払いの医療費、公共料金(電気、ガス、水道)の未払い分、家賃賃や地代の未払い分、所得税や住民税などの税金などには注意が必要です。
まとめ
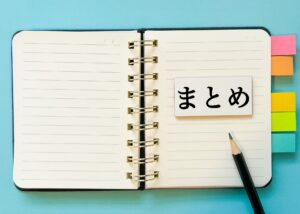
相続財産の調査は、円満な相続を実現し、将来のトラブルを未然に防ぐために、最も重要なステップです。
まずは故人の遺言書の有無を確認し、生活の痕跡を丁寧に辿っていくことから始めてみましょう。そして、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても漏れなく調査することが大切です。
もし、調査を進める中で、疑問点や不安な点が出てきた場合、また、調査自体が難しいと感じた場合は、一人で悩まずに法律の専門家である弁護士にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






