
被相続人の存命中に、被相続人と相続人予定者の間で話し合って財産の帰属先を決め、死因贈与契約を締結しておくことで、本来は相続発生後に行うべき遺産分割協議の代わりにすることができるでしょうか。本稿では、その有用性と注意点を述べます。
「被相続人の存命中に、財産の分け方を決めておきたい」として…

遺産分割協議は、相続発生後、すなわち、被相続人が死亡した後で、相続人が遺産をどのように分けるか話し合って決めていくものです。
このため、相続が発生していないにもかかわらず、すなわち、被相続人がまだ生きている段階で、相続人予定者が遺産をどのように分けるか話し合って決めたとしても、その遺産分割協議は無効です。
それでは、ここで切り口を変えて、被相続人がまだ生きている段階で、被相続人と相続人予定者が話し合い、遺産の帰属先を「死因贈与」という形で定めた場合はどうでしょうか。
その「死因贈与」に関する契約書を公正証書で作成しておき、そこで執行者も定めておけば、被相続人の生前に遺産分割協議を行ったのと同じ結果にならないでしょうか。
基本のおさらい:「死因贈与」とは?
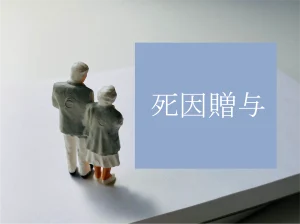
「死因贈与」とは、人の死亡を原因として効力が発生する贈与のことです。
通常の贈与だと、あげる人(=贈与者)ともらう人(=受贈者)がどちらも生きている状態で、贈与者から受贈者への財産の移転が行われます。
これに対して、「死因贈与」では、予め、「贈与者が死亡した場合に、●●を受贈者にあげます」と合意しておき、贈与者が亡くなった段階で、受贈者にその指定された財産が移転するということです。
同じく、人の死亡を原因として財産移転の効力が発生するものに、「遺贈」(=遺言によって行う贈与、遺言によって被相続人の財産が他の人に移転すること)がありますが、「死因贈与」は贈与者と受贈者との合意(契約)であるのに対し、「遺贈」は被相続人の一方的な意思表示による単独行為であるという点が異なります。
「死因贈与」は、口頭の合意だけでも成立しますが、将来のトラブルを未然に防止するためには、書面(契約書、特に公正証書)の形でしっかりと残しておくべきです。
「死因贈与」を活用する場合の有用性と注意点

それでは、この「死因贈与」を活用して、被相続人の存命中に、被相続人と相続人予定者が話し合って財産の分け方を決めておく(財産の帰属先を定めた死因贈与契約書を公正証書の形で作成しておく)という方法を取る場合の、有用性と注意点を見てみます。
有用性 ①生前に遺産分割協議を行ったのとほぼ同じ効果が得られる
被相続人と相続人予定者が話し合い、遺産の帰属先を「死因贈与」という形で定め、その「死因贈与」に関する契約書を公正証書で作成しておき、さらに執行者も定めておけば、将来、被相続人が死亡した時に、公正証書記載のとおりに遺産を分配することができます。
つまり、被相続人の生前に遺産分割協議を行ったのとほぼ同じ法的効果が得られるということで、基本的には、「死因贈与」は生前の遺産分割協議の代わりになると言えます。
ただし、当然ですが、本来の遺産分割協議は被相続人本人が不在の場で行うものであるのに対し、上記の方法を取った場合は被相続人(となるべき人)本人が存在して、「死因贈与」契約の当事者となるわけです。
この点は、「被相続人本人の意向を明確に反映させられる」という利点がある反面、「被相続人本人の意向を無視した合意はできない(相続人予定者だけでうまく事を収めるというわけにはいかない)」ことを意味しますので、ケースによっては向き不向きがあるかもしれません。
有用性 ②全ての財産を対象とする「死因贈与」も可能
民法上、「死因贈与」は特定の財産を対象としてしかできないとは定められていないため、全ての財産を対象とすること、例えば、「贈与者の有する一切の財産を死亡時に●●に贈与する」といった包括的な「死因贈与」契約も有効です。
これは、「遺言者の有する一切の財産を●●に相続させる」という遺言を作成したのと、同じような結果となります。
注意点 ①撤回の容易性
遺産分割協議は、いったん成立すると、全ての相続人の合意がある場合などを除き、原則としてやり直すことはできません。
これに対し、被相続人の生前に「死因贈与」の形で遺産の帰属先を定めた場合は、負担付き死因贈与の負担がすでに履行済みである場合などを除き、遺言と同様、贈与者(被相続人)は原則として「死因贈与」を撤回できます。
つまり、被相続人の心変わりによって、相続人予定者はもらえるはずだった遺産をもらうことができなくなる可能性がある、ということです。
なお、不動産をもらう予定の相続人の権利を確保するため、「死因贈与」の対象となる不動産に仮登記(始期付所有権移転仮登記)をしていたとしても、法律上は「死因贈与」の撤回を防ぐ効果はありませんので、注意が必要です。
注意点 ②遺留分侵害額請求の対象になる可能性
遺産分割協議の場合は、誰がどの財産をどれだけ取得するかを話し合い、相続人全員の合意がまとまったところで成立しますので、遺留分の問題が生じることはありません。
これに対し、「死因贈与」の方法を取った場合は、被相続人から遺産を贈与された相続人(受贈者)が、ある相続人の遺留分を侵害しているとして、その相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
注意点 ③相続税の他に不動産取得税がかかる
「死因贈与」の場合、かかる税金は「贈与税」ではなく「相続税」ですから、この点は遺産分割協議と一緒です。
ただし、「死因贈与」の方法を取った場合、対象が不動産だと、そこにさらに「不動産取得税」がかかってきます。これは、遺産分割協議によって不動産を取得する場合にはかかってこない税金ですので、注意が必要です。
まとめ
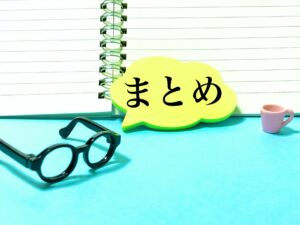
上記のとおり、「死因贈与」を活用することで、被相続人の生前に遺産分割協議を行ったのと同様の効果を得ることは一定程度可能ですが、そこには「死因贈与」ならではの注意点もあります。
事案によっては、ある特定の財産についてだけ「死因贈与」の対象とし、それ以外は遺言を作成しておく方法の方が向いている場合もあるでしょう。
「死因贈与」によるべきか、遺言によるべきか、または、敢えて相続人間の遺産分割協議に委ねた方がよいのか、判断に迷う場合は必ず弁護士など専門家にご相談下さい。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






