
例えば親(被相続人)がアパートやマンションを経営していた場合、その相続は一般的な家庭とは比較にならないほど複雑です。遺産の大部分が分けにくい「不動産」であるため、相続人間の意見がまとまらず、深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。
この記事では、不動産オーナーの相続で実際に起こる問題点を具体的な相談事例に沿って整理し、遺産分割の基本的なルール等を弁護士が解説します。
ご相談の事例:資産5億円の父が遺言なく逝去

相談者:長男・Bさん(50歳・会社員)
状況:
先日、長年アパート経営をしていた父が亡くなりました。遺言書はありません。相続人は母、遠方に住む妹、そして私の3人です。遺産は以下の通りです。
- 資産
- 不動産:約5億円(自宅、収益物件5棟)
- 預貯金:3,000万円
- 負債
- アパートのローン:約1億円
- その他
- 生命保険金:2,000万円(受取人は母)
妹は「不動産はいらない。法律上の相続分を現金で欲しい」と主張しています。母は今の自宅に住み続けたいと望んでおり、私自身は事業経験がなく、多額のローンを引き継ぐことに大きな不安があります。相続税の支払いも迫っており、どうすればいいか分かりません。
1. 遺産分割の前に知るべき法律の基本
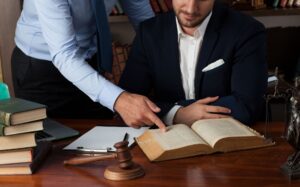
感情的な話し合いになる前に、まずは法律上のルールを正確に理解することが重要です。これが話し合いの共通の土台となります。
法定相続人と法定相続分
遺言がない場合、民法で相続人とその取り分(法定相続分)が定められています。Bさんのご家庭では以下のようになります。
- 母(配偶者):1/2
- 長男(子):1/4
- 妹(子):1/4
これが遺産分割の基本的な割合です。ただし、法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、この割合と異なる分割も可能です。
遺産の範囲
分割の対象となるのは、基本的には、プラスの財産(不動産、預貯金)の評価額から借金総額(ローン)を差し引いた金額を分け合うことになります。
- 純資産額:(不動産5億円 + 預貯金3,000万円) – ローン1億円 = 4億3,000万円
【注意点】生命保険金の扱い
お母様が受け取った生命保険金2,000万円は、受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象にはなりません。ただし、相続人間で著しく不公平な結果となる場合には、例外的に遺産に含めて計算する「特別受益」に準ずるものとして扱われることがあります。
相続人間の公平を図る「特別受益」と「寄与分」
法定相続分通りに分けることが不公平になる場合に、それを調整する制度があります。
- 特別受益: 相続人の誰かが、生前に家を建てる資金援助、事業資金の提供、高額な学費の負担など特別な援助を受けていた場合、その分を遺産に加算して計算し直すことで公平を図ります。援助額が相続分を超える場合は「超過特別受益」として、その相続人の相続分はゼロになることもあります。
- 寄与分: 相続人の誰かが、親の事業を無給で手伝うなど、財産の維持・増加に特別な貢献をしていた場合、その貢献度に応じて法定相続分以上の財産を受け取ることが認められる場合があります。
これらの主張には客観的な証拠が必要で、争いの原因になりやすい点です。
債務の承継について
相続では、プラスの財産だけでなく、債務(借金)も相続されます。アパートローン1億円についても、原則として法定相続分に応じて各相続人が承継することになります。
2. 不動産評価の重要性と具体的手法

不動産の評価は遺産分割の基礎となる重要な要素です。評価方法により大きく金額が変わるため、適切な評価手法を選択することが必要です。
2-1. 不動産評価の種類
固定資産税評価額 市町村が決定する評価額で、一般に時価の7割程度とされています。遺産分割では参考程度に留めるべきです。
路線価 相続税申告で使用される評価額で、時価の8割程度とされています。相続税計算では重要ですが、遺産分割での実際の価値とは乖離があります。
不動産鑑定評価額 不動産鑑定士による専門的な評価で、最も実際の取引価格に近いとされます。遺産分割では最も適切な評価方法です。
2-2. 収益物件特有の評価ポイント
収益還元法による評価 アパートなどの収益物件では、年間賃料収入を還元利回りで割り戻した「収益価格」も重要な指標となります。
築年数と修繕費用の考慮 建物の築年数、今後必要となる大規模修繕費用、空室リスクなども評価に影響します。
立地条件と将来性 駅からの距離、周辺環境、人口動態なども長期的な収益性に影響するため、評価に反映されます。
3. 不動産を分ける4つの方法

現金と違い、物理的に分けられない不動産の分割には、主に4つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、最適な方法を選ぶ必要があります。
方法1:現物分割
内容:「この土地は母に、あのアパートは長男に」というように、不動産そのものを分ける方法。
メリット:不動産を売却せずに済む。
デメリット:各不動産の価値が異なるため、公平に分けるのが難しい。
方法2:換価分割
内容:不動産を売却し、現金化してから相続分に応じて分配する方法。
メリット:
・最も公平に分けやすい
・納税資金も同時に確保できる
・管理の手間から解放される
・相続人間の争いが起きにくい
デメリット:
・収益を生む事業を手放すことになる
・売却に時間がかかる場合がある(通常3-6ヶ月)
・譲渡所得税が発生する(売却益の約20%)
・市況によっては安値での売却を余儀なくされる
・賃借人との関係で売却時期が制約される場合がある
方法3:代償分割
内容:相続人の一人が不動産を全て相続する代わりに、他の相続人へ法定相続分に相当する現金(代償金)を支払う方法。
メリット:事業や自宅をそのままの形で残せる。
デメリット:不動産を相続する側に、多額の現金を支払う資力が必要になる。
方法4:共有分割
内容:一つの不動産を、相続人全員の共有名義にする方法。
メリット:手続きが一時的に完了したように見える。
デメリット:将来の売却や建て替えなどで全員の同意が必要になり、トラブルの原因となる。権利関係者が増えていくリスクも高く、原則として避けるべき方法です。
今回の事例では、母の居住と事業の継続を考えると、「代償分割」等を軸に検討するとが現実的と思えます。
「代償分割」を進めるにあたり、具体的に何をすべきか

①不動産の「時価」を正確に把握する
全ての不動産の客観的な価値を把握します。相続人間の公平を期すため、固定資産税評価額ではなく、不動産屋の査定、中立な不動産鑑定士に依頼することで、実際の取引価格に近い「時価」を算出してもらうことが重要です。
鑑定費用の目安:20万~40万円程度が多いと思われます。
②収支状況の詳細把握
年間収支の把握
- 年間賃料収入(空室率も考慮)
- 管理費、修繕積立金
- 固定資産税・都市計画税
- 損害保険料
- ローン返済額(元金・利息)
- 純収益(ネット・オペレーティング・インカム)
※将来の大規模修繕計画
→築年数に応じた修繕計画と費用を見積もり、事業継続に必要な資金を把握します。
③具体的な分割案を作成する
不動産の時価を基に、具体的な分割案を考えます。
分割の例案
- 妹への代償金:純資産4億3,000万円の1/4である1億750万円を、長男Bさんが妹に支払う
- 母の取得分:遺産の預貯金3,000万円と、自宅の配偶者居住権
- 長男の取得分:全ての不動産とローン債務を引き継ぐ
代償金の調整→必要に応じてBさんから母への代償金で調整。
④代償金調達方法の検討
1億円を超える代償金をどう用意するかが最大の課題ですが、以下のような例が考えられます。
調達方法の組み合わせ
- 遺産の預貯金:3,000万円を充当
- 事業性融資:金融機関からアパートローンを新規で借入
- 一部物件の売却:収益性の低い物件1棟を売却
- 分割払い:妹との合意で代償金の分割払いを設定
相続税の申告と納税

遺産分割が終わっても、それで全てが完了するわけではありません。一定の基準を満たす場合は、相続税の申告をしなくてはなりません。
相続税の申告・納付期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限内に現金で一括納付が原則です。
相続税の基本的な計算方法
基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(3人)= 4,800万円
本件の場合・・・
課税遺産総額 純資産4億3,000万円 – 基礎控除4,800万円 = 3億8,200万円
※単純計算です。条件によって、控除は異なります。
■配偶者の税額軽減 配偶者は、法定相続分(1億6,000万円以内)または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税が軽減されます。
■小規模宅地等の特例 自宅について、330㎡まで80%評価減の特例が適用される可能性があります。
詳細な計算は省きますが、5000万円前後の相続税がかかる可能性があります。
まとめ:不動産相続は、早めに専門家へ相談を

不動産オーナーの相続は、法律、税務、不動産評価、事業承継など、多くの専門知識が必要です。当事者だけで解決しようとすると、感情的な対立が深まったり、法的に不備のある合意をしてしまったりするリスクがあります。
相続税の申告期限という時間的な制約もあるため、問題が複雑化する前に、できるだけ早い段階で相続問題に詳しい弁護士へご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






