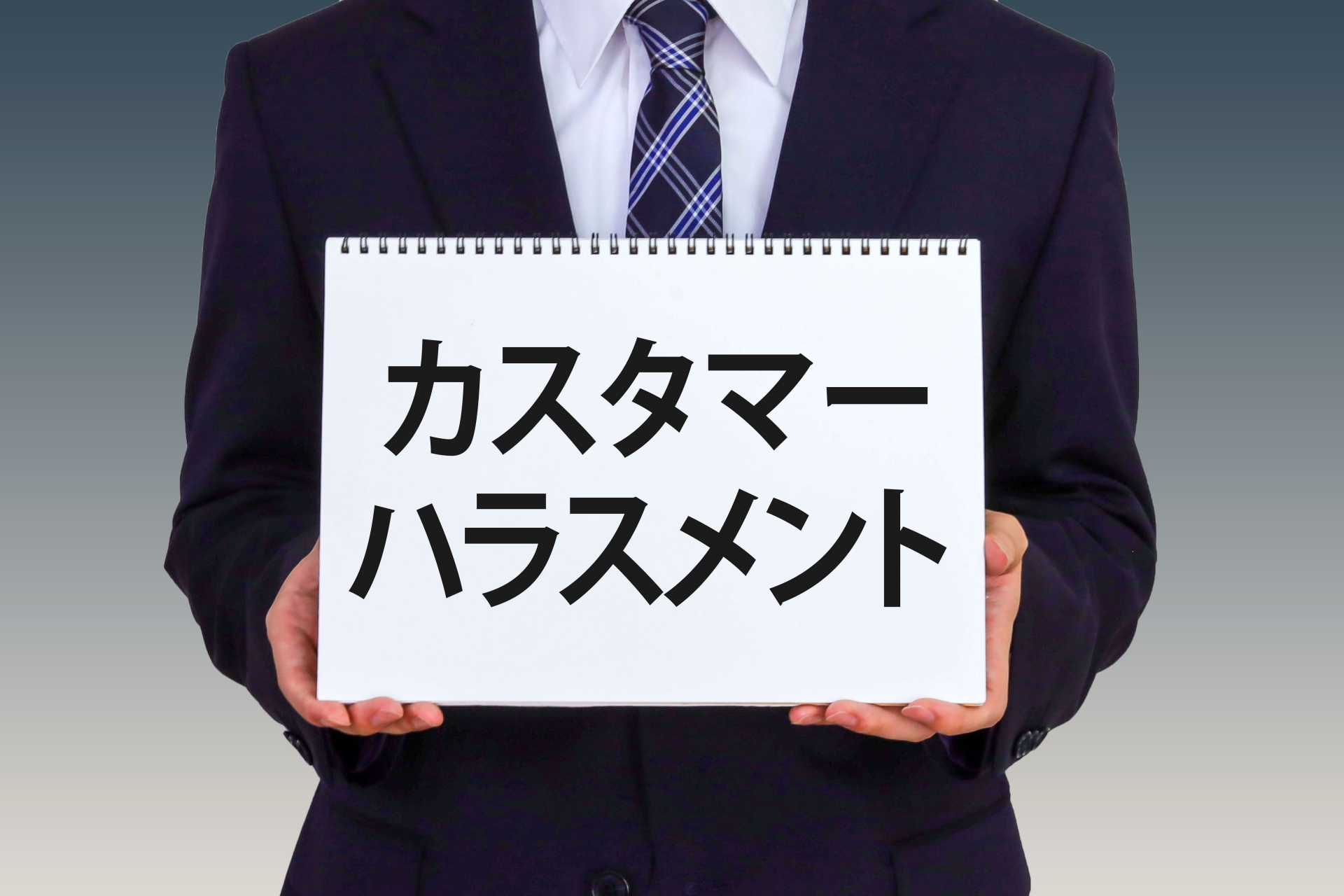
近年、企業が直面する労働問題は多様化の一途を辿っています。その中でも、特に深刻化し、多くの企業が対応に苦慮しているのが「カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)」です。顧客からの不当な要求や言動は、従業員の心身に大きな負担をかけ、時には企業全体の士気や生産性の低下を招きます。
「お客様は神様」という言葉が時に誤解され、理不尽な要求がまかり通る風潮は、決して従業員や企業にとって健全ではありません。
本コラムでは、急増するカスハラの実態と、企業が従業員を守るために講じるべき法的な位置づけ、具体的な対策について解説します。
カスタマーハラスメントとは何か?その実態と深刻性

カスハラとは、顧客や取引先などの第三者が、従業員に対して行う暴言、暴力、不当な要求、威圧的な言動、セクシュアルハラスメントなどの迷惑行為を指します。
クレーム対応中にエスカレートするケースや、製品・サービスとは無関係な個人的な感情に基づく嫌がらせなど、その内容は多岐にわたります。
カスハラが深刻な問題である理由は以下の通りです。
①従業員の心身への悪影響
暴言、暴力、理不尽な要求に晒されることで、従業員はストレス、不安、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などを発症し、休職や退職に追い込まれるケースも少なくありません。
②職場の雰囲気の悪化:
カスハラが発生すると、周囲の従業員も萎縮し、職場全体の雰囲気が悪化します。
③企業の生産性低下
従業員のモチベーション低下、離職率の増加、人材確保の困難化などにより、企業の生産性が低下します。
④企業のブランドイメージ毀損
従業員がカスハラの被害に遭っている事実が外部に漏れることで、企業の評判やブランドイメージが損なわれる可能性があります。
企業がカスハラ対策を講じる法的義務

「お客様とのトラブル」と片付けられがちだったカスハラですが、実は企業には従業員をカスハラから守るための法的義務が明確に存在します。
安全配慮義務(労働契約法第5条等)
企業(使用者)は、労働契約に伴い、従業員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っています。
この安全配慮義務は、従業員が顧客からのカスハラによって心身の健康を害することのないよう、適切な対策を講じることまで含まれると解されています。
もし企業が適切なカスハラ対策を怠り、その結果従業員が心身の不調をきたしたり、損害を被ったりした場合には、安全配慮義務違反として、企業が損害賠償責任を負う可能性があります。
労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)による措置義務
労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)は、職場におけるパワーハラスメントだけでなく、「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と定めています。
この「雇用管理上必要な措置」の中には、事業主が講ずべき措置に関する指針(厚生労働省告示)において、「顧客等からの著しい迷惑行為(以下「顧客等からのハラスメント」という。)に関する相談に対応することも望ましい」と明記されています。
直接的な義務化ではないものの、企業がカスハラ対策に積極的に取り組むことを強く推奨するものです。
さらに、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策として、事業主が取り組むことが望ましい具体的な措置が示されており、これらを講じないことは、安全配慮義務違反のリスクを高めることにも繋がりかねません。
その他の法的側面
その他にも、人権尊重の観点(企業は従業員の尊厳を尊重し、いかなるハラスメントからも保護する責任があると解されています)や、民法上の不法行為責任(カスハラの加害者が従業員に対して精神的苦痛を与えた場合、民法上の不法行為(民法第709条)として損害賠償責任を負う可能性があります)などから、企業は責任を負う可能性があります。
企業が講じるべきカスハラ対策の具体策

カスハラ対策は、単なる個別対応ではなく、組織全体で取り組む必要があります。以下の多角的なアプローチで対策を講じることが重要です。
方針の明確化と周知・啓発
カスハラに対する方針の明確化:
・カスハラを許容しないという企業の強い姿勢を明確に打ち出し、社内外に周知する。
・就業規則等にカスハラの定義、禁止規定、発生時の対応、懲戒規定などを明記する。
・顧客向けに「カスタマーハラスメントに対するご対応方針」などを明示し、迷惑行為に対しては毅然とした対応を取ることを伝える。
従業員への周知・啓発:
・研修や説明会を通じて、カスハラに対する従業員の意識を高める。
・カスハラの具体例、対応マニュアル、相談窓口の周知を徹底する。
・「一人で抱え込まず相談すること」の重要性を繰り返し伝える。
相談・対応体制の整備
相談窓口の設置:
・従業員が安心して相談できる窓口(社内窓口、外部窓口など)を設置する。
・相談者のプライバシー保護に最大限配慮し、相談内容が他に漏れないようにする。
・相談員は、カスハラに関する専門知識を持ち、適切な助言や対応ができる人材を配置する。
迅速かつ適切な事実確認と対応
・カスハラの相談があった場合は、速やかに事実関係を調査します。
・被害者、加害者(顧客)、目撃者などから状況を詳細に聞き取ります。
・事実が確認された場合、被害者への配慮、加害者への毅然とした対応を講じます。具体的には、顧客への注意・警告、サービス提供の中止、出入り禁止、場合によっては法的措置の検討などです。
再発防止措置
・カスハラの原因を特定し、同様の事案が再発しないための対策を講じる。
・顧客対応マニュアルの見直し、従業員への教育強化、設備改善などを検討する。
被害従業員への配慮
メンタルヘルスケア
・カスハラの被害に遭った従業員に対し、産業医やカウンセラーによる精神的ケアを提供する。
・必要に応じて休職制度や復職支援制度を適用し、心身の回復をサポートする。
配置転換や業務内容の変更
・被害従業員が精神的な負担から解放されるよう、一時的な配置転換や業務内容の変更を検討する。
プライバシーの保護:
・カスハラ被害に遭った従業員の個人情報や相談内容が外部に漏れないよう、厳重に管理する。
外部機関との連携
警察への通報
・カスハラが暴力、脅迫、器物損壊など犯罪行為に該当する場合は、躊躇なく警察に通報する。
・通報に際しては、従業員だけでなく企業として毅然とした態度で対応する。
弁護士への相談:
・カスハラ問題が複雑化したり、法的措置が必要となったりする場合には、早期に弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受ける。
・加害者への損害賠償請求や、事業活動妨害に基づく法的措置の検討など、状況に応じた法的対応を依頼する。
毅然とした対応と、現場への権限委譲
毅然とした対応」の具体化:
・カスハラの要求が不当であると判断した場合は、安易に要求に応じず、毅然とした態度で拒否する。
・「お客様だから」という理由で不当な要求を受け入れることは、更なるカスハラを助長しかねないため、このような対応は絶対しない。
・「当社は従業員の安全を守るため、ハラスメント行為には厳しく対処いたします。」といったメッセージを伝える練習をしたり、社内のマニュアルに組み込む。
現場への権限委譲とバックアップ:
・カスハラ対応は、多くの場合、現場の従業員が最初に直面するため、現場の従業員が単独で抱え込まないよう、上司や管理職が積極的に介入し、支援する体制を構築する。
・必要に応じて、現場の判断で対応を打ち切ったり、上層部へのエスカレーションを行う権限を付与する。
まとめ

カスハラは、従業員の尊厳を傷つけ、企業の持続的な成長を阻害する深刻な問題です。
単なる「クレーマー対応」として矮小化せず、企業の人権問題、安全配慮義務の問題として認識し、積極的に対策を講じることが不可欠です。
企業が従業員を守るための法的対策を講じることは、従業員のエンゲージメントを高め、安心して働ける職場環境を構築することに繋がります。
そして、それは結果として、企業と顧客との間に健全な関係を築き、長期的な企業価値向上にも貢献すると思われます。
法的に義務のあることは行う、そうでないことは行わないという姿勢を企業全体として共有し、毅然とした対応を行う事が必要です。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。






