
交通事故に遭ってしまった際、修理費用だけでなく「評価損」についても気になる方は多いのではないでしょうか。特にリース車両の場合、この評価損の扱いはさらに複雑になります。今回は、リース車両の交通事故における評価損請求のポイントについて解説します。
評価損とは何か?
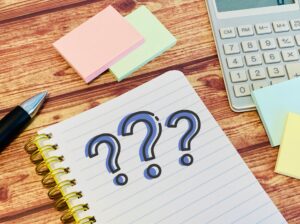
評価損とは、車両が交通事故により損傷し、修理によって外観や機能が回復したとしても、事故歴が残ることなどによって車両の市場価値が低下してしまう損害を指します。つまり、「事故車」というレッテルが貼られることで、売却時などに本来の価値よりも低い金額になってしまう分を損害として捉えるものです。
通常、評価損は常に認められるわけではありません。実際には以下のような事情を考慮して、評価損が認められるか否かが判断されます。
- 車種(高級車や外国車などか)
- 登録後の経過年数や走行距離
- 修理の内容と範囲(骨格部分の損傷か否か)
- 商品価値の低下が明らかかどうか
特に、登録からの年数が浅く、走行距離も少ない車両であればあるほど、評価損が認められやすい傾向にあります。
認定された評価損の金額は、通常、修理費の10〜30%程度が一つの目安です。
書籍に掲載されている判例では、以下のような割合が認められています:
- スマートブラバス(登録2年):修理費の20%
- スバル・インプレッサ(登録1年):修理費の20%
- BMW(登録1年8ヶ月):修理費の約30%
- ホンダステーションワゴン(登録約2年):修理費の10%
- 国産高級車(登録6ヶ月):修理費の30%
リース車両の場合、評価損は誰に帰属するのか?

通常の自家用車であれば、所有者である被害者が評価損を請求することになります。しかし、リース車両の場合、車両の所有者はリース会社であり、ユーザーは「借りている」立場です。
この点について、裁判所の判断では、評価損は車両の交換価値の減少として捉えられ、その損害は原則として車両の所有者であるリース会社に帰属すると考えられています。そのため、リース車両のユーザーが単独で評価損を請求することは、基本的に認められないとされています。
所有権と損害の関係についての法的理解
民法上、損害は「権利者」に発生するものとされています。リース車両において、所有権はリース会社にあるため、車両価値の減少という財産的損害は、原則としてリース会社が被るものとなります。これは、ユーザーが車両を「使用する権利」は有していても、「処分する権利(所有権)」を有していないことに起因します。
ユーザーが評価損を請求できる例外的なケース
原則としてユーザーは評価損を請求できませんが、例外的に請求が認められるケースも存在します。
リース会社とユーザーとの間で、評価損に関する請求権をユーザーに帰属させる旨の明確な合意や表示がある場合です。例えば、リース契約書にその旨が明記されている、あるいはリース会社がユーザーに評価損の請求を委任するなどの状況がこれにあたります。
リース解約料について

評価損をユーザーが請求できないとなると、評価損が生じている車に乗らざるを得ませんが、実務上、それは快適な車に乗れないという程度のこととしか評価されず、法的な損害とは認められません。
では、リース契約を解約する場合はどうでしょうか。事故車に乗るくらいであれば解約したいという方も多いでしょう。多くのリース契約では、途中解約を行った場合は、違約金が生じます。この違約金は加害者に請求できるのでしょうか。
この点、神戸地裁平成4年8月21日判決は、違約金は通常予見し得ない損害であるとして、事故の間の因果関係を否定しました。
しかし、近年、従来のリースとは異なる「カーサブスクリプション」サービスが普及しています。これらのサービスでは、より柔軟な契約条件が設定されている場合があり、評価損の取り扱いについても従来とは異なる判断がなされる可能性があります。
従来のリース契約では、違約金の請求は難しいでしょう。
リース車両と買換差額請求について

リース車両が事故で大破、修理費が時価を超える場合に、買替差額を請求できるでしょうか。つまり、リース車両が物理的に「全損状態」となった場合、つまり原型をとどめず修理も現実的でないほど破損してしまった場合、その車両が有していた交換価値(市場価値)も喪失したと考えられます。
このような場合、ユーザーはリース契約上、使用する利益を喪失することになり、結果的に新たな車を手配する必要が生じることになります。
この「新たな車を準備するために必要となる追加負担=買替差額」について、ユーザーが請求できるか否かが問題となります。
この点、「物理的全損」の場合は、車両の「所有者」はリース会社であり、ユーザーは「使用者」に過ぎないことから、ユーザーは買換え差額請求はできないとされています。
もっとも、経済的全損の場合は、一見すると、「使用者が損害賠償請求をすることはできないのでは?」と思われがちですが、判例や通説上は、所有権留保付き売買契約における買主による請求が認められるか否かと同様の論点とされており、リース契約でも類似の判断がなされる傾向にあります。
※川原田貴弘『物損(所有者でない者からの損害賠償請求)について』(赤本平成29年版)などによれば、使用者が交換価値の喪失という「現実的損害」を被った場合には、買替差額の請求は認められると整理されています。
たとえば、修理費が150万円、車両の時価が80万円だった場合、損害として請求できるのは原則「時価」のみですが、ユーザー側は「新たなリース車両の調達にかかる費用」が発生することから、その差額部分についても損害とみなして請求可能となるということです。
まとめ

リース車両の交通事故における評価損請求は、その性質上、車両の所有権がリース会社にあるため、ユーザーが直接請求することは難しいのが現状です。
もっとも、評価損が請求出来なくても、他の点できちんと主張立証すれば、現在の提示以上の損害を請求できる可能性もあります。特に、ケガをしている場合は、それが顕著です。
もし物損と同時にケガをしている場合
ケガをしている場合は、加害者に治療費を請求できますし、通院終了後に慰謝料も請求することができます。交通事故の慰謝料とは、被害者が交通事故によって受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償です。交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
入通院慰謝料は、入院期間や通院期間の長さによって決まりますし、後遺症慰謝料は、後遺障害の等級によって決まります。なお、死亡慰謝料は、被害者の属性や年齢などによって決まります。
慰謝料の金額は、保険会社と争いになることがほとんどです。
慰謝料は、通称「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準・財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)と言われる専門書に記載されている表が、基本的に基準として採用されています。
以下では、裁判基準の表を公開します(骨折等の場合)。

●表の見方
・入院のみの方は、「入院」欄の月に対応する金額(単位:万円)となります。
・通院のみの方は、「通院」欄の月に対応する金額となります。
・両方に該当する方は、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額となります。
(別表Ⅰの例)
①通院6か月のみ→116万円
②入院3ヶ月のみ→145万円
③通院6か月+入院3ヶ月→211万円
弁護士に依頼をすることによって、正しい慰謝料相場で保険会社と交渉したり、裁判の手続を代理で行うことができます。
まとめ

リース車両の交通事故における損害賠償請求は、リース契約の種類、約款の内容、車両の損害状況(分損か全損か)、ユーザーの修理意思など、多岐にわたる要素が複雑に絡み合います。特に、修理費用についてはユーザーによる請求が認められる可能性が高いものの、「具体的な損害」の認定には詳細な事実関係の立証が不可欠です。
もし、リース中の車両が交通事故に遭い、損害賠償請求に関してご不明な点やご不安な点がある場合は、ご相談ください。
もし弁護士特約に加入されていたら、弁護士費用の自己負担がなくなる可能性が高いです。
【弁護士費用特約】とは、ご自身が加入している、自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯している特約です。
弁護士費用特約が付いている場合は、交通事故についての保険会社との交渉や損害賠償のために弁護士を依頼する費用が、加入している保険会社から支払われるものです。
被害に遭われた方は、一度、ご自身が加入している各種保険を確認してみてください。わからない場合は、保険証券等にかかれている窓口に電話で聞いてみてください。
弁護士特約の費用は、通常300万円までです。多くのケースでは300万円の範囲内でおさまります。
物損だけではなく、骨折や重傷の場合は、一部超えることもありますが、弁護士費用特約の上限(通常は300万円)を超える報酬額となった場合は、越えた分を保険金からいただくということになります。
なお、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する場合、どの弁護士を選ぶかは、被害に遭われた方の自由です。
※ 保険会社によっては、保険会社の承認が必要な場合があります。
弁護士費用特約を使っても、等級は下がりません。弁護士費用特約を利用しても、等級が下がり、保険料が上がると言うことはありません。
弁護士費用特約は、過失割合10:0の時でも使えます。被害者に過失があっても利用できます。
まずは、ご自身やご家族の入られている保険に、「弁護士特約」がついているか確認してください。火災保険に付いている事もあります。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。












