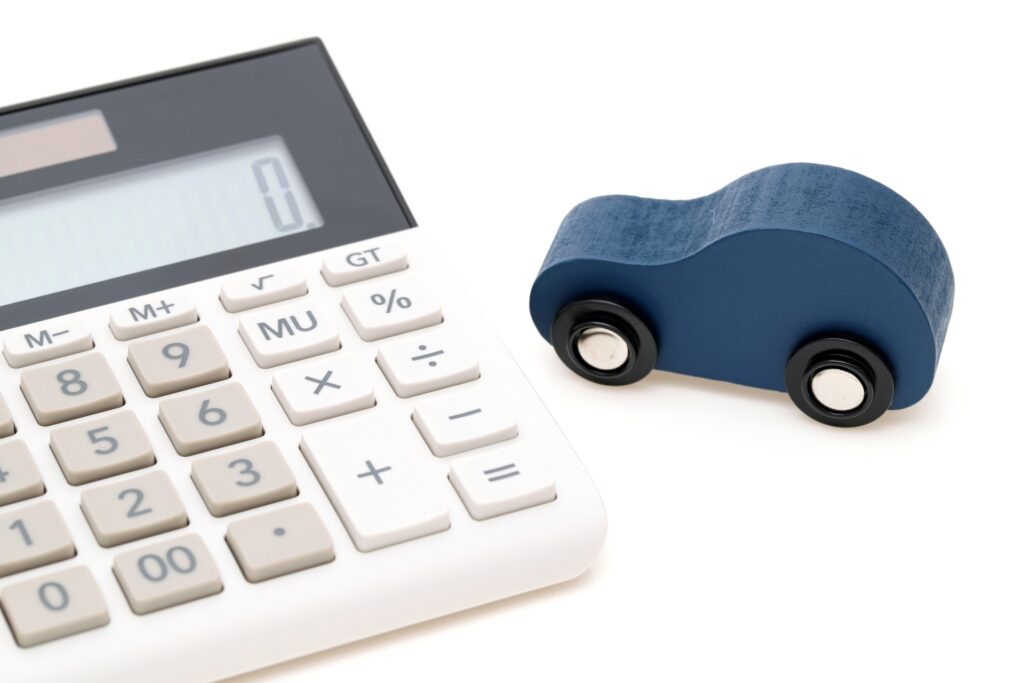
交通事故で車が破損した場合修理をしますが、修理代に加えて「評価損」という損害を請求できるケースがあります。評価損とは、事故が原因で、事故前より車両価格のが落ちた分の損を言います。本記事では、交通事故における評価損について、どのような場合に認められるのか、裁判例はどう判断しているのかを、弁護士の視点から解説いたします。
評価損とは何か?

評価損とは、事故により損傷した車両が「修理可能」であっても、修復歴や外観・機能上の問題から中古車市場での価値が下がることをいいます。たとえば、修理により見た目が回復していても、骨格にダメージが残っていれば買い手は敬遠しがちです。
こうした市場での価値の減少は、損害賠償の対象として認められる可能性があります。
裁判例から見る評価損の判断基準

評価損は常に認められるわけではありません。実際には以下のような事情を考慮して、評価損が認められるか否かが判断されます。
- 車種(高級車や外国車などか)
- 登録後の経過年数や走行距離
- 修理の内容と範囲(骨格部分の損傷か否か)
- 商品価値の低下が明らかかどうか
特に、登録からの年数が浅く、走行距離も少ない車両であればあるほど、評価損が認められやすい傾向にあります。
例えば、5年経過または6万km以上走行した国産車では、評価損が否定される傾向が強いといえます。
どのくらいの割合で認められるのか?
認定された評価損の金額は、通常、修理費の10〜30%程度が一つの目安です。
書籍に掲載されている判例では、以下のような割合が認められています:
- スマートブラバス(登録2年):修理費の20%
- スバル・インプレッサ(登録1年):修理費の20%
- BMW(登録1年8ヶ月):修理費の約30%
- ホンダステーションワゴン(登録約2年):修理費の10%
- 国産高級車(登録6ヶ月):修理費の30%
このように、車両の価値や損傷の程度により、修理費に対する評価損の割合が変動することがわかります。
評価損が否定された裁判例もある
一方で、以下のような場合には評価損が認められなかった事例もあります:
- 登録から9年、走行距離8万km超のメルセデスベンツ
- 登録から8年7万km超のベントレー
- 登録から1年1ヶ月の国産車(損傷が軽微と評価された)
つまり、年式が古く走行距離が多い車や、損傷が軽微であると判断された場合には、「評価損」が否定される可能性があるということです。
評価損請求の実務上のポイント

証拠の重要性
評価損を実際に請求する際には、単に「価値が下がった」と主張するだけでは不十分です。以下のような証拠を揃えることが重要です:
- 修理前後の写真(損傷状況と修理箇所を明確に)
- 修理見積書・明細書(どの部分をどのように修理したかを詳細に)
- ディーラーや査定士の意見書(市場価値の下落について専門家の見解)
- 同型車両の中古車相場データ(修復歴ありとなしの価格差)
保険会社との交渉における留意点
保険会社は評価損の支払いに消極的な傾向があります。「修理すれば元通り」「評価損は認められない」といった対応を受けることも少なくありません。
しかし、適切な証拠と法的根拠があれば、評価損の支払いを受けることが可能なケースもあります。特に以下のケースでは、積極的に評価損を主張すべきでしょう:
- 新車登録から3年以内、走行距離3万km未満の車両
- 骨格部分(フレーム等)に損傷がある場合
- 高級車や外国車での事故
- 修理費用が車両価格の相当割合に達する場合
法律上の評価損の扱い
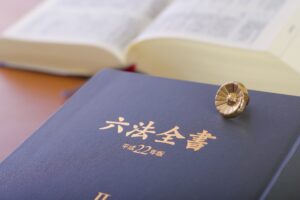
評価損は民法709条に基づく「不法行為による損害賠償請求」の一部です。
重要なのは、評価損が「現実に市場価値の下落がある」と合理的に証明される必要があるという点です。修理費用の見積書や修理明細だけでなく、ディーラーや査定士の意見書などを提出することが、評価損の認定において有効です。
今後起こりえる問題

電気自動車(EV)と評価損
近年増加している電気自動車については、バッテリー部分の損傷が評価損に大きく影響する可能性があります。EVのバッテリーは高額であり、わずかな損傷でも交換が必要となるケースがあるため、従来の判断基準では測りきれない新たな論点となっています。
自動運転車両への影響
将来的に自動運転技術が普及した場合、センサーやコンピューター部分の損傷が評価損にどのような影響を与えるかも注目されています。目立った判例は、現時点で公表されていません。
ご相談 ご質問

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
交通事故の初動対応は、その後の補償に大きく影響します。「物損で済ませたが、後から痛みが出てきた」「人身事故に切り替えたいが、手続きが不安」「加害者や保険会社とのやり取りに困っている」という方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。












