
離婚を考えたとき、どうしても気になるのが離婚に伴う経済的負担についてです。離婚するにあたり、離婚前後に元妻や子どもにどこまで金銭的な責任が発生するのか、疑問や不安を抱える男性は多いのではないでしょうか。概略を説明していきます。
離婚後の「生活費」とは?
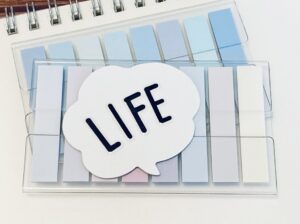
離婚後の生活費という言葉は曖昧で、人によって捉え方が異なります。しかし、法的に整理すると、以下のような費用が対象となります。
- 養育費(子どもがいる場合)
- 扶養的財産分与(元妻の生活支援)
- 財産分与(婚姻中に築いた財産の清算)
- 慰謝料(特定の離婚原因がある場合)
一方で、婚姻中に支払っていた「婚姻費用」は、離婚後には不要になります。婚姻費用は、夫婦であることを前提とした生活費の分担であるため、離婚が成立した時点で支払い義務は終了します。
養育費は支払わなければならないのか?
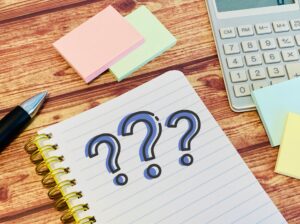
子どもがいる場合、離婚後も「養育費」の支払い義務は続きます。これは親である以上当然の責任であり、親権の有無に関係なく、非監護親(多くの場合は父親)が監護親に対して支払うことになります。
養育費の支払期間は、原則として子どもが成人するまで(現在は18歳が成人年齢ですが、養育費との関係では20歳が原則)とされていますが、大学進学などを見越して22歳までと定める例も増えています。
支払額については、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に、両親の年収・子どもの年齢・人数に応じて決定されます。たとえば、年収600万円の会社員の父親が子ども1人を育てていない場合、月5~8万円の支払いが目安となるケースが多いです。
財産分与の考え方と注意点

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を清算・分配することを意味します。これは、婚姻中にどちらの名義で取得したかにかかわらず、原則として2分の1ずつ分けるのが基本です。
たとえば以下のような財産が対象になります。
- 預貯金
- 不動産(自宅など)
- 自動車
- 有価証券(株・投資信託など)
- 退職金(一定の条件下で)
注意が必要なのは、財産分与は「離婚後2年以内」に請求しなければならないということです(民法768条)。また、夫婦間での合意が難しい場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
たとえば、自宅を購入する際に自分名義でローンを組んだ場合でも、婚姻中に夫婦が協力して築いたものであれば、元配偶者にも持分が発生する可能性があります。
また、財産分与の中には、単なる分配にとどまらず、相手の生活保障的な意味を持たせる「扶養的財産分与」が含まれることもあります。
子どもの教育費はどこまで負担するのか?

通常、養育費の中には公立学校に通うことを前提とした教育費が含まれています。しかし、私立学校の学費、塾代、習い事費用など、いわゆる「特別費用」は別途協議が必要です。
たとえば、母親が「子どもを私立中学に通わせたい」と希望しても、父親が事前に合意していなければ、その費用まで負担する義務はありません。ただし、離婚協議書などで私立学費や塾代の分担を明記していた場合には、その取り決めに従うことになります。
教育費について揉めるのを防ぐためにも、離婚時に「どこまで費用を負担するか」を明文化しておくことが重要です。
慰謝料はどうなるのか?

慰謝料は、不貞行為や暴力など、離婚原因が一方にある場合に支払われるものです。たとえば、不倫をしていた場合やDVがあった場合には、精神的損害に対する賠償として慰謝料が発生します。
ただし、慰謝料は一括で支払うのが一般的で、長期にわたって生活費のように支払い続けるものではありません。また、婚姻生活の破綻がどちらか一方の責任によるものでない場合は、慰謝料が認められないケースもあります。
扶養的財産分与という考え方

元妻が病気で働けない、高齢で就労が困難といった事情がある場合、生活の再建が困難であると判断されれば、「扶養的財産分与」が認められることがあります。これは生活を支えるための一時金や一定期間の定期支払いという形で支払われます。
しかし、これは義務ではなく、裁判所の判断や当事者間の合意によって決まるため、常に支払いが必要になるわけではありません。
再婚・収入減など状況が変わった場合

離婚後に再婚した場合や、収入が大幅に減少した場合、養育費の減額を求めることができます。この場合は、家庭裁判所に対して「養育費減額調停」を申し立てる必要があります。
ただし、自己判断で支払いを減額・停止することはできません。調停や合意書がないまま支払いを止めてしまうと、後日未払い分を一括で請求される恐れがあります。
金銭的トラブルを防ぐために大切なこと

離婚後の生活費に関するトラブルを防ぐためには、離婚時に必ず「離婚協議書」などを書面の形で作成することをおすすめします。
また、「将来的に生活状況が変わった場合は再協議する」などの条項を設けておくことで、柔軟に対応できる仕組みも整えることが可能です。
まとめ:責任と将来設計の両立を

離婚後も、父親として、また元配偶者との金銭的な関係を維持することは簡単ではありません。しかし、法律上の責任を果たすと同時に、自身の生活設計も冷静に見直す必要があります。
義務と任意の区別をしっかり把握し、書面に残すことで、感情的な対立を避け、子どもや新しい人生のために前向きなスタートを切ることができます。
離婚は終わりではなく、再出発のきっかけです。金銭面の不安を最小限に抑えるためにも、正しい知識と準備を持って臨みましょう。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






